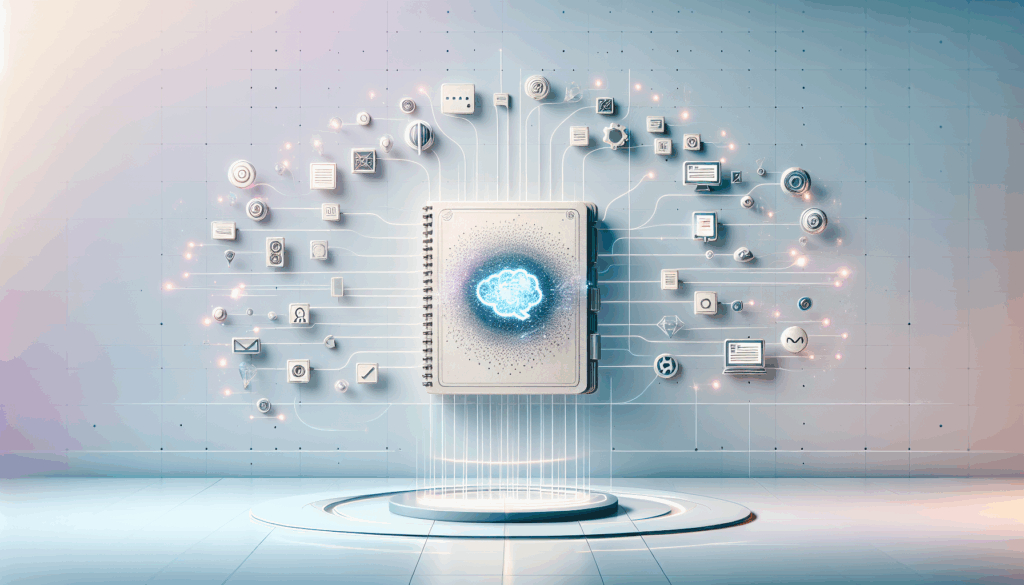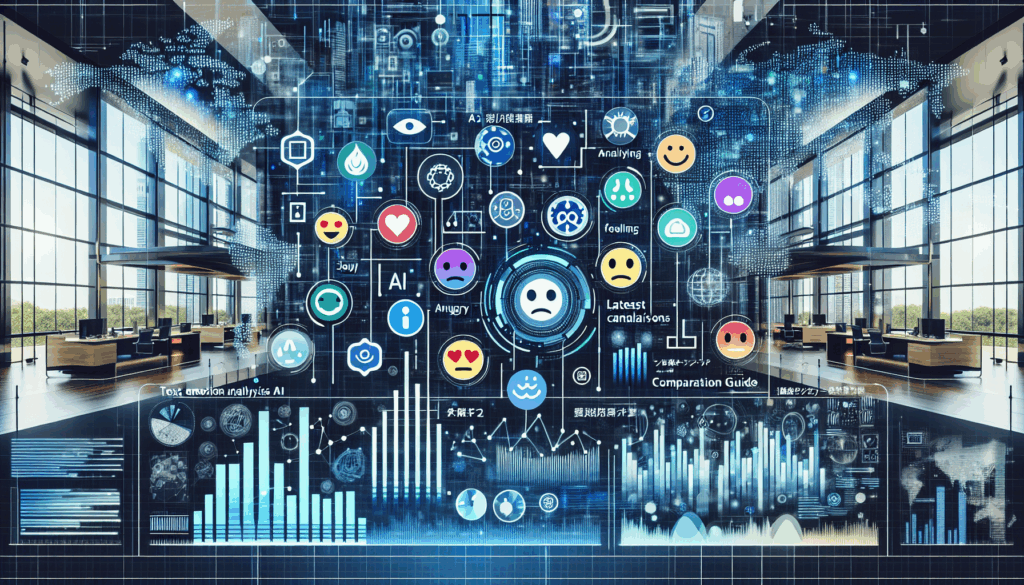(最終更新日: 2025年09月19日)
情報が散らかり、検索にも時間がかかる、NotionやEvernoteで迷っている——そんなあなたへ。
いま注目のAIノート「Mem」を、最新の仕様と実際の使い勝手から、強み・弱みまでフェアに解説します。
読み終えるころには、自分やチームに合うか、費用感、導入の一歩目がはっきり分かります。
本記事では、Memの2つの製品と会社の全体像、開発者向け基盤も含めた主な機能、料金の最新動向、他ツールとの違いと選び方、具体的な使い方、FAQまでを一気にカバー。
公式発表や検証結果も踏まえ、2025年の「いま」使える情報だけを厳選してお届けします。
データの移行や連携、チーム運用の不安にも具体策で答えます。
Memとは?2つのプロダクトと企業全体像を徹底解剖
当セクションでは、Memの名称の意味、2つのプロダクトの違い、そして運営企業Mem Technologiesの全体像を整理して解説します。
なぜなら、同一ブランドの下で「Mem(AIノートアプリ)」と「Mem0(AIメモリ基盤)」が併走しており、用途や対象が異なるにもかかわらず混同されやすいからです。
- Memの意味とブランド戦略
- Memの歴史と創業ストーリー
Memの意味とブランド戦略
結論として、Memは「AIノートアプリ(Mem)」と「AIメモリ基盤(Mem0)」の二層ブランドで構成され、前者は業務ツール、後者は開発インフラという役割で明確に分かれます。
この分離は、日々の知的生産を支える体験と、その土台となるパーソナライズ・コスト最適化の技術基盤を別設計にし、価値を最大化する狙いがあるためです。
Memは「自己組織化するワークスペース」を掲げ、AI検索や関連ノート提案、チームでの集合知化を特徴とする毎日の仕事道具です(出典: Mem 公式サイト)。
一方のMem0は、LLMアプリに永続メモリとトークン圧縮によるコスト削減、SOC 2やBYOK対応などエンタープライズ要件を提供するB2Bインフラです(出典: Mem0 公式サイト)。
ブランドの根底には「個人が情報を所有するMe API」という長期ビジョンがあり、アプリと基盤が相互に学習する循環を描いています(出典: Why We Started Mem)。
また名称の由来については、公式ヘルプのFAQ「What does mem mean?」で“記憶/メモ”の語感とブランド意図が説明されています(参考: Mem Help & Support)。
資金面ではトップティアの投資家から累計約2,900万ドルを調達し、シリーズA時の評価額は約1.1億ドルと報じられています(参考: PitchBook)。
したがって、プロダクトの選定では業務ツールとしてのMemと、AIアプリ実装で文脈保持を担うMem0を明確に使い分けると判断しやすくなります。
Memの歴史と創業ストーリー
Memは、共同創業者Kevin MoodyとDennis Xuが“整理いらずの自己組織化”に挑むため2017年に立ち上げたプロジェクトです。
従来のフォルダやタグ前提の知識管理が思考の速度を阻害すると捉え、AIが文脈で情報を浮上させる体験をつくる必要があったためです(出典: Why We Started Mem)。
同社は2021年にa16z主導で560万ドルのシード、2022年にOpenAI Startup Fund主導で約2,300万ドルのシリーズAを調達し、事業基盤を強化しました(参考: Clay)。
初期版のMem 1.0はキャプチャと検索体験を磨き、現在はMem 2.0としてAIチャットやCopilotなど“思い出させる”機能を中核に発展しています(参考: Mem 公式ブログ)。
筆者はITスタートアップ支援の現場で、営業や研究職の“断片メモ”が業務の隠れ在庫になる事例を多く見てきました。
だからこそ、AI×知識管理は「拾い集め→再利用→意思決定」までの摩擦を下げる投資対効果の高い領域として注目されます。
Memの歩みはこの課題に正面から向き合っており、個人向けの成功学習がMem0の企業導入を後押しする好循環(フライホイール)を狙っています。
AIエージェントの比較や文脈保持の設計思想を俯瞰したい方は、関連解説も参考になります(参考: 2025年最新AIエージェント市場徹底比較)。
業務に直結する生成AIスキルを体系的に学ぶなら、実務特化カリキュラムの活用が近道です(参考: DMM 生成AI CAMP)。
Memの機能・特徴:なぜ注目されるのか
当セクションでは、Memのコアとなる機能群と設計思想、対応プラットフォーム、そして開発者向けのMem0までを体系的に解説します。
なぜなら、知識管理の正解が「構造づくり」から「AIによる再浮上」へと移る中、Memの価値は個別機能ではなく全体設計で理解することが重要だからです。
- AIによる“自己組織化”ワークスペースの本質
- 主な機能一覧と技術ポイント
- 対応プラットフォーム・アプリ
- Mem0:開発者向けメモリレイヤーの概要
AIによる“自己組織化”ワークスペースの本質
Memの本質は「整理せずに貯める」ことを前提に、AIが文脈で再発見してくれる“自己組織化”ワークスペースだという点にあります。
手動のフォルダ分けやタグ運用は時間がかかり、認知負荷が高いからです。
筆者も過去に他ツールでタグを細分化し過ぎて「どのタグで保存したか」を毎回思い出す負債に追われ、生産性が大きく落ちました。
Memではキャプチャに集中しておけば、作業中に過去ノートが自動で立ち上がるCopilotや、意味ベースで横断検索できる体験によって後から素早く引き出せます。
創業者はユーザーの個人的ナレッジグラフ「Me API」やJ.A.R.V.I.Sのような相棒像を掲げており、この哲学が“自己組織化”として具現化しています(出典: Why We Started Mem)。
結果として、整理はAIに任せ、思考は止めずに深められるのがMemの最大の魅力です。
主な機能一覧と技術ポイント
Memは「Mem Chat」「関連ノート自動提案(Copilot)」「AIコレクション」「スマート検索」「外部連携・API」の5本柱と、Elasticsearch×Pineconeのハイブリッド検索基盤で構成されます。
これらが連動することで「キャプチャ→文脈での再浮上→生成AIでの実行」までが一気通貫になるからです。
検索はキーワードと意味検索を使い分け、類似メモのサジェストまで自動化されるため、情報探索の反復を大幅に短縮できます。
基盤はインデックスにElasticsearch、セマンティック検索にPineconeを用いる設計で、実運用に耐える高速性と関連性を両立します(参考: Building Mem: The AI Notes App (feat. Pinecone))。
以下の図は、Memのハイブリッド検索アーキテクチャの概念を示したものです。
| 機能 | できること | 主な出典 |
|---|---|---|
| Mem Chat | 自分のノート群を元に検索・要約・下書き生成を実行 | Chat in Mem/Find and Use Facts… |
| 関連ノート自動提案(Copilot) | 編集中の文脈に合わせて過去ノートをサイドで提案 | Mem 公式サイト |
| AIコレクション | フォルダ代替としてAIが関連グルーピングを支援 | Mem 公式サイト |
| スマート検索 | 自然言語・意味ベースでの横断検索 | Pinecone特集記事 |
| 外部連携 | メール転送、Chrome拡張、Zapier/Makeなど | Integrations – Help |
| API | REST APIでノート/コレクションの操作が可能 | Build with the Mem API |
- Chat in Mem – Mem Help & Support
- Find and Use Facts with Mem Chat
- Building Mem: The AI Notes App (feat. Pinecone)
- Integrations – Mem Help
- Build with the Mem API
競合理解を深めたい方は、比較観点の基礎としてNotion AIの使い方と活用例も合わせて参照すると違いが見えやすくなります。
対応プラットフォーム・アプリ
MemはMac・Windows・iOSの公式アプリとWebに対応し、2025年時点でAndroidは未リリースというのが公式見解です。
公式ヘルプでは「現在、MemにはまだAndroidアプリはありません」と明記されており、ここが最新かつ信頼できる一次情報です(出典: Is there an Android app? – Mem Help)。
Androidユーザーは当面Web版のホーム画面追加やメール転送連携でカバーするのが現実的で、音声起点のメモ取りは高精度録音デバイスと組み合わせると効率が上がります(例: PLAUD NOTE)。
デスクトップ/モバイルアプリのダウンロード情報は公式ページで随時更新されるため、乗り換えや導入時は最新版を確認してください(参考: Mem Download)。
| 項目 | ステータス | 出典 | 最終確認 |
|---|---|---|---|
| Mac | 公式アプリ提供 | Mem Download | 2025/09/15 |
| Windows | 公式アプリ提供 | Mem Download | 2025/09/15 |
| iOS | 公式アプリ提供 | Mem Download | 2025/09/15 |
| Web | ブラウザで利用可 | Mem 公式サイト | 2025/09/15 |
| Android | 未リリース(公式にて明記) | Mem Help | 2025/03/26 |
Mem0:開発者向けメモリレイヤーの概要
Mem0はLLMアプリに永続的な“記憶”を与えるメモリレイヤーで、コスト最適化と高度なパーソナライゼーションを同時に実現します。
チャット履歴の圧縮でプロンプトトークンを最大80%削減し、SOC 2やHIPAA対応、BYOKなどエンタープライズ要件も満たすからです(出典: Mem0 公式)。
たとえば医療アシスタントなら患者の嗜好や履歴を継続記憶し、教育分野では学習スタイルに合わせて対話内容が進化し、CRMでは長期商談の文脈維持に効きます。
公開事例ではパーソナライズの向上とトークンコストの大幅削減が報告され、実運用での価値が確認されています(出典: Mem0 公式)。
自社で類似の仕組みを構築する場合は、基礎としてRAG構築のベストプラクティスやOpenAI API実装ガイドを押さえておくと設計判断が速くなります。
結論として、Mem0は「パーソナル化×コスト効率×安全性」を両立させて、現場投入可能なAI体験の実装を加速する選択肢です。
Memの料金体系:最新版情報と将来予測
当セクションでは、Memの料金体系について最新状況と将来の相場観を整理して解説します。
なぜなら、ベータから有料化への移行は個人・チームの予算や運用方針に直結し、誤情報に左右されない判断基準が必要になるからです。
- 2025年9月時点の料金:現状は無料ベータ
- 過去の価格モデルと将来的な相場感
2025年9月時点の料金:現状は無料ベータ
2025年9月時点でMem 2.0はアルファ/ベータ期間に限り無料で利用できます。
公式ヘルプはテスト期間中の無料提供と正式リリース時に価格を発表する方針を明記しています(出典: What is the pricing for Mem?)。
たとえば新規ユーザーでも請求は発生せず、多くのAI機能を検証できるため、導入前の実地評価に適しています。
一方でベータ終了は予告なく訪れる可能性があるため、重要ノートのエクスポート手順やチームの承認フローを今のうちに整えておくと安心です。
リリース直前に慌てないよう、公式FAQを定期的に確認し通知設定やメール登録でアップデートを逃さない体制を作りましょう(出典: What is the pricing for Mem?)。
価格発表後の比較判断には、当サイトのガイド「AIツールの選び方完全ガイド」が参考になります。
過去の価格モデルと将来的な相場感
旧情報と第三者の記載を総合すると、個人向けは月8〜15ドル程度、チームはカスタム価格が相場観として妥当です。
これは複数ソースで同水準が繰り返し示され、同カテゴリ製品の価格帯とも大きく乖離しないためです。
以下の早見表に主要ソースの記載をまとめます。
| 情報源 | プラン | 価格(USD) | 注記 |
|---|---|---|---|
| Fahim AI(Notion vs Mem 比較) | プレミアム | $8.33/月 | Mem 1.0情報または推定の可能性 |
| Fahim AI(Mem AI Review) | Teams | カスタム | チーム向けはカスタム価格表記 |
| TheNeuron.ai | 有料プラン | $8〜15/月 | 一般的な市場推定 |
- (出典: Notion vs Mem: Which AI Note-Taking App is Best in 2025? – Fahim AI)
- (出典: Mem AI Review: Best Note-Taking App in 2025? – Fahim AI)
- (出典: Our Honest Review of Mem.ai (2024) – The Neuron)
ただし、これらは現行のMem 2.0の公式価格ではなく、推定もしくは旧バージョンの情報として取り扱うべきです。
比較の際は、代替候補の料金・機能も並べて検討すると判断の精度が高まります(参考: [2025年最新版] Notion AIの本当の使い方と活用例)。
音声主体のワークフローを強化したい場合は、録音から文字起こし・要約まで自動化できるツールの併用で費用対効果を高められます(PLAUD NOTE)。
公式発表が出たら、プラン別の機能差とチーム単価、推論コストの内訳まで確認し、導入の可否と予算を速やかに確定しましょう。
Memと他ノートアプリとの違いと選び方
当セクションでは、Memと他の代表的なノートアプリ(Notion・Evernote)の違いと、目的別の最適な選び方を解説します。
なぜなら、各ツールは「情報の持ち方」と「探し方」の思想が大きく異なり、相性を間違えると運用コストや成果が大きく変わるからです。
- 競合比較:Mem vs Notion vs Evernote
- Memが合う・合わないユーザー像のまとめ
競合比較:Mem vs Notion vs Evernote
結論は、Memは“探さずに見つかる”自己組織化とAI検索に最適、Notionは構造化・テンプレ活用が得意、Evernoteは従来型のノートブック分類に安心感がある、という明確な住み分けです。
Memは意味検索や関連ノートの自動提示(Copilot)などAIレイヤーを中核に据え、Notionはデータベースとテンプレートで自由度高く構造化でき、Evernoteはノートブック/タグ中心の整理で迷いにくい設計です。
例えば会議メモが日々増える状況では、Memは後からAIが横断要約や関連抽出を行うのに強く、Notionは会議テンプレや議事録DBを作り込める点が光り、Evernoteは定番のファイリング感覚で素早く蓄積できます。
以下の比較表で、特徴・AI機能・コラボ・料金の観点を一目で確認できます。

| 項目 | Mem | Notion | Evernote |
|---|---|---|---|
| 思想/特徴 | 自己組織化するワークスペース、第二の脳 | ブロックとDBで高度に構造化 | ノートブック/タグで伝統的に整理 |
| AI機能の中核 | Mem Chat、Copilot、セマンティック検索 | Notion AIで生成・要約・補助 | AI強化は限定的(比較基準上) |
| 検索の強み | 意味/文脈で横断的に再発見 | キーワード中心+一部AI補助 | キーワード+タグ/ノートブック |
| 自動提案 | 関連ノートのプロアクティブ提示 | プリセットは少なめ | 自動提示は限定的 |
| テンプレ/DB | 意図的に最小限 | 豊富なテンプレとDB関係 | テンプレは基本的 |
| コラボ | 共有ノート/コレクションでリアルタイム協業 | Wiki/プロジェクト/DBで強力 | 共有と共同編集は基本対応 |
| オフライン | iOS/デスクトップ/ウェブで対応 | 制限あり | アプリに依存 |
| 料金 | Mem 2.0ベータは無料、正式価格は未発表 | 無料/有料プランあり | 無料/有料プランあり |
構造を先に設計しながらチームの情報基盤を作るならNotion、まずは未整理のまま放り込み後からAIで回収したいならMem、従来の分類モデルに馴染みがあるならEvernoteが向いています(NotionのAI活用については[2025年最新版] Notion AIの本当の使い方も参考になります)。
参考:
- Mem公式:Notion vs Mem
- Mem公式:Evernote vs Mem
- Mem公式ブログ:Building Mem(Pinecone特集)
- Memサポート:料金(Mem 2.0ベータは無料)
Memが合う・合わないユーザー像のまとめ
結論は、日々増える未整理情報をまず集めて後からAI検索・要約で“再発見”したい人にはMemが最適で、情報スキーマを作り込みたい人はNotion等の併用が堅実です。
理由は、Memが「キャプチャ優先→AIが自己組織化・関連提示」という流れを得意とし、手作業のフォルダ分けやタグ設計を最小化できるからです。
一方で、プロジェクト管理やリレーショナルDB、テンプレ主導で精緻に運用したい場合はNotionの強みが活きます。
現時点ではMem 2.0はベータ中で無料提供、正式価格は未発表である点も選びやすさにつながります(参考は下記)。
モバイル中心でAndroid必須の人は現状の非対応が制約になり得るため注意が必要です(参考は下記)。
なお「Which is better, mim or mem?」という検索は誤記として見かけますが、AIノートアプリMemを指す前提なら“AIで探し直せること”を重視する人にフィットし、構造先行派や厳密なワークスペース設計を求める人はNotionや既存運用のEvernoteと棲み分けましょう。
会議や取材で音声→メモ化が多い人は、録音から文字起こし・要約まで自動化できるPLAUD NOTEや、用途に応じた比較としてAI文字起こしツール徹底比較の活用も相性が良いです。
参考:
Memの具体的な使い方ガイド
当セクションでは、Memのキャプチャ、AI活用、共有運用までを「今日から使える手順」として解説します。
なぜなら、Memは自己組織化を前提とするため、はじめに正しい流れを掴むと検索精度も提案品質も一気に伸びるからです。
- 基本のメモ作成・情報キャプチャの流れ
- AI活用のコツ:Mem ChatとCopilotによる知識発見術
- チームで使う時のポイント
基本のメモ作成・情報キャプチャの流れ
結論は「入れ方を増やして摩擦を減らす」ことが最短で効果を出すコツです。
理由は、MemのAIは投入データが多様であるほど関連付けと再浮上が賢くなる設計だからです。
おすすめの基本フローは「素早く書く→外部ソースを取り込む→AIコレクションで軽く整える→スマート検索で呼び出す」です。
具体的には、キーボードでMarkdown入力しつつ、重要なWebページはクリッパー、メールは転送、会議や移動中は音声メモを使い分けます。
初期設定ではメール転送アドレスの登録やChrome拡張の導入を先に済ませると、その日から情報の取りこぼしがゼロに近づきます。
最後に、毎日1回「本日のメモ」コレクションをAIに自動提案させる習慣を作ると、翌日の検索ヒット率が体感で上がります。
AI活用のコツ:Mem ChatとCopilotによる知識発見術
結論として、Mem Chatで「質問駆動の検索」を行い、作業画面ではCopilotの自動提案を受ける二段運用が最も生産的です。
理由は、Chatが横断要約と下書き生成に強く、Copilotが「今」の文脈に合う過去ノートを能動的に浮上させるからです。
議事録の要約は、制約と出力形式を指定したプロンプトを使うと一発で整います。
例えば次のように投げると要約品質が安定します。
あなたは議事録要約者です。以下のmem群を読み、5つの論点と担当/期限を抽出し、最後に3行で全体要約:
- 書式: 箇条書き、各論点は1行、担当は@記法、期限はYYYY-MM-DD
- トーン: 事実ベース、推測禁止
- 抜けがある場合は「未定」と明記なお、Mem Chatは自分のノートに基づく回答を返しつつ、公開Webは2021年頃までの情報に限られるため、最新ニュースは別途確認が必要です。
議事録作成や精度比較の観点は、実務者向けの比較記事も参照すると設計判断が速くなります(例: 【比較2025年最新版】AI議事録作成ツール徹底比較 や プロンプトエンジニアリング入門)。
チームで使う時のポイント
結論は「共有の単位とタグ運用を最小限に定義し、あとはAIの再浮上に任せる」が最適です。
理由は、厳密なフォルダ設計よりも、共有コレクションと一貫タグによりAIが関係性を学習しやすくなるからです。
まずはプロジェクトごとに共有コレクションを作り、議事録・決定事項・ToDoの3テンプレを運用標準にします。
次に、タグは「#決定 #課題 #次回」など最大10個程度の共通セットに絞ると、ノイズが減って検索が安定します。
会議の素材作りには高精度の音声→要約デバイスを併用するとキャプチャ品質が跳ね上がります(例: PLAUD NOTE
![]() を使えば多言語対応の自動文字起こしと要約が可能です)。
を使えば多言語対応の自動文字起こしと要約が可能です)。
最後に、AI導入の注意点として「公開範囲の既定」「機密の取扱い」「Chatへの質問ルール」を簡潔に文書化し、初回オンボーディングで徹底することが成功率を大きく左右します。
他のリアルタイム編集ツールの運用思想や分担も学びになるため、補助線として比較観点を押さえると良いでしょう(例: リアルタイム共同編集AIツール徹底比較)。
よくある疑問とその答え(FAQ)
当セクションでは、Memに関して多く寄せられる疑問に簡潔かつ実務視点で答えます。
名称の紛らわしさや他サービスとの違いが導入判断を遅らせる要因になっているためです。
- memって何?(memの意味・英語スラング/IT用語の違い)
- Memと他サービス(mimなど)の比較、選ぶ目安は?
memって何?(memの意味・英語スラング/IT用語の違い)
結論として、memは文脈で意味が変わりますが、本記事ではAIノートアプリの「Mem」を指します。
英語圏ではmemがmemoryに由来し、ITではメモリの略記、スラングではmemsが「思い出」を意味することがあります。
製品名のMemは自己組織化するAIノートで、Mem Chatが自分のノートをもとに事実照会や要約に応答します(参考: Chat in Mem – Mem Help & Support)。
また開発者向けには別製品としてMem0があり、LLMアプリに永続的な記憶を与えるメモリレイヤーとして提供されています(参考: Mem0 – The Memory Layer for your AI Apps)。
そのため検索で“What does mem mean?”のような一般用語に当たった場合でも、文脈で「用語」か「製品名」かを確認すれば迷いません。
Memと他サービス(mimなど)の比較、選ぶ目安は?
結論は、mimとmemは土俵が違うため比較対象にせず、用途で選ぶのが正解です。
MIMは経営学位など別分野の用語で、MemはAIノートアプリというプロダクトだからです。
ノートアプリ間で迷うなら「即時キャプチャの速さか、構造設計の自由度か、協業の深さか」という軸で判断します。
Memはフォルダ不要のキャプチャとAI検索や関連ノート提案に強みがあり、思考のフローを止めずに記録できます(参考: Notion vs Mem – Mem公式比較)。
一方でNotionはデータベースとテンプレートで高度に構造化でき、タスクやWikiで優位です(参考: Notion vs Mem – Mem公式比較/活用例: [2025年最新版] Notion AIの本当の使い方と活用例)。
実務コンサルの経験上、メモ取りが主で後からAIに再発見させたいならMem、最初に構造を設計してチーム運用を徹底したいならNotionやWiki型が向きます。
録音中心でキャプチャを自動整理したい人には、音声録音から文字起こしと要約まで自動化できるPLAUD NOTEの併用も実務では効果的です![]() 。
。
まとめと次の一歩
本稿はMem(AIノート)とMem0(開発者向け記憶レイヤー)を整理し、強み・課題・料金状況(Mem 2.0ベータは無料)を俯瞰しました。
要点は、AIで自己組織化と高速検索を実現するMem、継続的パーソナライズとコスト最適化を担うMem0、そして競合下での実装力が差を生むことです。
次にすべきは、「まず使い、型で回す」こと。小さく試し、成果で広げましょう。
プロンプトと運用の型を最短で学ぶなら生成AI 最速仕事術をどうぞ。
会議や取材を自動で文字起こし・要約するならPLAUD NOTEで記録を資産化しましょう。![]()
いま動けば、あなたの知識フローは今日から加速します。