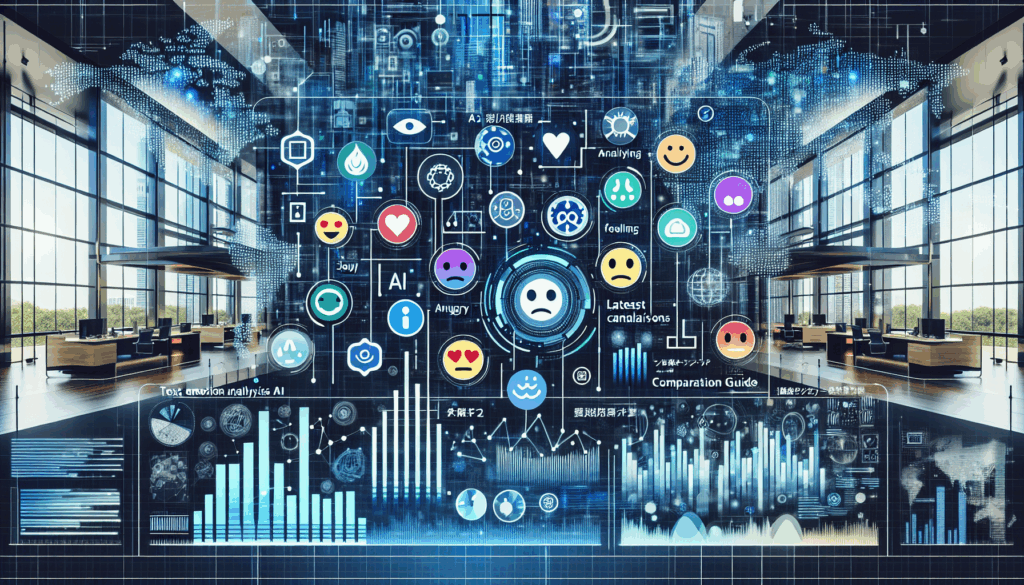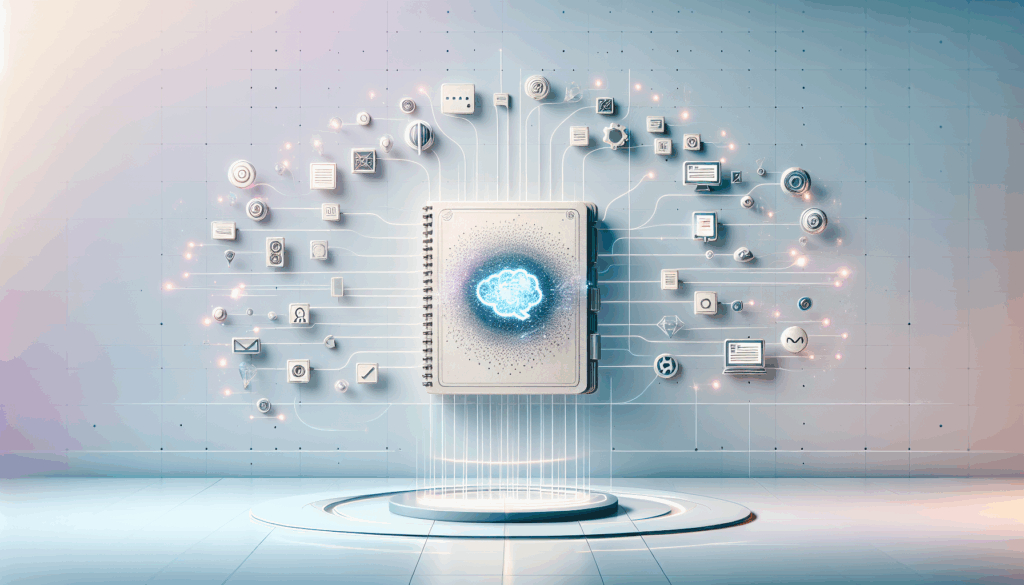(最終更新日: 2025年09月21日)
「『Lilli』って同じ名前が多すぎて、どれが自分に合うのか分からない…」そんな戸惑い、ありませんか?
本記事は、名前が似ている4つのLilli(lili/Lily)系AIを、目的別にやさしく整理します。
建設・大型プロジェクト向け、ECの売上改善、フリーランスの資金・経理、そしてマッキンゼー社内モデルまで、違いと使いどころをひと目で理解。
特徴・用途・料金・評判を最新情報で比較し、迷いや重複投資を避けるための判断軸が身につきます。
記事では図解と具体例で、選び方の手順や業種別のおすすめも一気に把握できます。
現場でAI活用を支援してきた編集チームが検証し、今日から動ける実践のコツまでお届けします。
Lilli(lili/Lily)が指す4つの主要AIツールと違いを整理
当セクションでは、「Lilli」「Lily」「Lili」という同名で語られる4つの主要AIプラットフォームの正体と違いを、用途別・業種別に整理します。
同名が乱立し、導入検討時に誤認や選定ミスが生じやすいため、最短で自社に合う候補へ到達する判断軸を提示します。
- 名前が紛らわしい理由と市場トレンド
- ざっくり早見表:どのLilliがあなたに合う?
名前が紛らわしい理由と市場トレンド
結論は、同じ「Lilli/Lily/Lili」でも中身は別物です。
選定の出発点は「業種×課題(守りか攻めか)」を見極めることです。
混乱の原因は、建設のLili.ai、小売のLily.ai、フィンテックのLili.co、社内専用のマッキンゼーLilliという、ターゲットも価値も異なる4者が同名で並立しているからです。
背景には、業界課題に最適化するバーティカルAIの台頭と、既存SaaSにAIを溶け込ませる組み込み型AIの普及があります。
例えばLili.aiは非構造化文書から遅延・コスト超過の兆候を検知する「防御的AI」で、Oracle Unifier連携など大企業のPMISと統合して力を発揮します。
一方でLily.aiは商品画像とテキストから2万以上の属性を自動付与し、検索や広告を底上げする「攻めのAI」として収益成長を狙います。
またLili.coは会計カテゴリ自動化とチャット会計をバンキングに組み込み、マッキンゼーのLilliは社内知を活かして調査・資料作成を加速させます。
下図のマトリクスを見ると、4者の目的と業種適合の違いが直感的に把握できます。
したがって、まず「守りか攻めか」「社外SaaSか社内ツールか」を定め、そのうえで業界適合と統合先で絞り込むのが最短距離です。
参考:
関連ガイドも参考にしてください:AIツールの選び方完全ガイド/建設業のAI活用事例/小売業のAI活用事例。
ざっくり早見表:どのLilliがあなたに合う?
結論として、最短で迷いなく選ぶには「目的(守りか攻めか)と業種」の二軸で当てはめるのが有効です。
同名でも導入形態や価格レンジ、期待ROIが異なるため、用途基準で切ると検討の手戻りを防げます。
次の早見表は、業種・課題ベースで4つのLilliを一目で見分けられるように整理しています。
| 名称 | 主要機能 | 主目的 | 業種適合 | 想定ユーザー | 導入/料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lili.ai | 非構造化文書のリスク検知 | 守り(遅延/超過の予防) | 建設・エンジ・インフラ | 契約/プロジェクト管理 | エンタープライズSaaS、要デモ |
| Lily.ai | 商品属性自動付与・検索/広告強化 | 攻め(CVR/売上向上) | 小売・EC・アパレル | EC/マーケ責任者 | エンタープライズSaaS、価格非公開 |
| Lili.co | 会計カテゴリ自動化・会計Q&A | 効率化(経理負担軽減) | フリー/小規模事業 | 個人事業主・SOHO | フリーミアム、バンキング一体 |
| マッキンゼーLilli | 社内知ベースの調査/下書き支援 | 生産性(社内専門知活用) | コンサル(社内専用) | マッキンゼー社員 | 非商用・社内限定 |
例えば、建設で遅延や紛争の予防が主眼ならLili.ai、小売で在庫の発見性とCVR向上を急ぐならLily.aiが起点になります。
目的×業種で選べば迷わないので、候補を絞ったらデモ依頼や無料プラン試用にすぐ移行しましょう(選定の進め方はAIツールの選び方完全ガイドが参考になります)。
出典:
Lili.ai|建設・エンジニアリング大規模案件特化型リスク管理AI
当セクションでは、建設・エンジニアリングの大規模案件に特化したリスク管理AI「Lili.ai」の実力、導入価値、機能・価格・評判を体系的に解説します。
なぜなら、数千〜数万件に及ぶ議事録やメールといった非構造化データに潜む遅延・コスト超過の予兆を見逃さないことが、巨額損失と訴訟を避ける最重要の打ち手になるからです。
- Lili.aiの強みとビジネス課題解決力
- 機能・価格・評判の詳細(プロジェクト志向のSaaSモデル)
Lili.aiの強みとビジネス課題解決力
Lili.aiの核心は「数ヶ月前のリスク予兆を可視化し、損失や訴訟を未然に防ぐ」防御型AIである点です。
その理由は、メールや議事録などの非構造化文書から意味を理解してリスクシグナルを抽出・追跡できる産業特化NLPを中核に据えているからです(参考: Lili.ai)。
実例として、3億ユーロ超の建設案件では、公式アラートの6ヶ月以上前から「#Delays」「#quality」「#IntermediateTestCancelled」の言及が急増し、事後分析で早期兆候の存在が裏付けられました(出典: Preventive use case – Lili.ai)。
さらに、Oracle Construction and EngineeringのサミットでNLPイノベーションパートナーとして紹介され、Oracle Unifierとの統合を進めるなど、運用現場の基幹システムに接続されている点も信頼性の証左です(参考: Press & news – Lili.ai)。
請求補強や差異分析レポートで必要な「文書化された証拠」の探索を高速化し、責任所在の立証を支援できるため、結果として高額な紛争・訴訟の回避に結びつきます(参考: Use Cases – Lili.ai、参考: 5 Q’s for Milie Taing – Center for Data Innovation)。
よって、議事録・メールといった「ダークデータ」を能動的なリスク管理資産へ転換し、ハイリスク案件の“保険”として投資価値が高いソリューションと言えます。
参考資料:
- Preventive use case – Lili.ai
- Use Cases – Lili.ai
- Press & news – Lili.ai
- 5 Q’s for Milie Taing – Center for Data Innovation
関連記事もあわせてご覧ください: 【最新2025年版】建設業界におけるAI活用事例大全 / AI議事録作成ツール徹底比較
機能・価格・評判の詳細(プロジェクト志向のSaaSモデル)
Lili.aiは「抽出(Extract)→検索(Search)→再利用(Reuse)」の三段構えで非構造化データを知見化するエンタープライズSaaSで、価格は非公開・要デモです。
大規模B2Bの性格上、案件規模や既存システムとの統合要件で導入設計が変わるため、個別見積りが前提になります(参考: Lili.ai)。
ExtractでPDFやメールなどを取り込み、Searchでプロジェクト語彙に最適化されたセマンティック検索を行い、Reuseで類似事象の再発時に早期警告を促す設計です(参考: Use Cases – Lili.ai)。
外部評価として、IBM Watson AI XPRIZEのファイナリスト選出や欧州イノベーションカウンシルによる助成金獲得、Oracle Unifierとの統合実績などが挙げられます(参考: Press & news – Lili.ai)。
一方で、中小規模・短工期の案件ではオーバースペックになり得るため、プロジェクト特性に合わせた費用対効果評価が不可欠です。
| 導入前の課題 | 導入後の成果 | ソース |
|---|---|---|
| 予兆の見落としにより遅延が顕在化 | 公式アラートの6ヶ月以上前から兆候検出が可能に | Preventive use case – Lili.ai |
| 請求・差異分析の証拠集めに時間がかかる | 文書横断の証拠検索が高速化し、請求書類の一貫性が向上 | Use Cases – Lili.ai |
| ツールがサイロ化し運用負荷が高い | Oracle Unifier連携などで既存PMISと統合し運用摩擦を低減 | Press & news – Lili.ai |
価格は公式に明記されておらず、まずはデモリクエストを通じた要件定義が必要です(参考: Lili.ai)。
関連記事: 導入判断の前に AIプロジェクト管理ツール完全比較 で評価軸を確認すると効果的です。
Lily.ai|Eコマース向け生成AI・顧客体験最適化プラットフォーム
当セクションでは、Lily.aiの仕組みと導入適性を整理し、ECの収益に直結する使いどころを解説します。
なぜなら、同名ツールの混同が起きやすい一方で、Lily.aiは小売特化で「発見性→CVR→収益」を底上げするバーティカルAIの代表格だからです。
- Lily.aiが変える『探しやすさ』と売上成長のロジック
- 導入形態・料金・適合企業とその選びどころ
Lily.aiが変える『探しやすさ』と売上成長のロジック
商品データを“顧客語”に翻訳し、発見性と売上を同時に底上げするのがLily.aiの本質です。
画像と説明文から2万以上の属性を自動生成し、色や素材だけでなくフィット感や雰囲気、利用シーンまでタグ化できるからです(参考: Ecommerce – Lily AI)。
例えば「夏の結婚式に着ていく揺れるミディ丈」と検索されたとき、style、occasion、fit、moodなどの属性に分解して高精度に一致させます。
この高密度属性はサイト内検索、レコメンド、さらに広告入札の一致精度を同時に引き上げます。

実績として、最大8%のEC収益増や最大10%のCVR増、Google広告で5〜22%の売上向上が提示されています(出典: Ecommerce – Lily AI)(参考: Futurepedia – Lily AI)。
ユーザー評価もG2で5点満点中4.9と高く、タグ付けの容易さや時間削減効果が支持されています(参考: Lily AI Reviews & Product Details – G2)。
だからこそ、検索・推薦・広告の三位一体でレバーを効かせ、短期の売上改善と中期のLTV向上を両立できます(関連記事: 【2025年最新】小売業のAI活用事例と導入のコツ)。
導入形態・料金・適合企業とその選びどころ
Lily.aiは基本的に大手小売向けのカスタムSaaSであり、選定の第一条件は「規模」と「商品点数の多さ」です。
価格は非公開で無料トライアルもなく、ハイタッチな導入前提のエンタープライズ型で提供されます(参考: Lily AI Pricing 2025 – TrustRadius)。
導入実績にはMacy’s、J.Crew、Abercrombie & Fitch、Tory Burchなどの名が並び、グローバル大手の基準を満たす実装力がうかがえます(出典: Ecommerce – Lily AI)。
SKUが多いほど属性付与のROIは逓増しやすく、商品点数が多いECや大規模カタログを持つ小売に特に向きます。

一方で中小や個人のショップでは初期設計や費用面のハードルが高く、まずは段階的にAIマーケティングや検索最適化の別解を検討すると良いです(参考記事: AIマーケティングツールのカオスマップ完全ガイド)。
結論として、十分な商品数とデータ量があり組織的に運用できるならLily.aiを本命として評価し、要件整理とPoCを進めつつ社内のAIスキル強化にはDMM 生成AI CAMPのような実践学習も併用すると効果的です。
Lili.co|フリーランス・小規模事業向けバンキング&会計AI
当セクションでは、フリーランスや小規模事業者向けのビジネスバンキング「Lili.co」と、その中に組み込まれた会計支援AIの実力を解説します。
同名のAIが複数存在して混乱しやすいなかで、Lili.coは「バンキングにAIが埋め込まれている」点が特徴で、日常の入出金と記帳をひとつに束ねて工数を削減できるからです。
- “一人経営”でも使える!簡単自動化バンキングの実力
- Lili.coでできること・コスト・評判
“一人経営”でも使える!簡単自動化バンキングの実力
結論として、Lili.coは口座管理と会計の間をAIでつなぎ、ひとり仕事でも「毎月締め」を回せる実務レベルの自動化を提供します。
理由は、取引の自動カテゴリ推奨とチャット型のAccountant AIが標準搭載され、仕訳の手間と会計の疑問をアプリ内で完結できるからです。
具体例として、私が請求書発行後の経費整理で使った際は、カード明細が自動で取り込まれ、AIの提案カテゴリを確認して数件だけ微修正するだけで日次の記帳が終わりました。
締め日前の「これ何費?」という迷いも、チャットに用途を打ち込むと勘定案と注意点が数秒で返ってきて、確認作業が5分で済みました。
要するに、アプリを開いて確認・微修正するだけで、面倒な記帳が“横目”で終わる体験が実現します。
Lili AIの予測的カテゴリ分類とAccountant AIは公式が明示しており、同社は税務・法務の助言主体ではなく補助ツールとして位置づけています(参考: Lili AI – Powering Your Business Growth)。
Lili.coでできること・コスト・評判
結論として、Lili.coは「口座開設→取引自動取り込み→AI仕訳→チャットで会計Q&A→レポート」の一連を低コストで始められ、評判面でも安心感があります。
理由は、AIによる自動仕分けとチャット会計に加え、本人確認の機械学習活用など運用面の自動化が進んでおり、Basicプランは無料で導入障壁が低いからです。
さらに、Trustpilotで4.7の高評価と20万人超の利用実績が公表されており、スタートアップから副業まで幅広い層で定着しています。
以下に主要ポイントを簡易に整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| できること |
|
| コスト |
|
| 評判 |
|
まず無料で導入し、必要に応じて有料で拡張する段階導入が取りやすく、スモールビジネスの現実解になっています。
経理AIの全体像や他社比較は、導入の前提知識として【2025年最新】経理AI完全ガイドも参考になります。
- 出典: Lili – Business banking for SMBs & Startups
- 出典: Lili AI – Powering Your Business Growth
- 出典: Socure Case Study: Lili Experienced 1700%+ Customer Growth
マッキンゼーの「Lilli」~社内活用モデル&独自データ戦略~
当セクションでは、マッキンゼーの社内生成AI「Lilli」の活用モデルと独自データ戦略、そして名称が似た他社事例との混同を避けるための前提知識を解説します。
なぜなら、Lilliは外部LLMと社内ナレッジを統合する“プロフェッショナル用途の最前線”であり、導入担当者の意思決定に大きな示唆を与える一方で、発音が近い企業名が誤解を生みやすいからです。
- プロフェッショナル用途でのAI活用最前線
- よくある混同事例と前提知識の整理
プロフェッショナル用途でのAI活用最前線
結論は「独自データ資産×マルチLLM」で、ベンダーロックインを避けつつ知見の再利用を最大化することが要諦です。
下図はその骨子です。
背景として、LLMは急速にコモディティ化が進み、差別化の源泉がモデル選定ではなく自社が保有するプロプライエタリデータと運用設計に移っているからです。
具体例として、マッキンゼーのLilliはCohereやOpenAI(Azure経由)など外部LLMを使いつつ、同社が数十年蓄積したプロジェクト資料や専門家知見を安全に検索・要約・草稿化する“社内専用アシスタント”であり、特定の基盤LLMに固定しない方針を明言しています(出典: Yahoo奇摩股市)。
運用面では、RAGで社内ナレッジを呼び出し、生成は常に最新・最適なLLMに切り替えられる構成が効果的です(実装の考え方はRAG構築のベストプラクティスが参考になります)。
併せて、社内境界内でのガバナンス、監査ログ、機密ラベル管理などのセキュリティ設計を前提に据えると、現場での安心感が高まります(実務の留意点は生成AIのセキュリティ完全解説を参照してください)。
最終的に、自社でも「独自ナレッジの接続」「マルチLLMでの最適実行」「利用ログと品質監視」の三点を整えれば、Lilli型の生産性向上を再現しやすくなります。
社内の実務者スキルを短期で底上げしたい場合は、オンライン講座の活用も効果的です。
DMM 生成AI CAMPなら、プロンプト設計から業務応用まで体系的に学べ、導入効果を早期に引き出しやすくなります。
よくある混同事例と前提知識の整理
結論として、「マッキンゼーのLilli」と「イーライリリー(Eli Lilly)」は全く別物であり、役割や目的を混同しないことが重要です。
両者は名称が似てAI関連の話題に並ぶため、購買やリスク審査の現場で誤解が起きやすいからです。
前者は社内コンサルタント向けの生成AIアシスタントで、外部LLMと社内知見を組み合わせてリサーチや資料作成を加速する“非商用の社内ツール”です。
後者は世界的製薬企業で、創薬や臨床のR&DにAIを投資・活用しつつ、データプライバシーやベンダー審査を厳格に運用する“産業用途のAIユーザー”です(参考: Purdue Daniels Insights)。
混同を防ぐには「正式名称」「AIの位置づけ」「データ戦略」「導入対象」をチェックリスト化して確認するのが有効です。
特に医療・製薬領域は規制や倫理配慮が不可欠であり、事例理解には医療AI事例大全やAI倫理ガイドラインの整理も役立ちます。
| 項目 | マッキンゼーの「Lilli」 | イーライリリー(Eli Lilly and Company) |
|---|---|---|
| 何者か | コンサル向け社内生成AIアシスタント | 世界的製薬企業(AIはR&D等の手段) |
| AIの位置づけ | 社内知見の検索・要約・草稿化支援 | 創薬・臨床最適化・データ統合の推進基盤 |
| データ戦略 | 独自ナレッジ活用とベンダー非依存 | 機密研究データ保護と厳格な外部審査 |
| 導入対象 | 同社コンサルタント(非商用) | 自社R&D・オペレーション(産業用途) |
| ロックイン方針 | マルチLLMで回避 | サプライヤー審査で統制 |
『Lilli』系AIツールを選ぶ際によくある疑問・Q&A
当セクションでは、「Lilli」系AIツールの名称の正体、似た綴りの違い、国内での利用可否、そして実際の成果をQ&A形式で整理します。
同名・類似名が複数存在しやすく、検討段階での誤認や社内説明の混乱が起きやすいため、意思決定に必要な最小限の確認ポイントを明確にします。
- Lilliとは何か?(名称の意味・発音・使われ方)
- LiliとLilly(またはLilli、Lily)の違いは?
- Lilliは日本国内でも使える?
- Lilliを使った場合の実際の成果例は?
Lilliとは何か?(名称の意味・発音・使われ方)
「Lilli/Lily/Lili」は一般名詞ではなく、主にブランド名や社内イニシアチブ名として使われる固有名で、発音はおおむね「リリィ」です。
命名は花の「Lily(百合)」や創業者名・ブランド語源などに由来することが多く、技術用語としての独立した意味は持ちません。
AIツール領域では、建設・エンジニアリングのリスク管理に特化したLili.aiなど、産業特化型(バーティカル型)のプロダクト名として用いられています(参考: Lili.ai)。
小売・Eコマースの属性生成に特化するLily.aiのように、消費者言語と商品データのギャップ解消を目的としたブランド名にも使われています(参考: Lily.ai Ecommerce)。
一方で米国のビジネスバンキング「Lili.co」では会計支援AIが組み込み機能として提供されるなど、分野や機能は大きく異なります(参考: Lili.co)。
このため、「Lilli」という語を見かけたらまず対象のサービス名と用途を特定し、必要に応じて一次情報を確認してください(参考: McKinseyの社内AI「Lilli」報道)。
LiliとLilly(またはLilli、Lily)の違いは?
スペルの違いは“表記揺れ”ではなく、そもそも別の企業・製品を指すことが多いため、公式サイトでターゲット業種と機能を必ず確認します。
各サービスは対応業務・導入対象・ビジネスモデルが異なるため、混同すると要件に合わないツールを選定するリスクが高まります。
たとえば「Lili.ai」は建設・エンジニアリングの非構造化文書から遅延やコスト超過の兆候を検知するリスク管理AIです(参考: Lili.ai)。
「Lily.ai」は商品画像とテキストから詳細属性を自動付与し、検索・レコメンド・広告の精度を高めるリテールインテリジェンスです(参考: Lily.ai Ecommerce)。
「Lili.co」は米国中心のビジネスバンキングで、取引の自動分類や会計Q&Aなど“埋め込みAI”を提供する別カテゴリのサービスです(参考: Lili.co)。
検討時は用途・対象・導入形態の3点を短時間で照合し、本記事後半の「公式リンク集」も併用して混同を避けてください(参考: AIツールの選び方完全ガイド)。
Lilliは日本国内でも使える?
結論として、多くは日本から利用・導入相談が可能ですが、製品ごとに前提条件が異なるため事前確認が必要です。
対象が海外SaaSや社内ツールであること、データ所在地や契約形態などのコンプライアンス要件が絡むことが理由です。
Lili.aiやLily.aiはエンタープライズ向けの問い合わせ・デモリクエストを受け付けており、日本企業からの導入相談も想定できます(参考: Lili.ai、Lily.ai Ecommerce)。
ただしLili.coは米国向けバンキングであり、日本の金融ライセンス枠組みとは異なるため、そのままの利用は想定されていません(参考: Lili.co)。
マッキンゼーの「Lilli」は社内用で商用提供はなく、日本法人経由での活用はマッキンゼーのプロジェクト支援を通じて個別相談が必要です(参考: McKinsey Lilli報道)。
初回は非公開情報を含まない範囲で要件整理から始め、法務・情報セキュリティと連携して評価を進めるとスムーズです(参考: 中小企業のAI導入ガイド)。
Lilliを使った場合の実際の成果例は?
各「Lilli」は業種ごとのKPIに直結する成果が確認されており、失敗回避や売上・工数の改善など定量ROIで評価できます。
理由は、バーティカル特化や組み込み型という設計思想により、成果指標がリスク損失回避・収益向上・会計時間削減など明確に定義されているためです。
Lili.aiでは、文書群から遅延や品質問題の兆候を早期検知し、請求や係争のエビデンス探索を高速化する事例が公表されています(参考: Lili.ai Preventive use case)。
Lily.aiは、コンバージョン最大10%増やEコマース収益最大8%増、広告単体で5〜22%の売上向上などの数値を提示しています(参考: Lily.ai Ecommerce)。
Lili.coは取引の自動分類や会計Q&Aにより、記帳ミスや工数の削減といった日常業務の効率化に寄与します(参考: Lili AI – Powering Your Business Growth)。
検討時は公式のケーススタディや第三者レビューで裏取りし、自社KPIに当てはめた事業計画を作ると精度が上がります(参考: 小売業のAI活用事例、建設業のAI活用事例)。
体系的に評価軸を学びたい場合は、短期集中で実務活用スキルを学べるオンライン講座も有効です(参考: DMM 生成AI CAMP)。
AIツール選定のプロが教える『Lilli』活用最適化のTips
当セクションでは、名称が紛らわしい複数の「Lilli」を正しく見極め、ビジネス価値を最大化する活用最適化の考え方と具体策を解説します。
なぜなら、同名でも技術と対象業界、ROIの出方がまったく異なり、選定を誤ると費用対効果が出ないどころか現場の混乱を招くからです。
- 最初に定義すべきは『何を解決したいか』
- 導入時の失敗パターンと対処法
- 権威性・信頼性を見極めるために――外部評価と公式データ活用
最初に定義すべきは『何を解決したいか』
最初に決めるべきは「守り(リスク防止)」か「攻め(売上成長)」かを言語化し、業種特有の課題に合うかを要件化することです。
同名のLilliは、Lili.ai(建設・エンジニアリングのリスク管理)とLily.ai(小売ECの収益成長)、Lili.co(スモールビジネスの会計効率化)、マッキンゼーの社内用Lilliで目的が異なります。
私はプロダクトマネージャーとして建設子会社の業務設計を再設計した際、「遅延兆候の早期検知」をKGIに置き、非構造化文書が多い実態を踏まえて要件を定義し、結果的にLili.aiを評価対象に絞り込みました(出典: Lili.ai)。
一方で、アパレルEC事業では「商品発見性とCVRの改善」を主目的に据え、商品属性付与で検索と広告を底上げできるLily.aiを候補に設定しました(参考: Lily.ai Ecommerce)。
この「課題→要件→ツール」の順番を守ると、比較は短時間で深く進み、予算・人員・導入ハードルもブレずに可視化できます(関連記事: AIツールの選び方完全ガイド)。
下図の意思決定マップを使うと、どの「Lilli」を検討すべきかを一目で整理できます。
- 参考: Lili.ai
- 参考: Lily.ai Ecommerce
- 参考: Lili.co
- 参考: マッキンゼーの社内用Lilli
導入時の失敗パターンと対処法
“AIを入れるだけ”では成果にならず、連携・データ・ユースケース設計が成否を左右します。
理由は、既存システムとつながらない、現場のデータが整っていない、初期の適用範囲が広すぎると、検証が遅れROIが霧散するからです。
私が率いた業務自動化プロジェクトでは、勤怠とERPのAPI制限を見落としデータ欠損が発生し、全社展開の前に「特定部署の請求補強レポート作成」にスコープを絞り、スキーマ確定とETLの監視で立て直しました。
対処法は、連携要否の棚卸し、現場の原データの欠損・表記ゆれ検査、成功確率の高い小さなユースケースから始めることです(例: Lili.aiは要デモで適合可否を早期に確認、Lily.aiは価格非公開のため導入ROI仮説を先に置く)(参考: Lili.ai、Lily AI Pricing情報)。
検証前に無料トライアルや事前相談、PoC計画で疑問を洗い出し、ログ取得とKPI定義を並走させると、改善ループが回ります(関連記事: AI自動化ツール徹底比較)。
権威性・信頼性を見極めるために――外部評価と公式データ活用
判断材料は公式データと第三者評価の両輪で検証し、出典を必ず確認することが基本です。
なぜなら、ROI主張や料金情報は二次サイトで誤って伝播しやすく、意思決定にバイアスをかけるからです。
たとえばLily.aiは「最大8%のEC売上増や最大10%のCVR増」を公式に掲示し、G2でも高評価ですが、価格は非公開で非公式のディール情報は鵜呑みにすべきではありません(出典: Lily.ai Ecommerce、参考: G2、注意喚起: Oncelyの割引情報)。
Lili.aiはOracle Unifierとの統合や複数の表彰実績が信頼の裏付けとなるため、社内の要件に対する適合性と合わせて一次情報で確認します(出典: Lili.ai)。
Lili.coはTrustpilot高評価やユーザー規模が参考になる一方で、AIは組み込み機能であり金融プラットフォームとしての価値が主である点を理解して比較します(参考: Lili.co)。
- 出典・参考一覧: G2 / Lily.ai Ecommerce / Lili.ai / Lili.co / Oncely
選定力の土台を強化したい場合は、体系的に学べる実務コースを活用すると効果的です(参考: DMM 生成AI CAMP、関連記事: AI市場調査の最前線)。
まとめと次の一歩
同名の4つのLilliを整理し、目的別の選定軸(防御=リスク、攻撃=成長、組み込み=効率、社内=独自データ)を明確化しました。
鍵はバーティカル化・エンベデッド化、そして自社データの活用です。
問題定義からエコシステム選定までを一気通貫で設計することが成功の近道です。
まず一歩、小さく試し、成果で次に進みましょう。
あなたの現場が動けば、戦略は磨かれます。
実装を加速したい方は、「プロンプトの型」と「最前線の活用事例」で武装しましょう。
生成AI 最速仕事術 と 生成AI活用の最前線で、今日の学びを明日の成果に変えましょう。