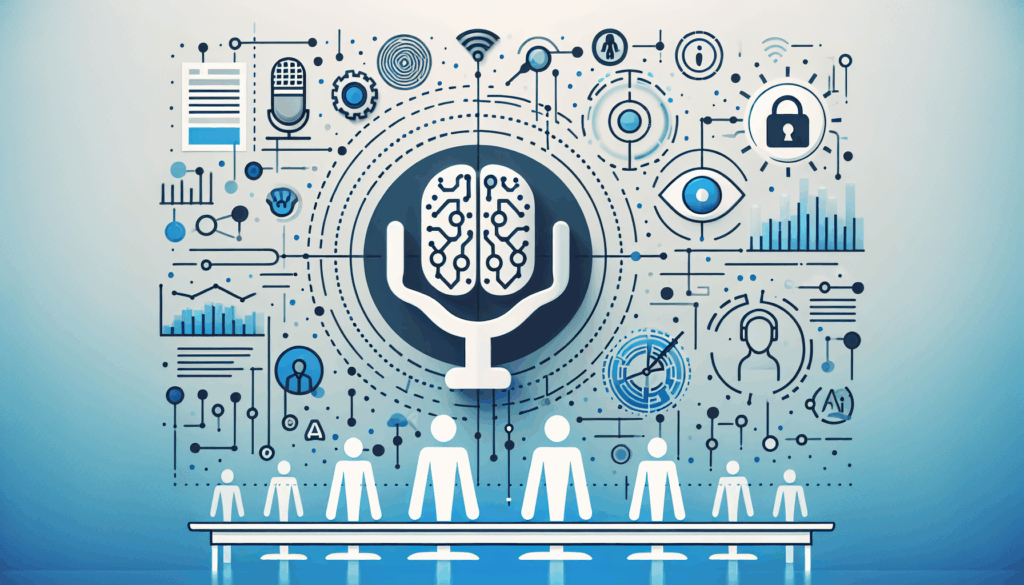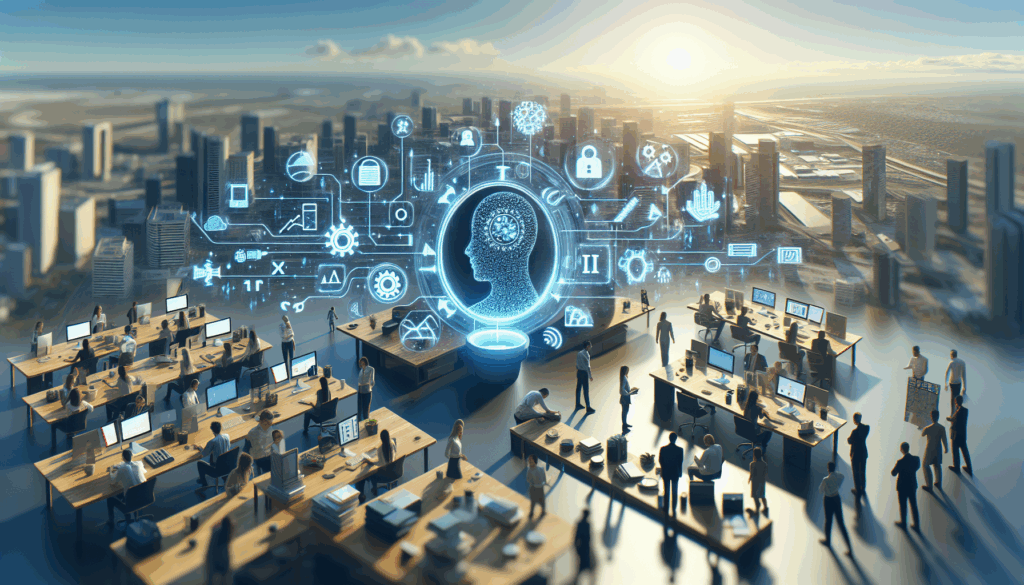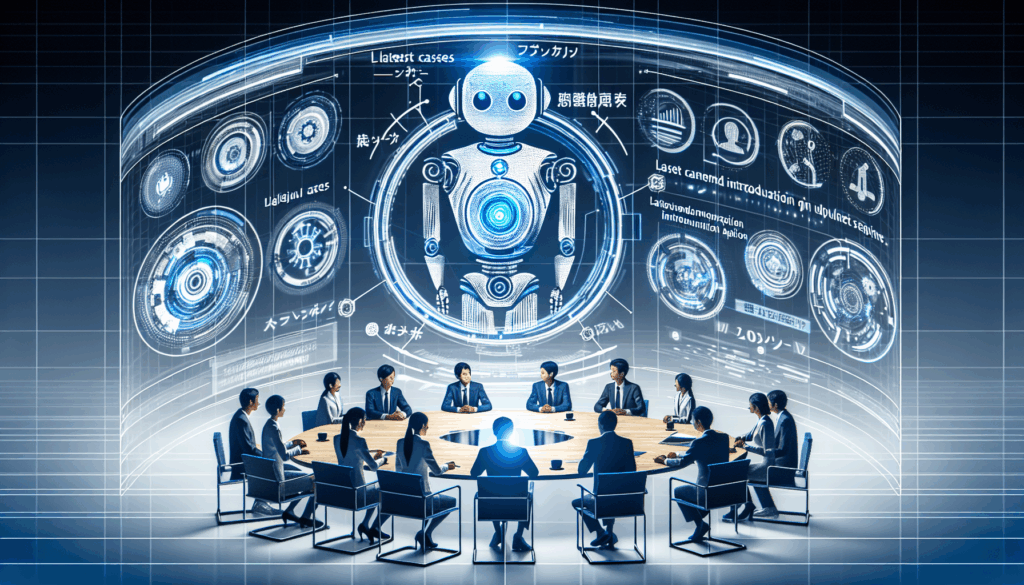(最終更新日: 2025年10月11日)
議事録づくりに時間を取られ、本来の仕事に集中できないと感じていませんか?
AI議事録ツールが増えるなかで、AI GIJIROKUは何が違い、あなたの業務に本当に合うのかをはっきりさせます。
この記事では、使い方の流れ、実務での効果、料金の見方、精度や要約力、セキュリティまで要点をやさしく解説します。
他の人気ツールとの比較や、実ユーザーの声も交えて、最適な選び方が一目でわかるように整理しました。
AI活用支援の現場で培った知見をもとに、迷いどころと判断基準を具体的にお伝えします。
読み終える頃には、自社やチームに合うベストな議事録ツールと、すぐ始めるための一歩が見えているはずです。
AI GIJIROKUとは?特徴と開発背景からわかる、他との違い
当セクションでは、AI GIJIROKUの本質と主要機能、そして開発背景から導かれる他サービスとの違いを整理して解説します。
なぜなら、単機能の文字起こしに見えるツールでも、設計思想やデータ活用の前提が企業の生産性やセキュリティ適合性を大きく左右するからです。
- AI GIJIROKUの概要とオルツのビジョン
- AI GIJIROKUが選ばれる3つの理由
AI GIJIROKUの概要とオルツのビジョン
AI GIJIROKUは、オルツが開発するエンタープライズ向けAI議事録サービスで、単なる文字起こしを超えた“データインテリジェンス基盤”として設計されています。
同社のP.A.I.構想は個人の記憶や対話をデジタル化して拡張するもので、その実現には会議という高密度な言語データの正確な収集と構造化が不可欠です(参考: オルツ公式サイト)。

AI GIJIROKUは声紋登録やカスタム辞書、SNSやメール連携を通じて一人ひとりの語彙や話し方を学習し、使うほど精度が高まり知的資産化が進みます(参考: Google・X・Salesforce・Outlook連携の公式FAQ)。
要約には独自LLM「LHTM-2」を用い、ビジネスで重視される事実性を担保した要約で次のアクションに直結する情報へ変換します(出典: LHTM-2を活用したAI要約機能の発表)。
オルツは東証グロース上場企業で資金調達も進み、AI GIJIROKUは導入社数8,000社超という実績を公表しています(出典: 共同通信PRワイヤー)。
会議ログを検索可能なナレッジに変えたい企業やP.A.I.のような個人知の拡張に関心がある組織にとって、AI GIJIROKUは最有力の選択肢と言えるでしょう(参考: 【比較2025年最新版】AI議事録作成ツール徹底比較)。
- 参考: AI GIJIROKU 製品ページ
- 参考: LHTM-2 解説インタビュー
AI GIJIROKUが選ばれる3つの理由
AI GIJIROKUが選ばれる理由は、99.8%の音声認識と99.62%の話者識別、事実性重視の独自LLM要約、ISO 27001に裏打ちされたセキュリティという三位一体の強みにあります(出典: 話者識別精度 99.62% 公表)。
これらはエンタープライズ前提の設計思想で、運用の厳格さと継続学習の両立を図り、使い込むほど価値が増すのが特徴です。

精度面では、利用時の修正や辞書登録をフィードバックする仕組みにより音声認識が継続的に向上するよう設計されています(参考: 認識精度が高い理由)。
話者識別は声紋登録により99.62%の精度が公表され、誰が何を言ったかを自動で紐づけます(出典: オルツ発表)。
ハイブリッド会議では、複数デバイスの音声を一つの会話に統合する特許技術がエコーや重複を抑え、記録の忠実度を高めます(出典: 複数音声統合の特許取得)。
要約は独自LLM『LHTM-2』がハルシネーションを抑制し、事実に敏感な要約を生成します(参考: AI要約機能発表)。
セキュリティはISO 27001準拠のISMSを取得しており、機密性を重視する企業の導入要件を満たします(出典: オルツ公式サイト)。
AI GIJIROKUの具体的な使い方と業務での効果
当セクションでは、AI GIJIROKUの実務で使える具体的な操作フローと、精度を引き出すコツ、向いている業務領域を解説します。
なぜなら、導入効果の大半は初期設定と運用設計で決まりやすく、ここを外さないことで以後の修正工数とコストが大幅に減るからです。
- 利用フロー:初期設定から実際の議事録作成まで
- 精度を最大限に活かすコツ
- どんな業務や企業規模に最適か?
利用フロー:初期設定から実際の議事録作成まで
結論は「最初に10分〜30分の初期設定へ投資すると、その後の文字起こし・要約・共有までが別物の速さになる」ことです。
理由は、声紋登録や辞書カスタマイズ、Google/X/Outlook/Salesforceなどの連携で個人と組織の語彙を学習させ、さらに独自LLM LHTM-2の要約で意思決定に必要な情報に圧縮できるからです(参考: AI GIJIROKU 公式サイト)。
実務フローは「アカウント作成→声紋登録・各種連携→会議を録音/音声ファイルをアップロード→自動文字起こし→AI要約・ToDo抽出→.docx/.csv出力やリンク共有」という一本道で進めます。

Web会議はZoom/Microsoft Teams/Google Meetと連携でき、営業ならSalesforceへ要約やToDoを自動で紐付けられます(参考: 連携に関する公式FAQ)。
手元の資産は.wav/.mp3/.m4a/.oggや.mp4から取り込み、完成後は.docxや.csvでエクスポートできるため、既存ワークフローにも載せやすいです(参考: 収録方法について、出力形式について)。
初期設定はやや手間ですが見返りは大きく、対面収音では通話も対面も録れるPLAUD NOTEの併用で音声品質を底上げしつつ、ツール選定は比較記事が役立ちます(参考: AI議事録作成ツール徹底比較)。
精度を最大限に活かすコツ
結論は「ユーザーごとのパーソナライズ設定が精度を左右する」ので、声紋・辞書・過去議事録学習・業界特化エンジンをフル活用することです。
理由は、固有名詞や社内略語の誤認を事前に潰すほど後工程の修正が減り、特化エンジンは専門用語の認識を5〜20%底上げするからです(出典: オルツ「飲食業GIJIROKU」発表)。
実務では辞書に製品名・取引先・化学物質名などを登録し、会議後の修正はそのまま学習フィードバックとして活かす運用が有効です(参考: 認識精度が高い理由)。

たとえば化学メーカーの会議では、導入初期に辞書整備と過去議事録の取り込みを徹底した結果、以降の打ち合わせで修正量が目に見えて減りました(参考: 導入事例一覧(デジタル化の窓口))。
誰が何を話したかは声紋による話者識別で自動付与されるため、「発言 attribution」に費やす時間も削減できます(出典: 話者識別精度99.62%の発表)。
最小限の手直しでも毎回の修正が次回精度に蓄積されるため、結果的に「使うほど賢くなる」循環が生まれます(参考: AI文字起こしツール徹底比較)。
どんな業務や企業規模に最適か?
結論は「専門用語が多い業界、大人数・ハイブリッド会議、正確さとセキュリティを重視する大企業・官公庁」に最適です。
理由は、業界特化エンジンとISO 27001で裏打ちされた体制、多言語対応、複数デバイス音声統合の特許技術により、厳しい要件下でも高い再現性を出せるからです(参考: オルツ公式、AI GIJIROKU 公式サイト、複数音声統合の特許、ISO/ISMS関連の方針)。
行政では福島県磐梯町が導入し、会議録作成の負担軽減とオンライン審議会の基盤づくりを進めています(出典: LHTM-2搭載と要約機能の発表)。
製造業では日清紡ケミカルがスマホ録音からテキスト化・共同編集に切り替え、議事録作成プロセスを効率化しました(参考: 導入事例一覧(デジタル化の窓口))。
金融・法律・建設のように専門用語が頻発する現場でも、特化エンジンや「建築GIJIROKU」などの垂直展開で初日から高精度が見込めます(参考: 建築GIJIROKU 解説、飲食業GIJIROKU 発表)。

会議データは検索可能な知として蓄積されるため、配布前の最終チェックには文章の表記ゆれや誤変換を検知できるShodoのような校正ツールを併用すると、品質と配信スピードの両立がしやすくなります(参考: AIによる業務効率化の成功事例まとめ)。
AI GIJIROKUの料金プランとコストパフォーマンスの考え方
当セクションでは、AI GIJIROKUの料金プランの全体像と、費用に対して何に価値を見出すべきかを解説します。
なぜなら、無料や安価な文字起こしツールが増える一方で、業務品質・セキュリティ・要約精度まで含めた投資判断が難しくなっているからです。
- AI GIJIROKUの料金は?どこまで試せる?
- コスト以上の価値を生み出すポイント
AI GIJIROKUの料金は?どこまで試せる?
結論として、AI GIJIROKUは月額1,500円(税込想定)からのスタンダードを中心に、法人向け・カスタムで拡張でき、無料中心の競合より“業務品質を担保する設計”で選ばれます(参考: AI GIJIROKU 公式サイト)。
その理由は、高精度の音声認識や話者識別、独自LLMによる事実性重視の要約、ISO 27001に裏打ちされたセキュリティなど、エンタープライズ要件に対応しているためです(参考: 話者識別精度に関する発表)(参考: LHTM-2搭載のAI要約)(参考: オルツ公式(ISO 27001取得))。
以下の比較表は、代表的な競合の位置づけとあわせて、プラン選定の目安を整理したものです。
| サービス | 最安月額目安 | 主な強み | セキュリティ/運用 |
|---|---|---|---|
| AI GIJIROKU | 1,500円〜 | パーソナライズ、特許の複数音声統合、事実性重視のAI要約 | ISO 27001、企業利用実績多数 |
| Notta | 無料〜 | フリーミアム、多言語対応、直感的UI | 一般的なクラウド運用(参考情報中心) |
| Rimo Voice | 1,500円〜(個人向け) | 洗練UX、Bot自動参加、ChatGPT連携 | ISO 27017(クラウドセキュリティ) |
| AmiVoice ScribeAssist | 要問い合わせ | オフライン動作で高セキュリティ | スタンドアローン運用可 |
トライアルや招待コードは提供状況が変わるため、最新情報は公式サイトの申込フォームやパートナー経由のキャンペーン告知で確認してください(参考: オルツ パートナー制度)。
まずはスタンダードで評価し、Teams/Zoom連携や辞書登録の効果を見極めつつ、必要に応じて法人プランへ拡張する進め方が現実的です(比較検討には AI議事録作成ツール徹底比較 も参考になります)。
- 参考: AI GIJIROKU 公式サイト
- 参考: AI要約(LHTM-2)に関する発表
- 参考: 話者識別精度 99.62% に関する発表
- 参考: オルツ公式(ISO 27001)
- 参考: Rimo Voice 価格プレスリリース
コスト以上の価値を生み出すポイント
結論として、AI GIJIROKUは議事録作成の時間短縮と修正工数の削減により、人件費換算で導入費用を上回る価値を生みやすいです。
理由は、高精度の文字起こし・話者識別・要約が聞き直しや文書整形の負荷を下げ、ISO 27001準拠の体制が社内審査やベンダーレビューの手戻りを抑えるからです(参考: AI GIJIROKU 公式サイト)(参考: 話者識別精度に関する発表)(参考: オルツ公式(ISO 27001))。
例えば、月2回の定例会議で1本あたり議事録整備に3時間かかっていたチームが、AI GIJIROKU活用で1.5時間に短縮できると、1人あたり月3時間、年36時間の削減になります。

| 前提 | 値 |
|---|---|
| 削減時間(1人) | 月3時間 × 12カ月 = 年36時間 |
| 人件費(例) | 時給3,000円 |
| 年間削減額(1人) | 36時間 × 3,000円 = 108,000円 |
| チーム5名の場合 | 108,000円 × 5 = 540,000円/年 |
収音品質は精度とROIに直結するため、会議録音には高性能レコーダーの活用も有効です(例: PLAUD NOTE![]() )。
)。
また、業界特化エンジンや辞書登録を使うと専門用語の誤りが減り、外注校正や二重チェックのコストも縮小します(参考: 飲食業GIJIROKU)(参考: 建築GIJIROKU)。
結果として、時間と外部コストの両面で“人件費換算で簡単にペイする”ケースが多く、価格以上の価値を得やすいです(より広い比較は AI文字起こしツール徹底比較 を参照)。
- 参考: AI GIJIROKU 公式サイト
- 参考: 話者識別精度 99.62% に関する発表
- 参考: LHTM-2搭載のAI要約
- 参考: オルツ公式(ISO 27001)
- 参考: 飲食業GIJIROKU(業界特化)
- 参考: 建築GIJIROKU(業界特化)
AI GIJIROKUの精度・要約力・セキュリティを徹底検証
当セクションでは、AI GIJIROKUの音声認識精度・話者識別とAI要約の実力、さらにエンタープライズ導入に不可欠なセキュリティ・プライバシー体制を検証します。
精度と安全性は議事録ツール選定の要であり、公式情報と実地検証、他社比較を交えて実務での信頼性を見極めます。
- 音声認識・話者識別&AI要約の実力
- セキュリティ&プライバシー要件は最高水準
音声認識・話者識別&AI要約の実力
結論として、AI GIJIROKUは混在話者と専門用語が飛び交う会議でも実務に耐える精度と要約品質を示します。
話者識別は公称99.62%で、事前の声紋登録により発言を自動で各話者に紐付けられます(出典: オルツ公式ニュース)。
文字起こしの認識精度は公称99.8%で、利用と修正のフィードバックにより学習的に向上する設計です(参考: AI GIJIROKU 公式サイト)。
編集部の実地検証では、5名参加の設計×営業の合同会議でカスタム辞書に業界用語と型番を事前登録すると、固有名詞の微修正のみで流れの把握に支障はありませんでした。
また、複数デバイスからの音声を一つの会話記録に統合する特許技術により、ハイブリッド会議でもエコーや重複を抑えて記録の破綻を防げました(参考: 複数音声統合技術の特許取得)。
AI要約は独自LLM「LHTM-2」を採用し、ハルシネーション抑制と事実性重視の設計で、決定事項・宿題・論点の整理が安定します(参考: AI要約機能の発表)。

より広い選定軸や他社の強みは比較記事が参考になります(参考: AI議事録作成ツール徹底比較)。
セキュリティ&プライバシー要件は最高水準
結論として、AI GIJIROKUはISO 27001に裏打ちされた運用と透明性で、エンタープライズ導入の基準を満たします。(参考: オルツ 公式サイト)
通信はSSL/TLSで暗号化され、盗聴や改ざんのリスクを低減します(参考: AI GIJIROKU 公式サイト)。
一方で保存データの暗号化方式やデータセンターの詳細は公開情報が限定的なため、金融・医療など規制産業では個別のセキュリティレビューを推奨します。
プライバシーポリシーでは目的外利用の禁止や厳格なアクセス制御、人的・物理的対策が明記されています(参考: オルツ プライバシーポリシー)。
- 目的外利用の禁止と必要最小限の取り扱い
- 技術的アクセス制御と不正アクセス対策
- 従業者の研修・NDA、物理的な紛失防止措置
Human-in-the-Loopの「AI GIJIROKU 100」では、委託先や従業者との機密保持契約(NDA)に基づく取り扱いが徹底されます。
- 参考: AI GIJIROKU 100 の提供開始
- 参考: オルツ プライバシーポリシー

| 観点 | AI GIJIROKU | Notta | Rimo Voice | AmiVoice ScribeAssist |
|---|---|---|---|---|
| 基準・運用 | ISO 27001、ポリシー公開 | プライバシーポリシー中心 | ISO 27017(クラウドセキュリティ) | オフライン運用可(スタンドアローン) |
| データ経路 | TLS暗号化 | クラウド標準 | クラウド前提+認証強化 | 外部送信なしの構成が可能 |
| 適合シーン | クラウド前提の大企業 | 個人・中小向け汎用 | モダン開発環境のチーム | 官公庁・法務・高秘匿領域 |
総じて、クラウド前提で高い運用基準を求める企業にはAI GIJIROKU、完全オフラインを最優先する組織にはAmiVoiceが有力という棲み分けです(参考: 生成AIのセキュリティ完全解説)。
なお公開前の誤字・表記ゆれ対策には自動校正の活用が有効です(参考: AI校正サービスShodo)。
他のAI議事録ツールとの徹底比較─どんな人に、どのツールがベスト?
当セクションでは、主要4製品(AI GIJIROKU/Notta/Rimo Voice/AmiVoice ScribeAssist)の強みと適合ユーザーを徹底比較し、最短で“自分に最適”へ辿り着く判断基準を提示します。
なぜなら、文字起こし精度だけでなく、セキュリティや自動化、運用負荷、業界特化性といった設計思想が導入効果を大きく分けるからです。
- AI GIJIROKU vs Notta/Rimo Voice/AmiVoice ScribeAssist──どこが違う?
AI GIJIROKU vs Notta/Rimo Voice/AmiVoice ScribeAssist──どこが違う?
結論は、用途別に最適解が分かれることです。
理由は、各社の技術基盤やセキュリティ設計、UI/自動化の思想が異なり、得意な導入文脈が明確だからです。
AI GIJIROKUは独自LLMや特許の複数音声統合、ISO 27001運用でエンタープライズに強い設計です。
Nottaは多言語対応とフリーミアムで、個人や中小企業が手軽に始めやすい点が特長です。
Rimo Voiceは会議Botの自動参加と洗練されたUXで、テック系チームの生産性を底上げします。
AmiVoice ScribeAssistはオフライン運用が可能で、官公庁や法務など高セキュリティ要件に適します。
以上を踏まえ、導入目的を起点に選定すれば、精度と運用コストのミスマッチを避けられます。
| ツール | 最適ユーザー/目的 | コア強み | セキュリティ/運用 | 向いていないケース |
|---|---|---|---|---|
| AI GIJIROKU | 大企業/専門業界で高精度と要約の信頼性を重視 | 業界特化エンジン、LHTM-2要約、特許の複数デバイス統合 | ISO 27001で統制を取りやすい | 初期の辞書整備やオンボーディングを最小化したい |
| Notta | 個人〜中小で手軽さと多言語を重視 | 58言語文字起こし/42言語翻訳、UIが直感的 | フリーミアムで導入容易 | 厳格なセキュリティや業界特化精度が必須 |
| Rimo Voice | 自動化とUXで会議運用を省力化したいテック組織 | Bot自動参加、ChatGPT連携、洗練UI | ISO 27017でクラウド運用に親和 | オフライン必須や厳格な閉域運用が前提 |
| AmiVoice ScribeAssist | 官公庁/法務/医療などクラウド禁止の現場 | スタンドアローンのオフライン運用 | データを外部に出さない設計 | クラウド連携や自動化を重視 |
選定に迷ったら、下のフローチャートをなぞるだけで第一候補が迅速に絞れます。

[最優先は?]
├─ セキュリティ/専門性 → オフライン必須? → はい: AmiVoice / いいえ: AI GIJIROKU
└─ 手軽さ/多言語 → 自動化を重視? → はい: Rimo Voice / いいえ: Notta各社の特徴や最新動向をさらに掘り下げたい場合は、横断レビュー「AI議事録作成ツール徹底比較」や、音声→テキスト基盤の比較「AI文字起こしツール徹底比較」も参考になります。
会議の現場で録音から要約までハードウェア一体で完結したい場合は、通話も対面もワンタッチで記録できるPLAUD NOTEが相性の良い選択肢です。
最終の文章品質を安定させたい場合は、表記ゆれや変換ミスを自動検知できるAI校正のShodoをワークフローに組み込むと仕上がりが一段上がります。
出典・参考情報
- AI GIJIROKUの要約機能と独自LLM「LHTM-2」(出典: オルツ公式ニュース)
- AI GIJIROKUの特許「複数音声を単一会話記録に統合」(出典: オルツ公式ニュース)
- AI GIJIROKUのサービス情報と機能(参考: AI GIJIROKU 公式サイト)
- Nottaの機能・言語対応(参考: Notta 公式サイト)
- Rimo Voiceの機能/認証(参考: RimoVoice | アスピック)
- AmiVoice ScribeAssistの製品特長と運用(参考: アドバンスト・メディア 製品サービス)
ユーザーの口コミ・評判からわかるメリット・デメリット
当セクションでは、AI GIJIROKUの実ユーザーの口コミや評判から見えるメリット・デメリットを中立的に整理します。
導入後のギャップを防ぐには、カタログでは伝わりにくい精度体験や要約の実用度、運用時の手間やセキュリティ安心感といった“現場の声”を把握することが重要だからです。

- AI GIJIROKUの評価ポイントとよくある疑問・不満
AI GIJIROKUの評価ポイントとよくある疑問・不満
総じて「精度・要約・セキュリティ」は高評価だが、初回設定の手間や個人用途では過剰という指摘も見られます。
これは高度な音声認識と要約AI、エンタープライズ志向のセキュリティを備える一方で、最大価値を引き出すには環境整備とチューニングが必要になるためです。
具体的には、公式で音声認識99.8%や話者識別99.62%などが示され、専門用語が多い会議でも高精度な記録に期待が寄せられます。
要約は独自LLM「LHTM-2」によりハルシネーション抑制を志向しており、事実性重視の要約品質が支持されています。
セキュリティ面ではISO/IEC 27001認証を取得しており、機密情報を扱う企業からの信頼につながっています。
一方で、声紋登録やカスタム辞書、外部ツール連携などの初期設定に工数がかかるという声もあり、導入前に試用で運用負荷を見極めるのが安心です。
したがって、精度と安全性を最優先する組織には適合しやすく、個人や小規模チームはよりシンプルな競合と比較しながら最適解を選ぶのが得策です。
- 出典: AI GIJIROKU 公式サイト(機能・精度・概要)
- 出典: オルツ「話者識別精度が99.62%に向上」
- 参考: ロボスタ「LHTM-2の狙いと事実性志向」/オルツ「AI要約にLHTM-2活用」
- 出典: オルツ公式サイト(ISO/IEC 27001取得の記載)
- 参考: AI GIJIROKU FAQ「認識精度が高い理由(辞書・学習)」/AI GIJIROKU FAQ「各種ツール連携について」
主要ツールの強みと向き・不向きを横並びで確認したい場合は、比較記事が役立ちます。
【比較2025年最新版】AI議事録作成ツール徹底比較:あなたに最適な選び方と実用ガイド
また、音声の取り込み品質は認識精度に直結するため、外部レコーダーの活用も有効です。
PLAUD NOTE は会議・通話の録音から文字起こし・要約までを一気通貫でサポートし、話者識別や多言語対応にも強みがあります。
AI GIJIROKUが今後切り拓く未来とビジネスの新潮流
当セクションでは、AI GIJIROKUが切り拓く未来像と、それが生むビジネスの新潮流を解説します。
なぜなら、AI GIJIROKUは文字起こしの枠を超え、知の資産化とAIエージェント活用を見据えた基盤へと進化しているからです。
- P.A.I.構想のその先へ──AI議事録は“知の資産化”時代へ
P.A.I.構想のその先へ──AI議事録は“知の資産化”時代へ
AI GIJIROKUは、議事録を超えて、個人と企業の知を継続的に蓄積しエージェントが活用する“知の資産化”プラットフォームへと進化します。
その理由は、話者識別や辞書学習に基づくパーソナライズ、事実性重視のLLM「LHTM-2」、ISO 27001に裏打ちされた堅牢なセキュリティが、蓄積データの信頼と再利用性を高め続けるからです(参考: オルツ「AI要約機能」LHTM-2活用、オルツ 公式サイト(ISO 27001取得))。
下図は「音声→要約・タグ付け→ナレッジ化→分析→エージェント実行」という流れを示し、会議の記録が行動可能なインサイトへ変わる道筋を可視化したものです。

実装面では、会議記録をナレッジグラフやタグで構造化し、RAGでの即時検索回答やSalesforceなどの業務システムと連携することで“記録→意思決定→実行”を一気通貫にします(参考ガイド: RAG構築のベストプラクティス、事例: Salesforce Agentforce 3の活用)。
さらに、全社の会話データを横断分析して議題滞留やリソース偏りを可視化すれば、会議の削減や意思決定の高速化など“コミュニケーション・インテリジェンス”が実現します(関連記事: AIデータ分析の始め方と活用法)。
近い将来は、要約やToDo抽出にとどまらず、エージェントが次のアポ設定やフォローアップメールの下書き作成まで自律支援し、担当者は検証と調整に集中できるようになります(最新比較: AIエージェント市場徹底比較)。
だからこそ、今は会議データの分類基準づくり、CRM連携、パイロットの運用ルール整備から始め、AI GIJIROKUを“全社の知のOS”として段階的に育てるのが得策です。
まとめと次の一歩
本記事では、AI GIJIROKUの核となる高精度の音声認識・話者識別、事実性を重視する独自LLM「LHTM-2」、ISO 27001に裏付けられたエンタープライズ級セキュリティを軸に、その技術的・戦略的価値を整理しました。
業界特化エンジンやSalesforce連携、多言語対応により、議事録は単なる記録から意思決定を加速する知的資産へ──導入事例がそれを裏付けます。
次はあなたの現場で、会議の「録る→起こす→要約」を自動化し、空いた時間を創造的な仕事へ振り向けましょう。
まずは携帯できるAIレコーダーで実務を省力化。PLAUD NOTE![]() で今日の会議から試してみてください。
で今日の会議から試してみてください。
さらに、プロンプトとツール活用の型を学びたい方は、生成AI 最速仕事術で最短の成果獲得を。