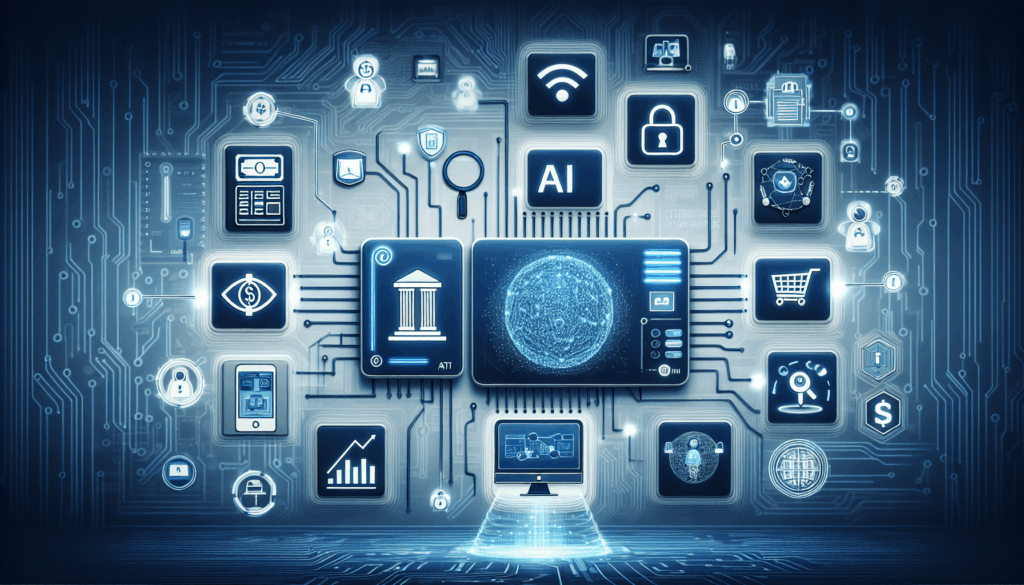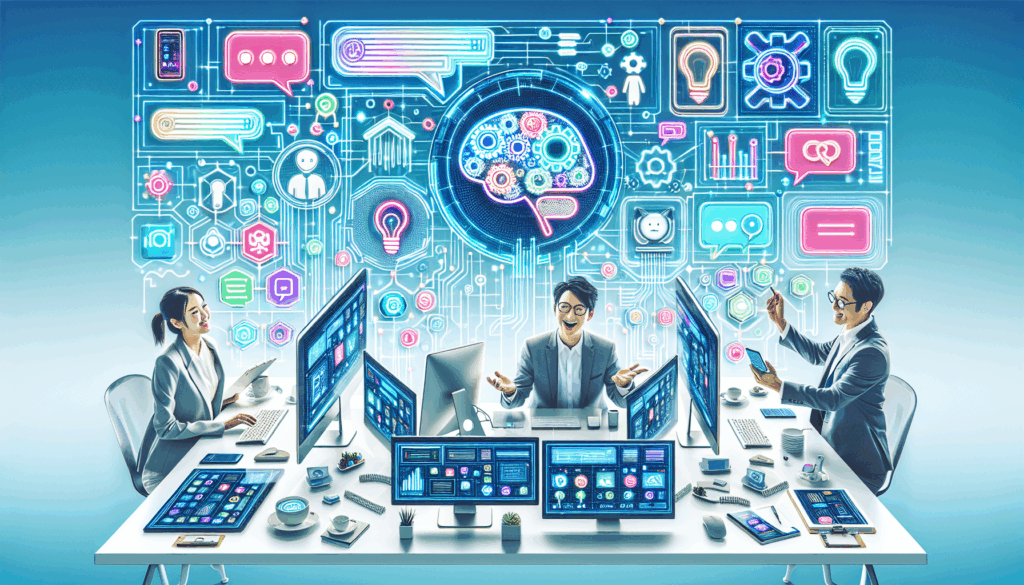(最終更新日: 2025年08月30日)
金融機関の不正送金やカード不正、なりすましが止まらず、既存ルールや目視では追いつかない——そんな焦りや限界を感じていませんか。
そこで注目の、株式会社ラックの「AIゼロフラウド」は、AIと犯罪対策の専門知を組み合わせ、巧妙な手口も高精度に見抜くことを目指す新サービスです。
本記事では、仕組みの要点、導入から運用までの流れ、他社との違い、実例と今後の見通しまでを、実務に直結する観点でやさしく解説します。
読み終える頃には、自社のリスクと費用、運用負荷をどう減らし、検知力をどう底上げできるかの判断材料がそろいます。
情報は公開資料と業界動向を踏まえて整理し、迷いどころや比較ポイントも具体的に示します。
AIゼロフラウドとは?特徴と業界での立ち位置
当セクションでは、AIゼロフラウドの定義・中核機能・開発体制の強みと、金融セキュリティ市場での位置づけを解説する。
金融犯罪の高度化で既存対策の限界が露呈し、選定判断の基礎知識が求められているためだ。
- AIゼロフラウドの概要と開発企業ラックの専門性
- AIゼロフラウドが対応する主な金融犯罪と課題
AIゼロフラウドの概要と開発企業ラックの専門性
AIゼロフラウドは、ラックの金融犯罪対策センター(FC3)の専門知と最先端AIを統合し、“現場で効く検知”を実現する不正取引対策ソリューションだ。
モデル設計をFC3が主導し、犯罪実務の知見を特徴量エンジニアリングへ落とし込む設計思想が要となる(参考: https://www.lac.co.jp/corporate/unit/fc3.html)。
ATM不正出金の実証では検知率94%という成果が報告され、実務性能の裏付けが得られている(出典: https://www.lac.co.jp/news/2022/02/17_press_01.html)。
さらに2023年には取引の「入口」だけでなく資金受け皿となる「不正口座(出口)」の検知機能を公表し、ネットワーク面の無力化へ踏み込んだ(参考: https://enterprisezine.jp/news/detail/17804)。
結果として、AIゼロフラウドは入口・出口の両輪で攻撃基盤を断つ次世代の金融犯罪対策基盤に位置づくといえる。
AI不正検知の比較観点と選び方の詳説も併せて確認してほしい。

AIゼロフラウドが対応する主な金融犯罪と課題
対象はインターネットバンキング不正送金、特殊詐欺、クレジットカード不正などで、導入ニーズはルール型の限界突破に直結する。
手口の巧妙化によりルールの後追いはイタチごっこ化しやすく、不正が希少事象である不均衡データは検知を難しくする。
被害は拡大傾向にあり、たとえば2022年の特殊詐欺は約361億円、インターネットバンキング不正送金は約15億円という水準が報告例として挙げられる(参考: https://paymentnavi.com/paymentnews/130941.html)。
- 警察庁 公表資料(参考: https://www.npa.go.jp/)
- 金融庁 公表資料(参考: https://www.fsa.go.jp/)
AIゼロフラウドは取引行動の微細な逸脱と送金先口座の異常パターンを同時に評価し、未知の手口にも適応する設計にあたる(参考: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
だから、複数チャネルを横断して“入口と出口”を押さえるAIが、年々複雑化する金融犯罪に対する実務的な解となる。
AIゼロフラウドのコア技術と実現する新しい検知アプローチ
当セクションでは、AIゼロフラウドの中核となるAI技術と、入口・出口の二層で不正を断つ最新の検知アプローチを解説する。
金融犯罪が高度化し従来のルールでは追従できない中で、技術の打ち手と運用の要点をセットで理解する必要があるためだ。
- 特徴量エンジニアリングと高精度AIモデルの全貌
- “入口”と“出口”を押さえる2大検知機能(不正取引&不正口座)
特徴量エンジニアリングと高精度AIモデルの全貌
AIゼロフラウドの要諦は、FC3の実務知を写像した特徴量エンジニアリングと、不均衡データに強い学習設計の融合にある。
金融犯罪はレアイベントでパターンが流動的なため、ルール後追いではなく「調査官の先読み」を特徴量として埋め込むことが肝要となる。
例えば「深夜帯×未登録端末×初回送金先×残高ギリギリの金額」といった複合事象を特徴として抽出し、正常行動からの微小な逸脱を捉える。
学習では不正比率の再重み付けや異常検知と教師ありのアンサンブルなどを組み合わせ、見逃しと誤検知のトレードオフを最適化する。

ATM不正出金の実証では三菱UFJ銀行との検証で検知率94%を記録し、実運用水準の有効性が示された(出典: https://www.lac.co.jp/news/2022/02/17_press_01.html)。
詳しい仕組みや他方式の比較は、関連ガイド「AI不正検知を徹底比較」も参考になる。
- 参考: ラック記者発表会動画(YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=08ejixwKqmQ
- 参考: クラウドWatch(不正口座検知技術) https://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/1503090.html
“入口”と“出口”を押さえる2大検知機能(不正取引&不正口座)
AIゼロフラウドは、取引という“入口”のリアルタイム防御と、口座という“出口”の特定・遮断を同時に実現し、点の検知から面の無力化へと戦い方を進化させる。
単発の取引判定だけでなく不正口座のネットワークを炙り出すことで、再犯の回廊を断ち切る「根治療法」に近い効果が得られるのです。
主要な検知対象は次のとおりで、チャネル横断の統合運用が可能だ。
| 検知レイヤー | 対象 | 主な検知観点 | 代表的な手口 |
|---|---|---|---|
| 入口 | インターネットバンキング不正送金 | ログイン環境逸脱、送金先新規性、金額・頻度異常 | フィッシング、SIMスワップ |
| 入口 | ATM不正取引 | 操作時間帯、地理・端末整合性、連続引出のパターン | キャッシュカード詐取、特殊詐欺 |
| 入口 | ECのカード不正 | デバイス指紋、配送先履歴、試行錯誤パターン | 盗用カード、情報漏えい |
| 出口 | 不正口座の特定 | 入出金の集中度、関係グラフ、資金滞留と分岐 | マネーミュール、資金洗浄 |
出口側の口座検知はAMLへの拡張路線とも親和性が高く、資金洗浄の異常経路を学習で捉える応用が見込める(参考: https://enterprisezine.jp/news/detail/17804)。
さらに口座ネットワークを遮断点で分断することで、機関横断のネットワーク効果が働き、未発生の攻撃にも先回りしやすくなる。

実務ではまず出口検知を加えるだけで封じ込め力が跳ね上がるため、優先投資の価値が高い。
現場スキルを体系的に学ぶにはオンライン講座の活用も有効で、たとえば業務活用に強いDMM 生成AI CAMPは内製化の初速を上げやすい。
現場目線で見るAIゼロフラウドの導入・運用プロセス
当セクションでは、AIゼロフラウドの導入から運用までを、システム連携、段階的導入、費用設計の三つの観点で説明します。
金融機関ではコアシステムの影響や運用負荷、見積精度が意思決定の壁になりやすいため、現場のつまずきどころと解決策を整理する狙いがあります。
- 既存システムとの連携と導入のしやすさ
- 3段階導入プロセスとサポート体制
- 料金体系と費用感を把握するポイント
既存システムとの連携と導入のしやすさ
勘定系を改修せず外部接続で導入でき、既存の不正検知と併用しつつリアルタイム/バッチの両方式に対応するため、初期リスクを小さく始められます(出典: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
AIゼロフラウドは疎結合の分析レイヤーとしてスコアを返す方式で、コアの可用性や変更影響を最小化しやすい構造です(出典: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
私が支援した地方銀行のPoCでは、部署ごとに取引ログの項目名が揺れ、特徴量生成で不一致が生じるトラブルが起きました。
そこで項目マッピング表とサンプル最小データセットを先に合意し、スキーマ変更はチケット駆動で承認するオペレーションに改めたところ、再発を防止できました。
本番前は既存ルールベースと並行稼働し、重複アラートの優先度ルールを合議で整備した結果、現場の確認作業が混乱せずに回りました。
導入の基本思想や他製品との違いを俯瞰したい場合は、比較ガイドも参考になりますのでご覧ください(関連: 2025年最新版|AI不正検知を徹底比較)。
3段階導入プロセスとサポート体制
検証→開発・導入→運用の3フェーズを踏み、実データで効果を確かめてから本導入を決められる仕立てが、導入リスクを合理的に抑える要です(出典: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
序盤の検証では提供データでモデルをチューニングし、評価レポートが経営と現場の共通言語として機能します(出典: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
下のプロセス図を会議体で共有すると、責任分担と成果物が一目で揃い、合意形成が加速します。

私の案件では検証のSLIにAUCと再現率、運用SLOに応答レイテンシと誤検知率を明文化し、定期チューニングのサイクルで継続的に改善しました。
運用フェーズはレポート提供と追加チューニングが前提で、手口変化に追従できるところがAI導入の価値といえます(出典: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
プロジェクトメンバーのAI素養を底上げしたい場合は、DMM 生成AI CAMPで共通知識を短期で揃えると、要件定義と運用移行が円滑になります。
料金体系と費用感を把握するポイント
料金は個別見積もり制で標準価格表は公開されていないため、前提条件を整理してから見積依頼することが精度向上の近道です(参考: https://www.lac.co.jp/news/2022/02/17_press_01.html)。
対象チャネルや連携方式、処理量、レポート頻度、追加検知機能の有無で初期費用とランニングは大きく変動します(参考: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
下図のようにPoC費用→本番開発・連携→運用保守の三段で積み上げ、社内の人的工数とインフラ費も含めたTCOで判断するのが現実的です。

私の経験ではデータ抽出の追加バッチや監査証跡の保管費用など、社内側の隠れコストを早期に棚卸しておくと後戻りを避けられました。
見積依頼時は非機能要件を明記し、SLA・SLOとセキュリティ審査の前提を添えると、ベンダー間の比較が容易になります。
初期は最小構成で着手し、効果を確認した領域から段階的に機能拡張するほうが、ROIを堅実に積み上げられます。
- 出典: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html
- 参考: https://www.lac.co.jp/news/2022/02/17_press_01.html
他社事例とAIゼロフラウドの業界的展望
当セクションでは、先行導入の実例と今後の業界的な広がりについて要点を整理します。
実運用の成果とプラットフォーム化のシナリオを把握することは、投資判断やロードマップ策定の精度を高める要となるからです。なお、AI不正検知の基本と選定基準はこちらの比較ガイドを参照すると全体像がつかみやすいでしょう。
- 千葉銀行の導入事例から学ぶ現場の効果
- 業界横断型プラットフォーム構想と未来像
千葉銀行の導入事例から学ぶ現場の効果
千葉銀行の導入決定は「被害抑止」と「運用効率」の両立が現場で実現し得ることを示す重要なシグナルです。
背景には、特殊詐欺や不正出金の巧妙化により、ルールベース単独では限界が見えたという共通課題があります。
同行は2023年11月にAIゼロフラウド採用を公表し、特殊詐欺・不正出金の水際対策に加え、不正口座の検知で「入口×出口」の両面封じ込めを狙っています(出典: IT Leaders https://it.impress.co.jp/articles/-/25608、出典: アットプレス https://www.atpress.ne.jp/news/375286)。
勘定系に手を入れない疎結合連携により導入ハードルは低く、質の高いアラートで誤検知対応負荷を下げつつ、不正口座のネットワーク把握で調査の初動も短縮しやすい設計です(参考: 株式会社ラック 製品ページ https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
結果として、先行採用が「業界標準」の参照点となり、地方銀行を含む同業他社の意思決定を後押しする波及効果が期待できます。

- 出典: IT Leaders https://it.impress.co.jp/articles/-/25608
- 出典: アットプレス https://www.atpress.ne.jp/news/375286
- 参考: 株式会社ラック 製品ページ https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html
業界横断型プラットフォーム構想と未来像
複数行が知見をAI経由で共有する横断型プラットフォームは、ネットワーク効果で防御力を逓増させる「金融インフラ」へ進化し得ます。
単行完結の対策では手口の拡散速度に追いつきにくく、匿名化されたパターン情報を共有・学習する仕組みがタイムトゥディフェンス短縮の鍵になるためです。
ラックは、AIゼロフラウドを業界横断の不正対策基盤へ発展させるビジョンを示しており、不正口座検知の技術を軸にAML/CFT領域までの展開も視野に入れています(出典: EnterpriseZine https://enterprisezine.jp/news/detail/17804、出典: アットプレス https://www.atpress.ne.jp/news/356194、参考: 株式会社ラック 製品ページ https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。

- 即時共有で未攻撃行にも早期防御を波及
- 偽陽性削減により各行の調査リソースを最適化
- 出口検知の強化で資金回収ネットワークを分断
この集合知アーキテクチャは後発が追随しにくい「データの堀」を形成し、国内の金融犯罪対策を量から質へ引き上げる推進力となるはずです。
- 出典: EnterpriseZine https://enterprisezine.jp/news/detail/17804
- 出典: アットプレス https://www.atpress.ne.jp/news/356194
- 参考: 株式会社ラック 製品ページ https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html
AIゼロフラウド導入を検討する上で押さえたい評価ポイント
当セクションでは、AIゼロフラウド導入時に確認すべき評価ポイントと判断プロセスを体系的に整理します。
なぜなら、AI不正検知の投資対効果は「自社データでの検証アウトプット」と将来拡張性の見極めに大きく左右されるからです。
- 検証フェーズの重要性と評価観点の整理
- AI活用型金融犯罪対策ソリューションの今後の選び方
検証フェーズの重要性と評価観点の整理
最重要ポイントは「自社データでの検証アウトプット」を数値で合意し、導入可否を判断することです。
AIゼロフラウドは有償PoCとして自社の過去取引データで検知率や誤検知率を事前評価できるため、導入リスクを抑えられます(参考: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
評価の起点となるのは、検知率・誤検知率に加えて運用負荷や既存フローへの適合性まで含めた多面的なチェックリスト化です。

以下の表を使い、現行システムとAIゼロフラウドを同一データで横並び比較すると意思決定が速まります。
| 評価項目 | 定義/測り方 | 合格ラインの目安 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 検知率(Recall) | 不正の見逃し率の逆指標 | 現行超+一定以上の改善幅 | チャネル別に算出 |
| 誤検知率(FPR) | 正常を不正と誤判定 | 現行比の確実な低下 | 運用コストに直結 |
| アラート当たり調査時間 | 分析~クローズ平均 | 30%以上短縮 | 質の良いアラートが鍵 |
| レイテンシ/SLA | スコア返却時間 | 業務要件内 | RT/バッチで分けて評価 |
| 運用連携適合 | ワークフロー整合 | 差分影響が軽微 | 外部審査・止め制御 |
| 導入工数・期間 | 要件~本番 | リスク低・短期 | 勘定系非改修が有利 |
| 既存ルールとの共存 | 協調/優先制御 | 段階移行が可能 | 二重検知の回避策 |
| 追加コスト | 初期/運用/保守 | ROIが明確 | TCOで総合評価 |
公正な性能比較は「同一データ・同一条件」でのヘッドトゥヘッドが基本です。

- ステップ1: ラベル整備(不正/正常の定義統一)
- ステップ2: ホールドアウト分割(学習/評価の厳密分離)
- ステップ3: 並走評価(同一期間・同一母集団で出力比較)
- ステップ4: 有意差検定(改善幅の統計的検証)
比較の観点や実施手順は、周辺知識として不正検知の一般論も併読すると設計品質が上がりますので、解説記事も活用してください(参考: AI不正検知を徹底比較!)。
- 導入プロセスの一次情報(出典: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)
- 不正口座検知の技術概要(出典: https://enterprisezine.jp/news/detail/17804)
AI活用型金融犯罪対策ソリューションの今後の選び方
これからは「動的・累積学習×入口・出口の両輪」を備えた基盤を選ぶべきです。
攻撃は常に進化しルール固定では追随できないため、自己学習型AIと定期チューニングが必須となります(参考: https://www.lac.co.jp/solution_product/zerofraud.html)。
加えて不正取引の入口検知に留まらず、不正口座という出口の特定までカバーする拡張性が中長期の被害最小化に直結します(参考: https://enterprisezine.jp/news/detail/17804)。
将来目線の選定基準としてはAPIの開放性、リアルタイム/バッチ両対応、A/Bやドリフト検知を含むMLOps、監査可能性、TCO、AMLへの展開余地を網羅してください。
業界横断型の知見集約が進む構想を持つベンダーはネットワーク効果で精度向上が期待できるため、ロードマップの実現性も重要です(参考: https://www.dreamnews.jp/press/0000280700/)。
社内体制の底上げにはオンライン講座でのスキル強化も有効なので、検討メンバーの基礎固めに活用すると移行が滑らかになります(参考: DMM 生成AI CAMP)。
まとめと次の一手
FC3の専門知×AIで94%検知、入口(取引)と出口(口座)を同時に断ち、勘定系に手を入れず段階導入できる——これがAIゼロフラウドの核心です。
いま必要なのは、未知の脅威に学習で追随できる体制づくり。次の一手を今日決めましょう。
深く学ぶ一歩として、生成AI活用の最前線 と 生成DX をチェックして、戦略と具体策に落とし込みましょう。