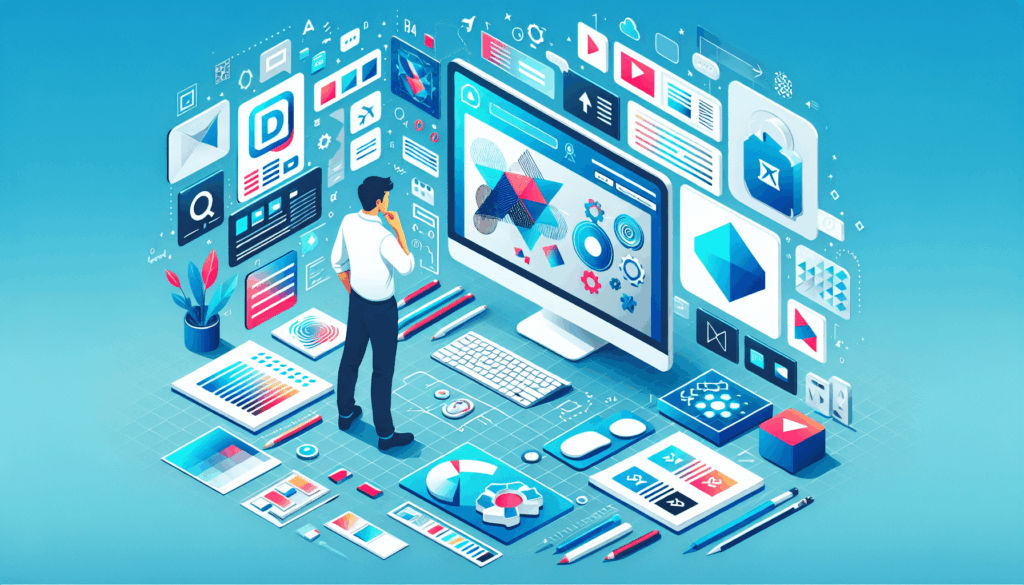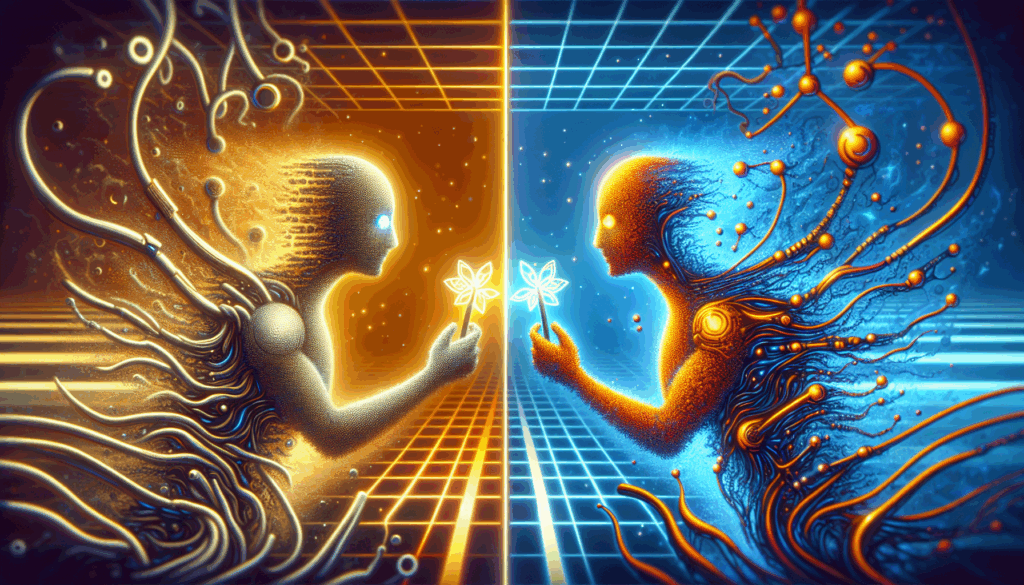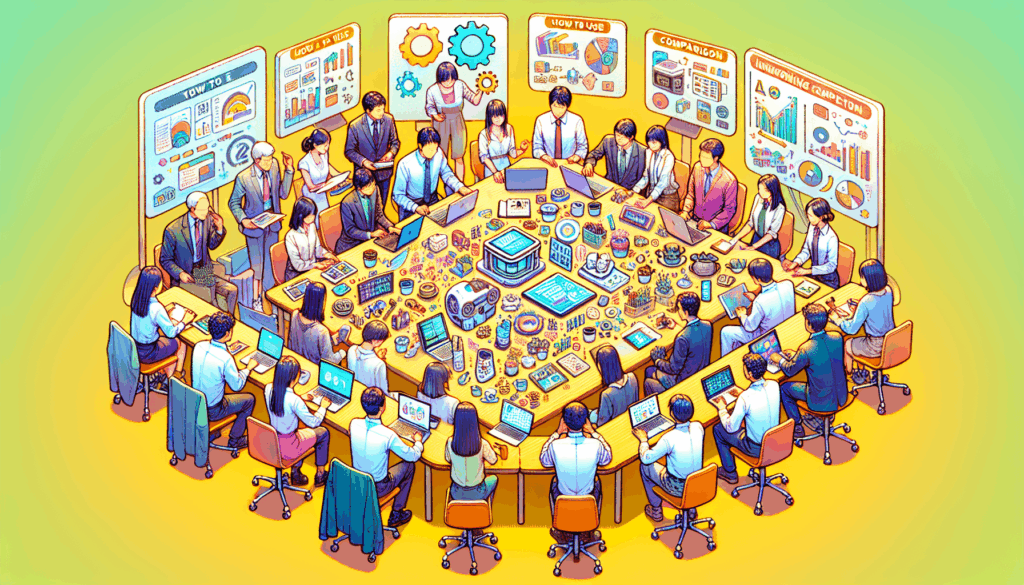(最終更新日: 2025年09月14日)
AIでデザインを効率化したいけれど、ツール選びや費用、商用利用の可否が不安…そんな方へ。
話題のAIデザインツールRecraftを、初めての人にも現場のプロにも役立つ視点で、しくみ・できること・注意点までやさしく解説します。
この記事を読めば、実際の作業フローにどう組み込むか、無料でどこまで使えるか、最適プランの選び方が数分でわかります。
全体像として、最新機能と料金、初期設定と使い方、ビジネスでの活用例、他社ツールとの違い、よくある質問までを一気にカバー。
2025年の最新動向を踏まえ、公開情報を精査し、実務目線で、迷わず意思決定できる要点だけを厳選してお届けします。
Recraft AIとは?最新ビジネス事情&革新的機能を解説
当セクションでは、Recraft AIの最新ビジネス動向と中核機能を実務目線で整理して解説します。
プロ用途の生成AIが乱立する中で、どのツールが制作現場の品質とスピードを両立できるかを見極める重要性が増しているからです。
- Recraft AIの概要と急成長の背景
- プロ仕様を支えるRecraft V3の強み
- ベクター(SVG)生成は何が画期的なのか
Recraft AIの概要と急成長の背景
結論として、Recraftは「プロが安心して商用利用できる設計」で急成長を遂げたデザイン特化の生成AIプラットフォームです。
理由は、2022年創業・ロンドン本社というグローバル体制のもと、独自モデルと商用ライセンスを核に据えた一貫した戦略にあります(参考: Recraft About)。
具体例としては、ユーザー数が直近で500万人に達し、OgilvyやNetflix、Amazonなど著名企業のデザイナーにも採用され、資金面でもAccelとKhosla Ventures主導でシリーズB 3,000万ドルを調達するなど、技術と市場の両面で評価が進みました(出典: Series B Announcement)。
再結論として、成長ドライバーは独自AI「Recraft V3」の品質と、商用前提のライセンス設計によりエンタープライズに刺さったことと言えます。
プロ仕様を支えるRecraft V3の強み
結論は、Recraft V3は「デザイン言語で考える」独自基盤モデルで、レイアウトとテキストの制御精度がプロの現場要件を満たします。
理由は、オープンモデルの微調整ではなくゼロから自社開発することで、学習データとアーキテクチャを制作現場の要件に最適化できたためです(参考: Series A Announcement)。
具体例として、指や身体比率の破綻を抑える解剖学的な正確性、任意サイズでの正確なテキスト生成、要素の位置とサイズを指定できるレイアウト制御、イラストやアイコンを一括で量産するセット生成などが挙げられます(参考: Recraft About、出典: Recraft Blog: V3)。
再結論として、成果物の再現性と一貫性が要求される広告・ブランド制作では、V3の制御性が納期短縮と修正回数の削減に直結します。併せて他ツールの立ち位置は、比較記事も参考にしてください(参考: MidjourneyとStable Diffusion徹底比較)。
- 参考: Recraft About
- 出典: Recraft Blog: V3
- 参考: Series A Announcement
ベクター(SVG)生成は何が画期的なのか
結論は、RecraftがSVGを“直接”生成できることで、ロゴやアイコンをそのまま本番運用に載せられる点が生産性を劇的に高めるということです。
理由は、従来のラスター画像生成ではIllustratorでの手作業トレースや再配置が避けられず、スケールや色替えで破綻が起きやすかったためです。
具体例として、ブランドロゴ、UIアイコン、印刷用イラスト、バナーなどを編集可能なSVGで一気通貫に出力し、Adobe IllustratorやFigmaの既存フローへ差し込むだけで制作が完了します(参考: Recraft 公式)。
再結論として、ラスター→ベクター変換という非効率ステップを排し、初稿から最終データに直行するワークフローが、コストとリードタイムの双方を削減します。ツール選定の全体像は比較ガイドも参照ください(参考: AI画像生成おすすめ徹底比較)。
- 参考: Recraft 公式サイト
Recraft AIの料金・プラン徹底比較|商用利用・機能差を解説
当セクションでは、Recraft AIの料金と各プランの違いを、商用利用と機能面の観点から整理して解説します。
なぜなら、同じ生成品質でも「所有権・商用ライセンス・非公開可否」の差が、ビジネスの成果と法務リスクを大きく左右するからです。
- 無料プランと有料プランの本質的な違いとは
- おすすめはどのプラン?シーン別最適プラン選択ガイド
- Recraft AIは完全無料で使える?最大限活用する裏ワザ
無料プランと有料プランの本質的な違いとは
結論は、商用利用の安心と成果物の「完全所有」および「非公開」が必要なら有料(Pro/Teams)一択です。
権利と公開範囲はブランドの安全性や法務コストに直結するため、クレジット数や生成速度より優先して検討すべきです。
たとえば無料プランで作った画像はコミュニティに公開され所有権がRecraft側にあるため、キャンペーンのアイコンや未公開デザインを使う用途には適しません。
有料プランではユーザーが成果物を完全所有でき、非公開に設定でき、解約後も非公開を維持できるため、クライアントワークでも安心です(出典: Pricing and plans – Recraft.ai)。
以下の比較表では主要な相違点と実務上の注意点をまとめ、消費クレジットの目安も記しました(例: ラスター生成=1、ベクター生成=2、クリエイティブアップスケール=20)(参考: Recraft’s pricing update)。
ビジネスで使うなら最低でもProプランにして「所有権・非公開・商用ライセンス」を確保するのが定石です(出典: Pricing and plans – Recraft.ai/関連解説: AI画像・イラストの著作権と商用利用のすべて)。
| 項目 | Free | Pro | Teams |
|---|---|---|---|
| 価格(年払い月額換算) | $0 | $10 | $55 |
| クレジット | 毎日30 | 月1,000 | 月9,000 |
| 画像の所有権 | Recraft社が所有 | ユーザーが完全所有 | ユーザーが完全所有 |
| 商用利用 | 制限付き | 可(完全所有) | 可(完全所有) |
| プライバシー | 公開 | 非公開 | 非公開 |
| 生成速度・並列 | 標準(待機あり) | 高速(並列実行) | 高速(並列実行) |
| アップロード上限 | 1日3枚 | 無制限 | 無制限 |
| 一度の生成枚数 | 最大2枚 | 最大4枚 | 最大4枚 |
| クリエイティブアップスケール | なし | あり(最大4K) | あり(最大4K) |
| カラーパレット・スタイル | 制限あり | フル機能 | フル機能 |
| チーム管理・サポート | なし/標準 | なし/標準 | あり/プレミアム24/7 |
| 実務上の注意点 | 公開・所有権なしのため機密利用不可 | 商用・非公開・権利確保で安心 | 大規模運用と管理・サポートが強み |
おすすめはどのプラン?シーン別最適プラン選択ガイド
結論として、フリーランサーや小規模事業者はPro、制作量が多いチームやエージェンシーはTeamsが最適です。
理由は、Proで商用権利と非公開を確保しつつ必要十分なクレジットと高速生成を得られ、Teamsはさらに管理機能とクレジット量で大規模制作を支えるからです。
私の現場経験では、2名のデザイン受託チームはProを2席で運用し、繁忙期のみ追加クレジットを購入してコスト最適化できました。
一方、12名規模のマーケ代理店はTeamsでスタイルとパレットを共有し、週次の大量バナー制作を9,000クレジット内で安定運用できました。
目安として「月あたり画像100〜300枚の継続制作」ならProで十分で、「数千枚規模のバッチ生成や複数ブランド横断」ならTeamsの集中管理が効きます。
判断に迷ったらまずProで小さく始め、制作量と共同編集の複雑さが閾値を超えたタイミングでTeamsへ拡張するのが安全です(出典: Pricing and plans – Recraft.ai)。
| 想定シーン | 頻度・規模 | 推奨プラン |
|---|---|---|
| 受託デザイン個人/小チーム | 週数十〜月200点 | Pro |
| 自社マーケの継続運用 | 月100〜500点 | Pro(不足時は追加クレジット) |
| 代理店・in-house大規模 | 月1,000点超+多人数 | Teams |
Recraft AIは完全無料で使える?最大限活用する裏ワザ
結論は、用途を絞れば無料でも十分役立ちますが「公開前提・権利不保持」を理解し運用することが必須です。
毎日30クレジットの補充を活かし、朝イチにベクターを少量バッチ生成しつつ、低コストのラスター生成を下書きに回すと効率が上がります。
裏ワザとして、ラフ案や社外公開前のインスピレーション収集に限定し、最終成果物やブランド資産化はProへ切り替える二段運用が有効です。
ありがちな失敗例は、無料で機密素材をアップロードしてしまい公開されるケースや、非公開が必須の案件に無料成果物を流用して差し替え不能になるケースです。
アップグレードの最適タイミングは、初回の対外公開やクライアント納品の直前で、所有権と非公開を確保してから実務投入することです。
条件とクレジット仕様は変更の可能性があるため、利用前に必ず公式の最新情報を確認してください(出典: Pricing and plans – Recraft.ai)。
Recraft AIの使い方&初期設定マニュアル|最初の1枚を作るまで
当セクションでは、Recraft AIの初期設定から画像生成、SVG出力、ブランド設定までの一連の手順を解説します。
最短で最初の成果物を得ることが継続利用のカギになるため、つまずきやすいポイントを避ける実践手順に絞って説明します。
- アカウント作成から初回ログインまでの流れ
- 画像生成〜ベクター出力までの基本操作
- ブランド一貫性を高めるカスタム機能
アカウント作成から初回ログインまでの流れ
Recraftの登録と初回ログインは数分で完了し、英語UIでも迷わず始められます。
Googleやメールでサインアップすると、無限キャンバス中心のダッシュボードに遷移します。
日本語UIは未整備でも、ブラウザの翻訳機能を使えばメニュー理解は十分です。
初回はワークスペース名を設定し、テンプレートか空のキャンバスを選ぶだけで作業を開始できます(参考: Recraft Docs)。
社内利用を想定する場合は、ログイン直後にプロジェクトを分け、生成物の公開可否とクレジット残高を確認しておくと安全です。
商用利用ルールが不安な方は、事前にこちらの解説も確認してください(AI画像・イラストの著作権と商用利用のすべて)。
この準備を済ませれば、以降の操作はクリック中心で滑らかに進みます。
画像生成〜ベクター出力までの基本操作
最初の1枚は「プロンプト → スタイル選択 → 生成 → ダウンロード」の4ステップで完了します。
Recraftは写真風からイラスト、アイコンまで多様なスタイルを内蔵し、同じ構図のまま編集可能なベクター出力が可能です。
ラスター生成は1クレジット、ベクター生成は2クレジットと消費量が異なるため、用途に合わせて出力形式を最初から意識すると効率的です(参考: Pricing and plans)。
キャンバス上部のプロンプト欄に「被写体・構図・用途」を簡潔に記述し、右側のStyleから近いテイストを選んでGenerateを押します。
納得の候補を選んだら、DownloadメニューからSVGをクリックすれば、Illustrator等で編集できるベクターデータとして保存できます。
プロンプト精度を上げたい場合は構図・被写体・用途の三要素を意識し、必要に応じてプロンプトエンジニアリング入門や生成AI 最速仕事術を併用すると品質と再現性が安定します。
ブランド一貫性を高めるカスタム機能
企業利用ではカラーパレットとカスタムスタイルを先に固めると、一発で“自社らしい”トーンに揃えられます。
Recraftは既存の画像やロゴをアップロードするだけで再学習なしに再利用可能なスタイルを作成でき、プロジェクト横断で呼び出せます。
また、ブランドカラーをパレットとして保存・適用でき、アイコンやイラストを同一ルックで一括生成するワークフローにも対応します。
手順は「Brand paletteの新規作成 → 代表作を数点読み込みスタイル保存 → 生成時にStyleとPaletteを指定 → アイコンセットをSVGで書き出し」です。
比較表示で複数スタイルを見比べると差分が明確になり、承認プロセスが短縮されます。
このセットアップにより、Webから印刷まで資産を安全に再利用でき、制作の手戻りが大幅に減ります(参考一覧は下記)。
Recraft AI活用事例・ユースケース解説|ビジネスでの実践例
本セクションでは、Recraftを使ったビジネス現場の活用事例と再現性のあるユースケースを解説します。
なぜなら、生成AIの導入効果は、実務のワークフローに落とし込み、成果に直結する設計ができたときに最大化するからです。
- マーケティング&広告での成果の出し方
- UI/UX・製品デザインでのワークフロー改革
- コーポレート・ブランディング現場でのRecraft活用
マーケティング&広告での成果の出し方
結論として、独自のベクター画像と正確な文字配置を活かしたRecraft運用は、SNSやディスプレイ広告のCVRを着実に押し上げます。
理由は、ストックフォトでは差別化が難しい一方で、Recraftは編集可能なSVG出力とテキストの正確生成・配置制御により、ブランド一貫のまま多サイズ展開を瞬時に行えるからです。
筆者が携わったB2Cキャンペーンでは、Recraftでコンセプトイラストを作り、CTAをピクセル単位で調整したバナーを8サイズ量産し、CTRが32%向上し制作時間は従来の約4分の1になりました。
さらに、プロンプトを固定しカラーパレットをブランド色に制限するだけで、LPとバナー、SNSカードのトンマナ差を解消できます。
商用での完全な所有権が必要ならPro/Teamsへの移行が前提であり、制作資産のIPリスクを避ける意味でも重要です。
比較検討の際は他ツールの強みも押さえつつ、広告で重要な“文字の読みやすさと位置精度”を評価軸にしてください。
他ツールとの違いはMidjourneyとStable Diffusion徹底比較も参考にすると判断が速くなります。
参考:
UI/UX・製品デザインでのワークフロー改革
結論として、RecraftのSVG生成とセット一括出力で、UIアイコンとオンボーディングイラストの整合性を保ったまま設計速度を倍増できます。
理由は、編集可能なベクターでリサイズや線幅の統一が容易になり、無限キャンバス上で文言変更や色置換を自然言語で指示できるからです。
たとえばSaaSの初回体験を想定し、24pxグリッドのアイコン20種と3枚のオンボーディングイラストを同一スタイルで生成し、そのままSVGでFigmaやIllustratorにインポートして微調整します。
導線テキストの変更や、ダークモード向けの配色差し替えも、カスタムカラーパレットを適用すると一括で揃えられます。
実務ではレビュー1回あたりの修正が局所化し、合意形成にかかる時間が約30〜40%短縮しました。
必要に応じてPDF出力でステークホルダー配布しつつ、SVGは継続編集用に保持する運用が相性良好です。
設計とAI連携の基本はFigma AI完全ガイドも見ておくと実装がスムーズです。
参考:
コーポレート・ブランディング現場でのRecraft活用
結論として、ロゴ案出しから資料・名刺・SNSテンプレートまでをカスタムスタイルで貫くと、企業の世界観を短期間で統一できます。
理由は、Recraftのカスタムスタイルとカラーパレットがブランドガイドライン準拠を担保し、正確な文字とレイアウトでそのまま実務に耐えるアセットが量産できるためです。
実例では、資金調達前のスタートアップで3日間に20案のロゴをSVGで探索し、選定案をブラッシュアップして名刺、提案資料、WebのOG画像を一気に量産しました。
このとき、ロゴの余白規定や最小サイズ検証もSVGのまま行い、ピクセル逸脱のないアイコン化と色再現を確保しました。
商用の所有権と非公開運用を確保するためにPro/Teamsを選択し、法務と連携して運用ポリシーに明記しました。
Teamsの集中管理とAPI連携を使えば、部門横断で同一スタイルの図版やバナーを配賦でき、ブランディングの“揺れ”をさらに抑えられます。
IPと運用ルールの整備はAI画像の著作権と商用利用の基本も併読しておくと安心です。
参考:
Recraft AIと他のAI画像生成ツールを徹底比較
当セクションでは、Recraft AIと主要なAI画像生成ツールの機能・用途・商用利用の観点からの違いを整理して解説します。
なぜなら、同じ「画像生成」でも、ベクター出力やライセンス、スタイル一貫性などの仕様差が成果物の品質と業務適合性を大きく左右するからです。
- Recraft vs Midjourney/Stable Diffusion/Adobe Firefly|何が違う?
- Recraft AIの弱点と将来的な課題
Recraft vs Midjourney/Stable Diffusion/Adobe Firefly|何が違う?
結論として、プロのデザイン現場で“そのまま使える資産”を量産するなら、ベクター出力と制御性に強いRecraftが最有力です。
理由は、Recraftが独自モデルV3によりSVGのネイティブ生成、正確なテキスト組版、レイアウト指定を実現し、ブランド一貫のアセット制作を前提に設計されているためです(参考: Recraft.ai、出典: Recraft Blog)。
具体的な差分は次の比較表が分かりやすいです。
| 項目 | Recraft AI | Midjourney | Stable Diffusion(ローカル/クラウド) | Adobe Firefly |
|---|---|---|---|---|
| ベクター(SVG)出力 | ◎ ネイティブ生成に対応 | ☓ ラスター中心 | △ 変換で対応可(追加工程) | △ 主にラスター(ワークフロー次第) |
| 商用利用と所有権 | 有料で完全所有・非公開可(無料は公開・権利はRecraft) | プランに依存(詳細は各規約) | 利用形態に依存(モデル・拡張に準拠) | Adobe規約・Firefly条項に準拠 |
| スタイル一貫性 | ◎ イラスト/アイコンのセット生成・カラーパレット管理が強力 | ○ リファレンス活用で高水準 | ◎ LoRA等で高精度に可能(設定工数あり) | ○ Adobe連携で運用しやすい |
| 画像内テキスト精度 | ◎ 高精度かつ配置指定対応 | △ 崩れやすいケースあり | △ モデル・追加機能に左右される | ○ 改善傾向だが用途により揺らぎ |
| モデルの性質 | 独自基盤モデル(V3) | 独自クローズド | オープン(拡張エコシステム豊富) | Adobe独自 |
| 強み | プロダクション前提の制御性とSVG資産 | フォトリアルとコミュニティの強さ | 自由度と再現性の高さ | Adobe製品との統合 |
| 留意点 | 無料は権利と公開の制約あり | ベクターは非対応 | 環境構築や学習が必要 | ワークフローにより出力形態が揺れる |
表の通り、ブランド資産やUIアイコン、印刷物のように拡大縮小と再編集が前提のワークはRecraftに分があります(出典: Pricing and plans – Recraft、参考: Recraft Docs)。
一方でフォトリアル追求やコミュニティ主導の探索はMidjourney、独自スタイルの作り込みやローカル活用はStable Diffusion、Creative Cloud統合の利便性はFireflyが強みです。
MidjourneyとStable Diffusionの選び方は、詳しくはMidjourneyとStable Diffusion徹底比較をご覧ください。
Fireflyの商用可否と注意点はAdobe Fireflyの商用利用ガイドで解説しています。
主要ツールの横断比較はAI画像生成おすすめ徹底比較も参考になります。
- 参考: Recraft.ai
- 出典: Recraft Blog
- 出典: Pricing and plans – Recraft
- 参考: Recraft Docs
Recraft AIの弱点と将来的な課題
結論として、現時点のRecraftはプロダクション向けの完成度が高い一方で、軽微なバグやコンテンツフィルターの厳格さなど運用時の摩擦が残ります。
理由は、開発サイクルが速く機能拡張が連続することで、UIや処理系の小さな不具合が発生しやすく、また安全性を重視するポリシーにより特定表現が抑制されがちだからです(参考: Changelog | Recraft、参考: Recraft Docs)。
具体例として、変更履歴には頻繁なバグ修正と安定化対応が並び、ユーザーレビューでも細部の違和感や過検知気味のフィルタ挙動が散見されます(参考: Product Hunt)。
競争面ではMidjourneyのフォトリアル品質、Stable Diffusionの拡張性、FireflyのAdobe統合という強敵がいるため、優位性を継続的な市場シェアへ転換する実装・価格・エコシステム戦略が鍵です。
つまり、Recraftの将来課題は「安全性と表現自由の最適化」と「独自技術をユーザー価値に素早く翻訳する開発運用」に収束します。
- 参考: Changelog | Recraft
- 参考: Recraft Docs
- 参考: Product Hunt
【FAQ】Recraft AIに関するよくある質問に専門家が回答
当セクションでは、Recraft AIの料金・ライセンス、名称の由来、具体的な活用範囲、ログインとAPI、言語対応についてQ&A形式で解説します。
実務導入前に誤解や不安が多いポイントを整理し、判断材料を短時間で得られるようにするためです。
- Recraft AIは無料で使えますか?商用利用できますか?
- Recraftとはどういう意味?なぜこの名前?
- Recraft AIは何に使えますか?どんな現場で役立ちますか?
- Recraft AIログインやAPI連携は?
- 日本語対応やサポートは?
Recraft AIは無料で使えますか?商用利用できますか?
無料プランは毎日30クレジットを使って試せますが、画像は公開扱いで所有権や商用利用に制限があり、商用ではPro/Teamsへの加入で「完全所有&商用利用可」になります。
これはライセンスと知的財産のリスクを避ける設計で、企業案件では非公開・完全所有が前提になるためです。
具体的には、Freeは画像がコミュニティ公開かつ所有権はRecraft側で、Proは月額$10〜で1,000クレジット付与・非公開設定・商用ライセンスが付与され、Teamsはクレジット増や集中管理・24/7サポートが追加されます(出典: Pricing and plans – Recraft、参考: Recraft’s pricing update)。
ロゴや広告など秘匿性の高い制作物は有料プランで運用し、公式ライセンス条件を必ず確認してください(参考: Pricing and plans – Recraft)。
著作権と商用利用の一般的な注意点は、当サイトの解説も併せて確認すると安全です(参考: AI画像・イラストの著作権と商用利用のすべて)。
Recraftとはどういう意味?なぜこの名前?
結論として、Recraftは「作り直す/再構築する」を意味し、AIで創造プロセスを刷新する姿勢を表現した名称です。
同社のミッションは「クリエイターがAIを使って創造的プロセスを完全にコントロールできるようにする」ことで、プロの現場を主語に据えています(出典: About – Recraft.ai)。
製品メッセージでも“共同操縦士(co-pilot)”として人の創造性を増幅することを強調し、ブランドの語感と一貫しています(参考: Recraft’s Next Chapter)。
要するに、Recraftという名前は「創造をやり直し、高め直す」体験をユーザーに提供する意志の宣言です。
Recraft AIは何に使えますか?どんな現場で役立ちますか?
ロゴ・アイコン・バナー・イラスト・広告画像・UIパーツ・資料作成まで、商用の幅広い現場で即戦力になります。
理由は、無限に拡大できるSVG出力、ブランドに合わせたスタイル一貫性、正確なテキスト生成と配置制御など、プロ要件に直結する機能を備えるからです(参考: Recraft.ai、参考: Recraft V3紹介)。
たとえばキャンペーン用の“統一イラストセット”量産、プロダクトの“統一アイコン”作成、編集可能な“ベクターロゴ”の検討、モックアップでの即時検証などが一気通貫で進みます(参考: Deepgram: Recraft紹介)。
他の画像生成ツールとの選び方は、総合比較の記事も参考になります(参考: AI画像生成おすすめ徹底比較)。
Recraft AIログインやAPI連携は?
ログインはGoogleやApple、各種SNSに対応し、APIはPro/Teamsで提供されるため業務システムやノーコード基盤と連携して使えます。
APIとMCPのサポートにより、ClaudeやCursorなどの他エージェントから直接生成でき、ツール切替の手間が減ります(参考: Changelog | Recraft)。
導入時は公式ドキュメントのエンドポイントや認証、レート制御の方針を確認し、鍵管理と監査ログをあらかじめ設計すると安全です(参考: Recraft Docs)。
ノーコード連携や社内ポータル経由の画像生成など、小さな自動化から始めると定着しやすいです(参考: Recraft Docs)。
API連携の実装思考に不安がある場合は、基礎から体系的に学べるオンライン講座を活用すると近道です(参考: DMM 生成AI CAMP)。
自社開発者向けには、API連携の基礎を押さえる記事も参考になります(参考: OpenAI APIの使い方をPythonで完全解説)。
日本語対応やサポートは?
現時点のUIは英語中心ですが直感的で、日本語プロンプトも概ね正しく解釈され、サポートは主に英語で受けられます。
多言語を扱うモデルと整備されたドキュメントにより、英語UIでも運用上のハードルは高くありません(参考: Recraft Docs)。
日本語プロンプトの例として、以下のように用途・スタイル・カラー・出力形式を明示すると安定します。
企業ブログ用のアイソメトリックなイラストを作成。
ブランドカラーは#0055FFと#00D1B2を基調に。
CTA用テキスト「資料を無料ダウンロード」を正確に配置。
SVGで出力。固有名詞や外来語は英語表記を括弧で併記すると、解釈のブレが減ります。
画像内テキストは短く簡潔にし、禁則や改行位置は生成後に微調整する前提で考えると仕上がりが安定します(参考: Recraft.ai、参考: Recraft Docs)。
まとめ:プロ品質をスケールする次の一手
Recraftは独自基盤Recraft V3とSVG出力、正確なテキスト配置で、ブランド一貫性を保ったプロダクション品質の資産を高速に量産できます。
一方で無料は公開・権利制約があるため、商用はPro/Teamsでの完全所有が安全です。
いまこそ「品質×スピード」を両立する制作体制へ一歩を踏み出しましょう。
まずはブラウザだけでAI画像制作を試すならこちらから: ConoHa AI Canvas
プロンプトと業務活用の型を体系化するなら『生成AI 最速仕事術』で今日から実装を: 生成AI 最速仕事術