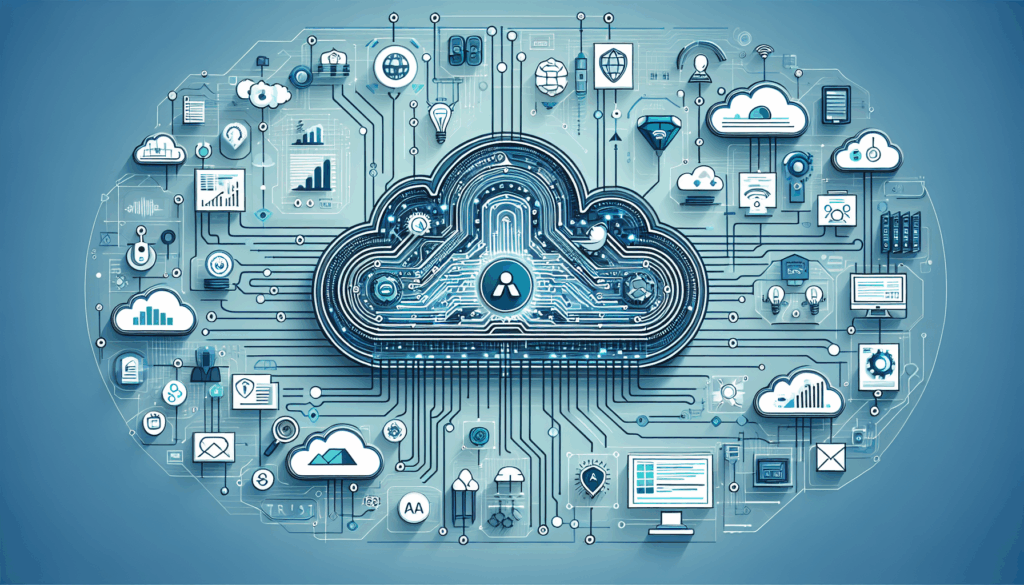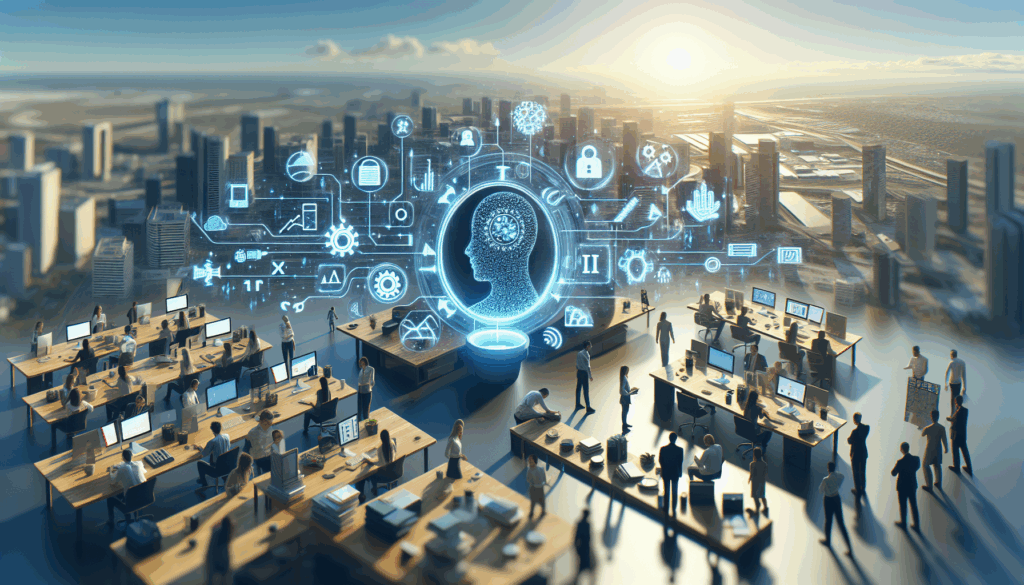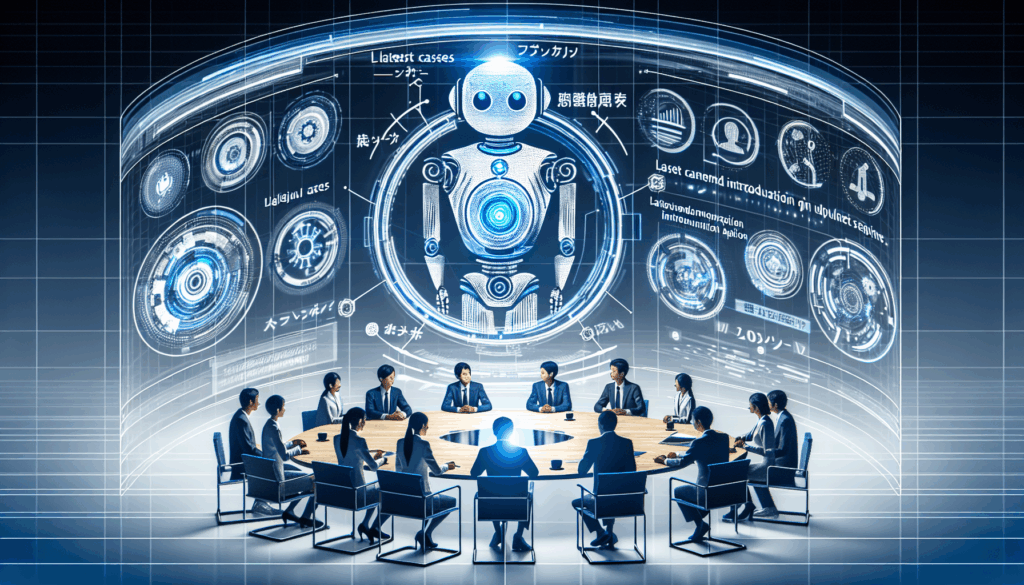(最終更新日: 2025年8月13日)
「Amazon Bedrock AgentCoreって実際どんなものなの?」「使いこなせるか不安…」「他のAIツールと比べたときのメリットや活用方法が知りたい」と感じていませんか?
この記事では、最新AIを業務に活用したいビジネスパーソンやエンジニアの方に向けて、Amazon Bedrock AgentCoreの仕組みから、導入手順・安心して使うための費用や運用ポイント、さらには具体的な現場での活用術まで、わかりやすくまとめました。
これを読めば、AgentCoreの活用イメージがクリアになり、2025年のAI導入を一歩リードするためのヒントが必ず見つかります。
最新情報をもとに執筆しているので、これから導入を検討する方も安心してご覧ください。
Amazon Bedrock AgentCoreとは何か?特徴と位置付けをやさしく解説
このセクションでは、最新のAWSエージェントAI運用基盤「Amazon Bedrock AgentCore」の特徴や、Bedrock Agentsとの関係、その意義についてやさしく解説します。
なぜこの話が重要かというと、AIエージェントを企業で本格運用するには、「PoC(お試し段階)」から「本番」へ移行する際に様々な壁があるためです。
- AWSのエージェントAI戦略を支える「二層構造」
- AgentCoreの主な機能と他AIツールとの優位性
AWSのエージェントAI戦略を支える「二層構造」
Amazon Bedrockエージェントの全体構成は、「プロトタイピング向けのAgents for Amazon Bedrock」と「本番運用狙いのAgentCore」という“二層構造”でできています。
この戦略が採用された理由は、AIエージェントの開発現場で「手軽に試せるが本番導入には不安…」という悩みが頻発したからです。
例えば、多くの企業はAI PoCを「Agents for Amazon Bedrock」を使ってすぐ形にしますが、実際に本格的な業務システムへ組み込もうとすると、急に厳しい要件(セキュリティ、スケーラビリティ、社内外APIとの連携、ガバナンス、監査ログ…)がのしかかり、現場エンジニアは「まさに壁に当たった」状態に陥りがちです。
実際、コンソール作成のPoCは社内デモで大ウケでしたが、いざ本番設計を始めたところ「ID認証どうする?」「LambdaやDB連携の権限制御は?」「監視や障害検知は?」と未解決課題だらけ。「手軽だったはずが、結局ゼロから環境構築…」と苦笑いした方も多いでしょう。
そこで、AWSは「開発スピード重視」と「本番運用重視」を分けて設計しました。簡易ツールのAgents for Bedrockで素早くPoCを作り、実際に価値が確認できたら、スムーズにAgentCoreで堅牢・スケーラブルな基盤に“卒業”できるようデザインされています。
この二段階アプローチにより、PoC段階と本番移行時に求められることのギャップを最小限に抑え、「スピードと安心」の両立を実現しています。
AgentCoreの主な機能と他AIツールとの優位性
AgentCoreの最大の強みは、「どんなAIフレームワークや外部ツールとも連携でき、かつエンタープライズ品質のセキュリティ・運用性を“標準”で備えている点」にあります。
従来のAIプラットフォームやフレームワークだけだと、以下のような課題が顕在化しやすいです。
- セキュアな実行環境やID認証(SSO・OAuth等)の自作が必要になり、手間もリスクも高まる
- オンプレ/クラウドの業務API統合や権限管理が複雑化しがち
- エージェントの「会話の文脈保持」や永続ストレージ連携を自前で用意しないといけない
- コスト効率・安定稼働を担保する監視とトレーシング環境がバラバラになる
AgentCoreなら、こうした「本番化の壁」を一手に引き受けてくれるため、現場エンジニアは“ビジネスロジック作り”に集中できます。
さらに、他社AIプラットフォームと比較しても、フレームワーク非依存かつオープンな運用基盤・ID連携・可観測性・柔軟なAPI統合の「全部入り」アーキテクチャは、現時点で随一です。
例えば、LangChain/CrewAIなどのOSSエージェントや、Google Vertex AI、Azure AI StudioのMLOps/LlMOps系と比較した場合の特徴は次の通りです。
| 機能/特徴 | AgentCore | Agents for Bedrock | 他AIツール例 |
|---|---|---|---|
| 開発フェーズ | 本番運用/大規模利用 | PoC/プロトタイピング | 各社異なる |
| フレームワーク対応 | LangGraph/CrewAI等OSSもOK | Bedrock専用 | 多くはベンダーロック |
| セキュリティ | 本番品質(分離、権限、暗号化) | 簡易的 | 要自作/プラグイン |
| ID/認証統合 | SSO/OAuth連携など標準 | 限定的 | 個別対応 |
| 外部API統合 | Gatewayで任意APIを即ツール化 | OpenAPI経由、制限あり | 個別実装 |
| メモリ | 短期・長期メモリ両方標準装備 | 短期のみ | 要自前実装 |
| 監視/トレース | OpenTelemetry等と連携可 | 基本的なトレース機能 | ツールごと |
つまり、企業で「AIエージェントを本気で業務システムに取り込みたい」場合、AgentCoreの導入によって、セキュリティや複雑な運用要件でつまずく心配が大幅に減ります。
PoCのスピード感と、本番化の安心感を両立したい現場にとって、AgentCoreはまさに“頼れる仲間”になるでしょう。
【徹底図解】Amazon Bedrock AgentCoreの実践的な使い方ガイド
このセクションでは、Amazon Bedrock AgentCoreの実践的な活用法と導入ステップを徹底的に解説します。
なぜなら、AgentCore導入の「全体像」を明確に把握し、そのうえで具体手順や応用パターンを知ることが、現場へのスムーズな本番展開・戦略的な業務自動化の成否を大きく左右するからです。
- プロトタイピングから本番運用までの全体像
- AgentCore導入までのステップバイステップ手順
- 実務ワークフローでの応用例:複数エージェント連携やヒューマンインザループ
プロトタイピングから本番運用までの全体像
Amazon Bedrockエージェント開発の正攻法は、「コンソールで高速プロトタイプ→本番志向のAgentCore環境へ卒業」という二段階構成です。
なぜなら、ローコード・GUI主体のAgents for Bedrockは爆速でアイデアを形にできますが、セキュリティや運用自動化といったエンタープライズ要件には限界があるからです。
たとえば、まず管理画面でLambda連携のシンプルなワークフローを作り、動作検証や社内プレゼンが終わったタイミングでBedrock AgentCoreに移し替えれば、プロトタイプ時の資産(API仕様やプロンプト設計)を最大限活かしながら、本番グレードのセキュアなサーバーレス実行基盤へ“シームレスに卒業”できるのです。
このような「プロトタイピング→本番化(卒業パス)」の流れは、PoC段階のスピード感と本番品質のトレードオフという、大企業現場のリアルな課題を解決する合理的な開発ジャーニーといえるでしょう。
AgentCore導入までのステップバイステップ手順
AgentCoreへの移行や新規開発では、「IAM設定→Lambda連携→エージェント作成→IaC→Docker化→本番デプロイ→ワークフロー連携」という段階的なステップが不可欠です。
この理由は、AWS管理者権限まわりのトラブルやDocker化時の行き詰まり、Step Functionsとの連携ミスなど、どれか1つでも抜けると“現場のPoCが止まる”実体験例が少なくないからです。
まず公式ハンズオン(Amazon公式チュートリアル)でIAMやLambdaの基本をおさえ、次にPythonのBoto3サンプル(GitHubサンプル)を試しましょう。
SDKによるIaC化例はAWS公式ライブラリ(Boto3コード例)、AgentCore用Dockerワークフローはbedrock-agentcore SDKのリポジトリ(bedrock-agentcore-sdk-python)が参考になります。
さらに、本番運用を見据えAWS Step Functionsと連携して、エージェント複数段タスクやヒューマンインザループ判定まで実装できるようにしましょう(AWS公式ブログで動画&図解多数)。
実務ワークフローでの応用例:複数エージェント連携やヒューマンインザループ
Bedrock AgentCore最大の強みは、業種横断で使われる「R&D×法務×財務」型マルチエージェント設計や、人間(担当者)との協調判定パターンを本番品質でデプロイできる点です。
これは、金融・製造・マーケ現場でよくある「1エージェント=万能ではない。部門ごとの知識や判定ロジックを分散させ、最後に“つなげる”」現実に直結しています。
たとえば製薬企業PharmaCorpの実例では、R&Dエージェントが候補薬を解析→法務エージェントが知財判定→財務エージェントが資金管理を担当し、各エージェントの専門性をStep Functionsで連携し“タスクをリレー”しています。
しかも途中で人間のレビュー判断を挟めたり、全工程を監査トレース付きで運用できる(AWSベストプラクティスに実装例)など、本格業務への応用力が桁違いです。
利用料金・クォータ・ガバナンスを完全理解:失敗しないコスト&運用計画
このセクションでは、Amazon BedrockエージェントおよびAgentCoreの利用料金体系、クォータ(利用上限)、運用時のガバナンスに関する要点をわかりやすく解説します。
なぜなら、AIエージェントの本番運用では「どんな費用がかかるか」「想定通りにスケールできるか」「どのリージョンで利用可能か」を把握しなければ、ROI評価やシステム冗長化に大きな落とし穴が生じるからです。
- ベースコスト:モデル推論料金と各コンポーネント課金の全体像
- コスト見積もり・最適化実践ポイント
- 運用上の制約とAWSリージョン対応状況
ベースコスト:モデル推論料金と各コンポーネント課金の全体像
BedrockエージェントやAgentCoreを導入する際、最重要なのは「料金構成の全体像」を把握することです。
なぜなら、AIエージェントの運用コストは、モデル推論(FM)、AgentCoreの各コンポーネント利用料、さらにAWS Lambda・S3ストレージやベクトルDBなど、複数サービスの費用が積み上がる「多層構造」だからです。
たとえば、Bedrockのモデル(ClaudeやLlamaなど)は、利用したトークン数や予約キャパシティにより単価が大きく変動します。AgentCoreのRuntime、Browser、Code Interpreter等は「vCPU-hour/GB-hour」の従量課金に加え、GatewayやMemory、Identity機能は呼び出し回数や保存件数ごとに細かく課金されます。さらに、LambdaやS3のトリガーやストレージは、利用頻度やデータ量によって思いがけない負担増につながることもあります。
以下の図は、各レイヤーの料金構成や代表的な課金単位の関係を視覚化したものです。事前に全体のコストイメージをつかむことで、無駄や予期せぬ費用の発生を最小限に抑えられます。
このように、AgentCoreでは「使ったぶんだけ支払う」設計なので、想定ユースケースごとの構築ミスやサービス選択の誤りが致命的コスト超過につながるリスクもあります。
コスト見積もり・最適化実践ポイント
AIエージェント開発で失敗しないコスト管理には、「細かい利用パターンの見積もり」と「最適化シナリオの実践」が欠かせません。
なぜなら、ユーザー1回の対話でモデル推論が何回発生し、どのツール(Lambda)がトリガーされ、ナレッジベース検索が何件行われるかで、大きくコストが変動するためです。
例えば、「請求書自動チェック」というユースケースを考えると、一般ユーザー向けなら小型モデル(Claude 3.5 Haikuなど)+キャッシュ活用で十分なケースも多く、この組み合わせだけで推論単価を3分の1以下に抑えられます。一方、経営層向けのレポート生成など複雑なタスクでは、大型モデルや計算リソース・ナレッジベース利用回数が跳ね上がるため、バッチ推論導入やキャッシュ&インテリジェントルーティング(例:「ルーティング設計で30%コスト削減」のシナリオ)を戦略的に検討しましょう。
現場で実際によくある失敗談として、「本番想定トラフィックで単価計算せず、LambdaやベクトルDBのAPI料金が想定を大きくオーバーした」「キャッシュ設計を入れ忘れて同一問い合わせに何度も高額な推論処理が走った」などが知られています。必ず見積もりにコスト可視化ツール(AWS Pricing CalculatorやCost Explorer)を組み合わせ、試算パターンを複数作るのが成功の近道です。
運用上の制約とAWSリージョン対応状況
運用設計では、利用クォータやリージョン制約が本番システムの障害ポイントになることに注意しましょう。
なぜなら、AgentCoreとBedrock Agentsでは、用途や優先するスケール要件が異なるため、各サービスで上限値や機能展開範囲に大きな差が生まれるからです。
例えば、AgentCore Runtimeでは、アカウント単位・リージョン単位で同時アクティブセッション数やエンドポイント呼び出し数(デフォルトは500程度/最大引き上げ可)、メモリやブラウザ等の同時実行数など、複雑かつ細かい利用上限が定められています。しかも、最新のAgentCoreは日本含め一部リージョンでは未提供で、「グローバル展開を計画していたが欧州先行のためスケジュール修正」といった実運用での混乱も散見されます。
このような制約への対策として、プロダクト設計初期から「クォータ・リージョン制限」を織り込むことが、コスト予測以上に重要です。リリース後の拡張・移行コストや想定外のサービス制限を避けるため、必ず最新のAWSドキュメント(Bedrock AgentCore公式)を定期的にチェックしましょう。
業界ユースケースとAI導入インパクト:AgentCoreが選ばれる理由
当セクションでは、Amazon Bedrock AgentCoreを中心としたエージェントAIの業界別ユースケースと、なぜ今、企業がAgentCoreを選ぶのかという本質的な理由を解説します。
なぜなら、エンタープライズAIの導入効果は単なるコスト削減やチャット効率化にとどまらず、組織全体のワークフロー革新や新ビジネス創出というレベルにまでおよんでいるからです。
- 金融・製造・ヘルスケア…主要産業での最新導入事例
- AgentCoreを選択することで得られる経営・事業インパクト
- これからのエンタープライズAI戦略に向けてのポイント
金融・製造・ヘルスケア…主要産業での最新導入事例
Amazon Bedrock AgentCoreは、金融・製造・ヘルスケアなど多様な産業でコア業務のデジタル変革を牽引しています。
その理由は、AgentCoreが単なる自動応答エージェントではなく、組織内のAPIやナレッジベースと連動し、複雑な意思決定やワークフローの自動化にまで対応できる点にあります。
たとえば金融業界では、コンプライアンス報告書作成(SARドラフトの自動草案)や本人確認(KYC)の多段階処理をAIが分担し、ヒューマンエラー削減と審査スピードを両立させています(AWS公式ブログ: AgentCore事例)。
製薬企業のPharmaCorpでは、R&D・法務・財務の各部門専用エージェントを連携させ、従来は部門横断型で非効率だった経営インサイトの抽出が、わずか数分で自動レポート化されるようになりました(マルチエージェント事例)。
このような高度応用が現場で普及している理由を一言で表すなら、AgentCoreが「連携」と「自律性」を本気で両立できる設計だからです。
AgentCoreを選択することで得られる経営・事業インパクト
AgentCoreの導入によって、経営と現場両方の視点で、業務効率化にとどまらない抜本的な変革が実現されています。
なぜなら、AgentCoreが提供するモジュール型基盤(セキュアなランタイム、ID統合、ガバナンス監視など)が、企業ごとのシステムや外部サービスとの“本番統合”を救うからです。
実際、ある大手保険会社では、従来1案件ごとに30分以上かかっていたマーケティングキャンペーン構築が、AgentCore導入後はインテリジェントエージェントの自動化により20分短縮(最大30%工数削減)、新規開発サービスも年間2件増加したという定量成果が公式に発表されています(AWS News Blog)。
また製薬企業でのデータアクセス民主化の事例では、自然言語によるレポート自動生成や部署横断での知識検索実現により、“知的資産の活用量”が以前の3倍を記録しています。
つまりAgentCoreを選ぶ本当の価値は、単なるコンバージョン率向上や労働時間削減の枠を超え、「全社のデジタル競争力を底上げするAI基盤」として機能する点にあります。
これからのエンタープライズAI戦略に向けてのポイント
これからのAI推進企業が押さえるべき最大のポイントは、プロトタイプ段階と本番運用段階を明確に分け、それぞれに最適なプラットフォーム設計を選択することです。
なぜなら、短期のPoCと全社スケールの本番化では、求められる柔軟性・セキュリティ・インフラ管理工数が全く異なるためです。
具体的には、「Agents for Amazon Bedrock」で高速な価値検証を行い、運用フェーズではAgentCoreのアンバンドル設計(モジュール単位の選択的利用)へ段階的に移行する“卒業パス”が、AWS公式でも推奨されています(AgentCore公式ドキュメント)。
また、現場チーム主導によるプロトタイプ展開と、経営層によるガバナンス&コスト統制を同時に満たす設計が求められます。
この「プロトタイプと本番運用の切り分け」「アンバンドル型の柔軟運用」「現場主導×ガバナンスの両立」が、今後の戦略的AI導入の黄金則です。
まとめ
AWSのエージェントAI導入は、スピード感を重視したプロトタイピングから、エンタープライズレベルの本番運用まで、二層構造で最適化されています。
まずは「Agents for Amazon Bedrock」でPoCを高速化し、ビジネス価値の検証後は「AgentCore」でスケールやガバナンス、セキュリティ対策を盤石にしましょう。
今こそAIエージェント活用の最前線に立つためのアクションを始める絶好のタイミングです。実際に生成AIを業務活用するにはノウハウや具体的な事例・プロンプト集を学ぶことが近道です。
生成AI 最速仕事術 なら、AI時代の仕事術・プロンプトの型・ツールの組合せまで具体的にわかります。
さらに実践派のあなたには DMM 生成AI CAMP で、本格的な生成AIスキルをオンラインで体系的に磨くという選択肢も。
この知見を活かし、次の一歩を今、踏み出しましょう。