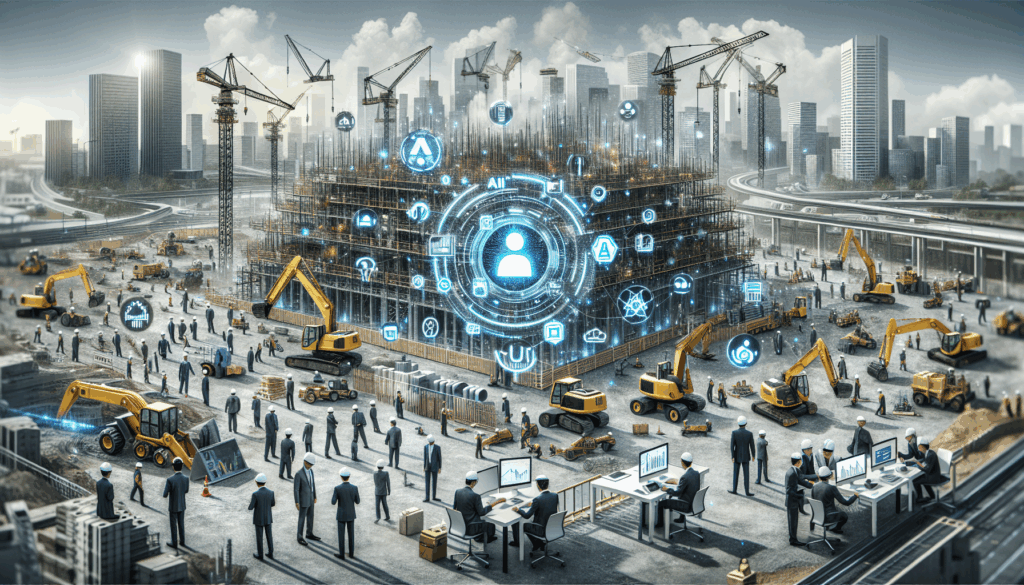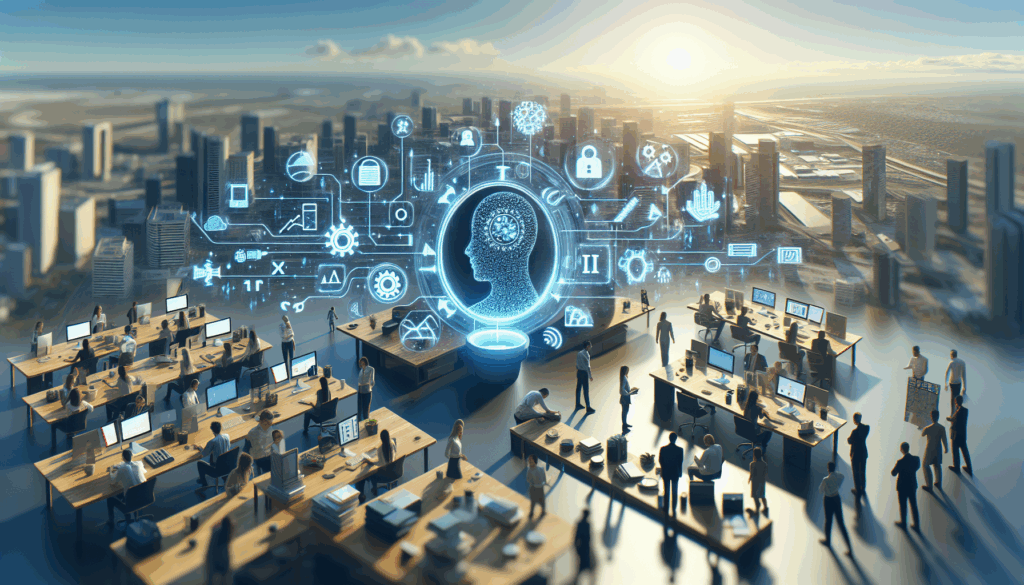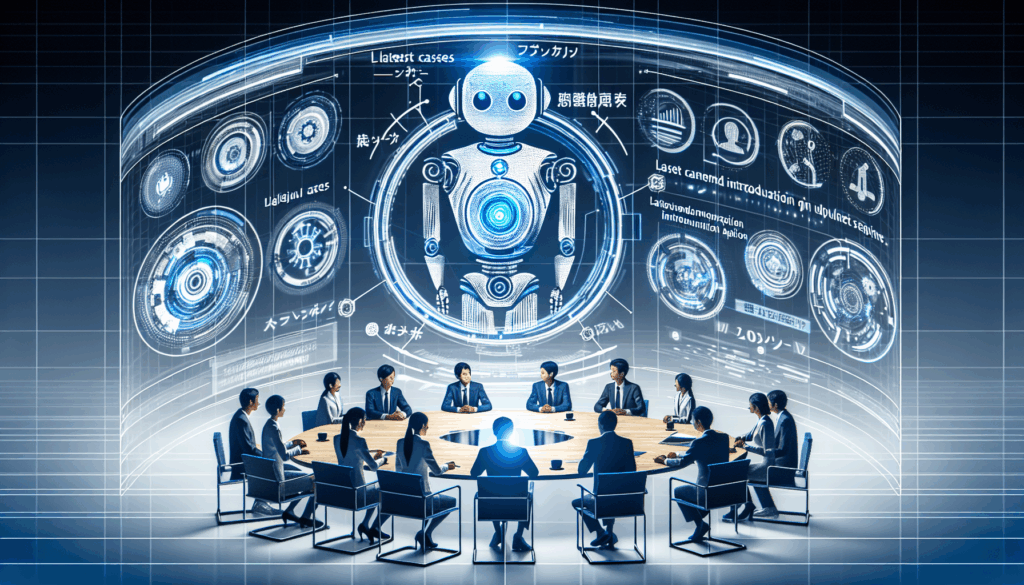(最終更新日: 2025年07月14日)
「AIを導入したいけど、どのツールが本当に役立つのか分からない」「他社はどうやって人手不足を解消しているの?」――建設業で働くあなたも、こんな疑問を感じていませんか?
この記事では、実際にAIを活用して生産性を上げている有名ゼネコンや施工会社の最新事例や、2025年注目のAIツール・サービスを分かりやすくまとめました。
現場目線の課題や、今から取り組める導入ノウハウを詳しく解説。これからAIを活用したい方の「どう始めればいい?」に答えるリアルな情報を揃えています。
信頼できる最新データや先進企業事例をもとに、自社に最適なAI活用のヒントを得られる内容です。ぜひ最後までご覧ください。
業界全体の動きと建設AI導入のリアル――どんな課題、どんな戦略?
当セクションでは、日本の建設業界全体におけるAI導入の現状や戦略、その課題について段階的に解説します。
なぜなら、国内建設業界では政府主導でAI活用が推進されており、政策のビジョンから現場の実務へと、どのようなリアルな動きや障壁があるのかを知ることは、今後の技術活用・働き方変革のヒントになるからです。
- 国策として推進される建設AI──i-Construction 2.0とは何か
- 日建連アンケートで明らかになった生成AI活用の実態
- 導入障壁と今後の業界のAI戦略
国策として推進される建設AI──i-Construction 2.0とは何か
日本の建設業界は「i-Construction 2.0」という国策により、AIとオートメーション導入を加速度的に推進しています。
これは、少子高齢化による人手不足、インフラの老朽化、現場の安全対策など、深刻な業界課題を背景にした国家的な戦略です。
例えば、国土交通省は「2040年までに建設現場の3割を省人化し、死亡事故を大幅に減らす」という明確な数値目標を掲げており、これを後押しする具体策として、建設機械の自動化、BIM/CIM(3D設計データ)の普及、リモート施工管理の強化などが挙げられます。
また、「AI-PF」や「BRIDGE」プログラムのように、国が官民連携で教師データを整備し技術開発を支援することで、単なる掛け声では終わらない現実的な土台を整えています(国土交通省公式HP参照)。
このような官民一体型の施策があるからこそ、日本の建設AI導入は「現場の未来を描き換える壮大な社会実験」と言えるでしょう。
日建連アンケートで明らかになった生成AI活用の実態
業界大手の16社すべてが生成AIの活用に前向きですが、実態は「業務で使う分野」と「現場での活用」の間に大きなギャップがあります。
これは日建連(日本建設業連合会)の2024年調査でも明確に示されました。
たとえば、多くの企業が「翻訳」「要約」「議事録作成」「プログラミング支援」といったオフィス業務で生成AIを使い始めていますが、「現場の施工・安全管理」や「検査作業」など、本丸となる作業領域でのAI導入はまだ限定的なのです。
その最大要因は「情報の信頼性」と「セキュリティ」への懸念であり、多くの企業が社内限定のAI環境(イントラネットAIチャットボット等)を構築するかたちで慎重に進めている現状が「現場の声」からも浮き彫りになっています(日建連調査PDF)。
結論として、AIは「まずリスクの低い間接業務から現場へ段階的に入る」段階的戦略が主流であり、今後の展開が注目されています。
導入障壁と今後の業界のAI戦略
建設AI導入の最大のハードルは、高コスト・人材不足・データガバナンス・社内文化など多面的かつ現場固有の課題です。
筆者も実際にAIシステム導入現場の支援で痛感したのは、「一気に現場を変える」ことの難しさでした。
組織では「こういう最新AIが役立つ」とプレゼンしても、『現場担当者が日々使い続けて定着する』までには、トレーニング期間や信頼関係、そして「設計、オフィスから段階的に」小さく始めて成果を可視化する着実なステップが不可欠です。
こうした現場のリアルな課題を踏まえ、多くの企業では「オフィス業務→現場業務」と二段階で適用範囲を拡大し、人間拡張(ヒューマン・イン・ザ・ループ)の発想をベースとした変革が戦略の主流となっています。
この柔軟かつ実証重視の姿勢こそが、AIと現場の“共進化”を可能にし、未来の建設業競争力のカギとなるでしょう。
主要ゼネコン・建設会社の先進事例――“成果が出たAI活用”の全貌
当セクションでは、建設業界をリードする主要ゼネコン・建設会社による「実際に成果につながったAI活用事例」の全貌について解説します。
なぜなら、AI活用の成功実例からは、業界共通の課題解決ノウハウのみならず、各社の独自戦略や先端技術の具体像が見えてきて、自社導入や競争戦略のヒントとなるからです。
- 鹿島建設:セキュアなAIエコシステム戦略
- 大林組:設計・安全管理を加速するAIの現場事例
- 清水建設:非構造化データの自動処理・現場AIの最前線
- その他会社の注目事例:xenoBrain/日立・北野建設など
鹿島建設:セキュアなAIエコシステム戦略
鹿島建設は自社専用のAI基盤「Kajima ChatAI」や災害知識の可視化AI「K-SAFE」など、セキュリティと社内データの活用に徹底的にこだわったAIエコシステムを構築しています。
その理由は、業界特有の機密情報や専門知見(例:建築基準法・社内基準・施工法など)を守ることはもちろん、「社外AIとの差別化」や、AI活用範囲の拡大がこれで可能になるからです。
例えば、2023年からグループ全社員が使えるKajima ChatAIの開発では、Microsoft Azure OpenAI基盤上にイントラネットで専用環境を設け、自社で集積した膨大な技術資料・法令・過去の災害事例などをAIが学習。従来丸一日かかっていた法規調査や、特殊な施工条件の知見検索も、数十秒~数分で完了するケースが増えています(出典:鹿島建設公式ダイジェスト)。
また、現場安全分野ではK-SAFEが6万件超えの災害事例データを解析し、作業内容に応じてAIがリスクを即座に提示。これにより危険予知活動の質が飛躍的に向上し、「新人でも違和感なくベテラン同等の知見を得られる」点が現場から高く評価されています。
加えて、ドローン画像解析やデジタルツイン(鹿島スマートBM)を活用した効率的な建物管理の仕組みも同時に社内展開を進めている点も特徴です。
このような「壁に囲まれたAIプラットフォーム」戦略は、建設業界で主流となりつつあるエンタープライズAI導入の鍵とも言えるでしょう(参照:日建連アンケート調査)。
大林組:設計・安全管理を加速するAIの現場事例
大林組は、設計現場と安全管理現場の双方で“AIの現場定着”に注力しており、設計の自動化や安全リスクの可視化で独自の成果を出しています。
設計分野で注目されるのは「AiCorb®」という、手描きスケッチから自動でファサード案や3Dモデルを瞬時に生成する設計支援AIです。
利用エピソードとして、「施主との初回ミーティングで、その場で複数のデザイン案をAIがリアルタイムに提案し、合意形成のスピードが大幅に向上した」という声が現場から上がっています(出典:東証マネ部 大林組事例)。
安全管理では、MetaMoJiと協業したeYACHOの危険予知AI(KY活動自動化)が、厚労省公的DBや自社災害履歴と連携。作業内容に基づきAIがリスクと対策を自動提示し、若手担当者も「自分の視点だけでは見落としていたリスクもAIが気づかせてくれる」とその導入効果を実感しています。
さらに、品質管理では画像認識AIによるコンクリートひび割れの自動検出も始まっており、手作業による目視チェックの負担を大幅低減しています(詳細:Lightblue Tech事例)。
清水建設:非構造化データの自動処理・現場AIの最前線
清水建設は、AIによる膨大な非構造化データ自動処理や、人の熟練が必須だった現場技能の“AI化・自動化”に躍進しています。
全社導入されたAIアシスタント「Lightblue Assistant」は、RAG技術で施工要領書・設計基準書から必要な情報の即時検索が可能です。これにより、例えば「一つの設計調査・法規チェックに従来2~3時間かかっていた作業が、わずか数分で完了」といったビフォーアフターが現場から報告されています(参考:ITmedia NEWS 清水建設全社導入事例)。
また、音声から自動で議事録を作成する「Rimo Voice」は、会議後の手入力作業を大幅に減らし、「会議終了と同時に議事録が完成・即配信できる」という効率化効果も得ています。
さらに、“熟練技術自動化”の最前線として、シールドマシンの掘進制御AIでは、地盤状況に応じた最適操作を自動判断。担当者が「技能者が不足する現代、AIが技能伝承の役割を担う点が特に大きい」と語るように、人的スキルのAI化が現場力の底上げに直結しています。
新たな防災分野では、AI火災検知など現場安全もカバーし、「AI活用で1日あたりの業務時間40%削減」などの具体的成果も数値で公表されています(詳細:SEデザイン清水建設事例)。
その他会社の注目事例:xenoBrain/日立・北野建設など
中堅ゼネコンや地域建設会社でも、用途に特化したAIや自社ナレッジチャットボット等の導入が着実に進んでいます。
例えば、西松建設は建設業界向け経済予測AI「xenoBrain」を活用し、物価変動下でも最適なコスト見積もり・調達計画の策定を実現しています。
また、北野建設と日立ソリューションズは、国土交通省の公開資料や自社文書を学習した独自生成AIチャットボットを開発中です。これにより“現場担当者が膨大な行政・社内情報を会話形式で即座に入手”できる環境が整いつつあります(出典:日立ソリューションズ公式)。
こうした動向からも、「大手だけでなく、用途特化AIやクラウドベースのナレッジAIによる業務効率化・競争力強化」が、中堅・地域企業にも波及していることが分かります。
これで分かる!2025年最新 建設AIツール主要製品・提供会社まとめ
当セクションでは、2025年時点で注目されている建設AI関連の主要製品およびその提供企業について、分野ごとに最新の状況を詳しく解説します。
なぜなら、建設業界の変革の鍵となるAIツールは多岐にわたり、その選定・比較には用途やセキュリティ、導入方法まで多角的な視点が求められるからです。
- 建設特化型LLM・業務系生成AI
- 議事録AI・現場コミュニケーションAI
- 安全・リスク管理専用AI
- 自律建機/現場ロボティクスAI
- グローバル建設管理プラットフォームのAI機能
建設特化型LLM・業務系生成AI
建設現場に本当にフィットするAI基盤なら、AKARI Construction LLM™やMicrosoft Copilotのように用途特化・セキュリティ強化製品の比較が不可欠です。
なぜなら、建設分野の業務はBIMや設計図など独自フォーマット・専門用語を多用し、かつ機密性の高い情報も扱うため、汎用AIでは満足できる精度・安全性が得られないケースが多いからです。
例えば、燈(あかり)株式会社『AKARI Construction LLM™』は、BIMデータや設計書など建設業務に特化したデータセットを学習材料とした国産大規模言語モデルで、「プライベートな社内環境で閉域運用できる」という強みがあります。
一方、Microsoft CopilotやAzure OpenAI Serviceは世界的な大企業にも選ばれており、OfficeやTeams等と組み合わせて安全な情報管理・ナレッジ共有環境を実現します。
つまり、機密文書や独自情報をAIで扱う場合は「セキュア環境」に重点を置く専用基盤が必須となり、一般的なクラウド型生成AIとは導入体制も大きく異なる選択肢となります。
主な違いが直感的に分かる比較表や実際の管理画面は、導入検討者にとって大変参考になります。
議事録AI・現場コミュニケーションAI
現場の議事録作成やコミュニケーションの効率化に関しては、Rimo VoiceなどのAI議事録自動化サービスが特に注目されています。
なぜなら、人手不足や作業負担の重さが課題となる現場では、「正確な議事録のタイムリーな作成」がプロジェクト遂行の質を左右するからです。
例えば、Rimo Voiceは日本語に最適化したAIエンジンを持ち、リアルタイムの高精度文字起こし、話者ごとの識別、会議自動録画・要約作成までをわずか数分で可能にします。
実際のUI画面やAI出力サンプルがあれば、どれだけ直感的に使えるかをイメージしやすく、他にも清水建設など大手導入事例も公開されているため、導入前の不安解消につながります。
さらに月額4,500円程度(年契約時はさらに割安)と、無料トライアルも充実していることから費用対効果の高さも導入企業が増える大きな理由です。
安全・リスク管理専用AI
労働災害ゼロを目指す現場では、「eYACHO安全AI」や「HAio」など、安全と健康リスク管理に特化したAIが現実解として機能しています。
従来、ヒヤリハットや経験則頼みのリスク評価しかできなかった作業場でも、AIは公的災害データベースや自社独自の蓄積情報をクロス解析し、「見逃しがちな危険」まで自動抽出できるようになりました。
例えばMetaMoJi「eYACHO安全AI」は、日常の危険予知活動(KY活動)で計画内容や作業プロセスをAIが自動点検し、想定災害と安全対策例をレコメンド。
また、平山「HAio」はウェアラブルデバイス等から取得したバイタルデータをAI分析し、「今まさに無理をしている作業員」をリアルタイムで発見・予防できる仕組みを持ちます。
こうした“人命を守るAI”の活用拡大は、建設現場の安全マネジメントを根本から変えるイノベーションです。
導入現場のビジュアル紹介やリアルなKPI計測例があると、他社導入の説得材料になります。
自律建機/現場ロボティクスAI
建設作業を「自動化」する最前線では、株式会社アラヤの自律重機AIや資材運搬ロボットなど、現場ロボティクスと画像認識AIの連携が急速に進化しています。
理由は、熟練作業員の高齢化・人手不足がますます深刻化し、遠隔操作や無人化施工のニーズが高まっているからです。
例えばアラヤは、ショベルカーの自律操縦AIや、作業現場向けの画像解析(人物・車両・障害物自動検知)をゼネコンと共同開発し、複雑な作業手順の自動生成や、現場事故の予防に活用されています。
多くの現場では、資材搬送ロボットの自律走行も導入され始めており、導入プロジェクトの様子やロボット稼働イメージは、未来的で多くの方にインパクトを与えます。
この分野はカスタム開発例が多いため、画像や動画の実装事例が理解促進に役立ちます。
グローバル建設管理プラットフォームのAI機能
海外発の建設管理プラットフォーム(OpenSpace、Procoreなど)は、AI活用による進捗管理・現場状況の可視化で、日本でも導入実績を伸ばしています。
なぜグローバル製品が注目されるのかというと、多拠点・多国籍プロジェクトでも統一品質で「現場の今」を即座に把握できる仕組みや、遠隔からの検査・モニタリング、膨大な書類の自動整理など、日本の大規模案件でもすぐメリットが出やすいからです。
OpenSpaceは360度カメラの画像をAIでマッピングし、まるで「現場のデジタルツイン」のような空間を画面上に再現します。
ProcoreやFieldwireも、タスク進捗や設計図との連携、コミュニケーション履歴の一元管理など各種AI機能を備えており、従来比で1日1時間以上の事務工数削減も珍しくありません。
日本市場では大手建設会社でも徐々に採用が進み、国内外で便利に使える点が評価されています。詳細なUIキャプチャや導入事例紹介は、他社担当者の大きな参考となるでしょう。
失敗しない建設AI導入・運用のポイントと、これから押さえるべき戦略
当セクションでは、建設業界でAIを導入・運用する際に押さえておきたい失敗しないポイントと、今後の成長に不可欠な中長期戦略について解説します。
なぜなら、建設AIへの期待が高まる一方で「途中で止まる」「つまずく」失敗も少なくなく、持続的な成果につなげるためには現場視点のリアルな知見と組織的な戦略の双方が不可欠だからです。
- よくあるつまずきと成功への“5つのポイント”
- “人とAI”の協働時代を見据えた社会技術的統合のすすめ
よくあるつまずきと成功への“5つのポイント”
建設現場のAI導入で失敗を回避し成果を出すには、「よくあるつまずき」を知り、5つの成功ポイントを押さえることが重要です。
その理由は、多くの企業で初期コストや効果の不透明さ、社内教育、業務の現場感覚とAIのギャップ、データの扱いなど、決まった壁につまずくケースが後を絶たないからです。
たとえば私がDX推進を担当したプロジェクトでも、導入初期は「結局どれだけ工数が減るのか?」というROI(費用対効果)の説明に苦労したり、現場サイドから「AIが勝手にやってくれるとは思えない」と根強い抵抗がありました。
その経験を通じ、現場で成功につながるポイントは次の5つに集約できます。
- 初期コストの妥当性:「オフィス業務(例:議事録自動作成)」など、比較的リスクが低くROIを早期に見せやすい領域から着手する
- ROI不透明リスクの解消:パイロットプロジェクトや短期導入でクイックウィンを提示し、成功事例を可視化
- 現場教育と心理的壁の克服:社内ハッカソンや業務横断の教育プログラムで、体感型のAI体験を多様な職種に提供(清水建設の社内AIハッカソン事例など)
- データ管理とセキュリティ:社外に出してはいけない現場写真や災害事例などは「ウォールドガーデン」(イントラネット限定)環境下で管理できるAIチャットボットを利用(鹿島建設のKajima ChatAIが代表例)
- 人的業務“現場を残す”戦略:完全自動化ではなく、人間の意思決定や現場判断を補う「ヒューマンインザループ」方式から始め、最初から“全部AI任せ”にしないこと
このように最初の一歩は、AIによる自動化ではなく「現場を補完し、安心して試せる仕掛けづくり」に重きを置くことが、次の展開を大きく左右します。
「AI=人間の代替」でなく「AI+人間の協力で成果を引き出す」ことを現場目線で徹底することが、長く使えるDXの土台作りと言えます。
“人とAI”の協働時代を見据えた社会技術的統合のすすめ
今後10年を見据えた建設AI活用戦略のカギは、“人とAIが協働する新しい社会技術的統合”にあります。
なぜなら、これまでの建設現場の自動化は、個別作業の効率化が中心でしたが、2040年を見据えた「i-Construction 2.0」(国土交通省公式資料)では、AIを活かした持続的成長のために、人・組織・プロセス全体の組み換えが求められているからです。
具体的には、最初は「ヒューマンインザループ(HITL)」──つまりAIが提案やチェックを行い、最後は人間が判断する協働モデルを採用し、データ品質や現場ノウハウを着実に蓄積していくことがポイントです。
また、鹿島建設や清水建設のように“ウォールドガーデン型(社内限定AI)”を整備し、自社だけのノウハウをデータ資産として積み上げていく内製化戦略が、業界の競争優位につながりつつあります。
一方、AI導入を一部の現場の頑張りだけに依存せず、経営層による全社的なデータガバナンスの構築や、現場の「失敗を許す文化」、AI検証プロジェクトの社内横展開など、組織をまたいだ改革も欠かせません(清水建設の全社AIアシスタント導入などが参考事例)。
このように、AIの進化を「自動化ツール」としてではなく、「人・現場・組織の連携を底上げする社会的インフラ」と捉え、着実なデータ戦略や現場教育と一体で進めることで、激変する競争環境をリードする“真のAI建設カンパニー”が生まれます。
国内外の動向や最新ツールも整理していますので、より具体的なソリューション例は「業務効率化AIの成功事例・比較ガイド」も参考にしてみてください。
AIが変える建設業界の未来像と、これからのツール選びの指針
当セクションでは、「AIが変える建設業界の未来像」と、それを見据えた「これからのAIツール選びの指針」について解説します。
建設業界では、AI導入の基盤を整える政府の政策と、現場に根ざしたイノベーションの両輪が急速に進行しており、今後は単なるツール導入ではなくエコシステム思考が重要となるからです。
- AI統合エコシステムの時代へ──単なるツール導入から価値創出へ
AI統合エコシステムの時代へ──単なるツール導入から価値創出へ
今、建設業界は「個別ツールの分散導入」から「全工程を貫くAI統合エコシステム」への本格的な転換期に突入しています。
なぜなら、政府主導の「i-Construction 2.0」や「AI開発支援プラットフォーム」など、データの共有・活用を前提にした政策インフラが急速に整備されつつあるからです。
たとえば、大手ゼネコンの間では自社専用AIチャットボットやセキュアなAI検索アシスタントが普及し、現場〜オフィスのドキュメント管理、危険予知、品質管理…とパーツごとにAI化が進行。さらに最近は、これらを社内独自のデータベースやBIM(3D設計データ)、IoTセンサーなど横断的に連携し、“見えないインフラ”としてAIがプロジェクト全体を統べる仕組み=エコシステム化へと発展しています。
今後10年で目指すべき姿は、2040年の「3割省人化」「AI自動化現場」の実現です。これは業界ビジョンとして明確なロードマップが描かれており、工程ごとに“とりあえずAI”という時代は終わり、御社の経営資源・現場課題・守るべきセキュリティレベルに応じて、シームレスなデータ連携とプロプライエタリなAI活用を設計することが生存戦略になります。
「ツール選び」は“機能・価格”基準から、“統合・相互運用性・データ主権”基準へと移行します。つまり「手軽な議事録AI」「オフィス効率化AI」で安全な体験を積み、その後オリジナルの社内知見を学習させて、現場固有の課題──施工管理・安全・品質・コスト推定・リスク管理など──を横断支援するAIプラットフォームの構築がカギを握る時代です。
【図1:2040年ビジョンに向けた日本の建設DX公式ロードマップ】【図2:今後10年のAI技術進化と導入フェーズ別トレンド予測グラフ】
こうした変化の中で、最適なAIツールを選ぶポイントや具体的な選定フロー、実際に各フェーズで必要となるソリューションの例などは、以下の関連記事でも実践的にまとめています。
→ AIによる業務効率化の成功事例とソリューション徹底比較|中小企業から大企業・自治体まで導入のコツを解説
つまり、単なるAI導入で小さな効率化や省人化を目指す段階から、AIを軸に「既存データの価値を最大化」「人間中心の意思決定を進化」させる、真の意味での“建設AIエコシステム”時代の到来が始まっています。
まとめ
本記事では、政府による「i-Construction 2.0」戦略や業界全体のAI導入トレンド、先進ゼネコンによる現場での具体的活用事例を多角的に解説しました。
AIは単なる効率化の枠を超え、建設現場や管理業務の革新、人材・技術承継の新たなモデルとして進化しつつあります。
今こそ、時代をリードするデジタルツールと先端知識を活用し、次の一歩を踏み出す好機です。
現場や会議の生産性向上を体感したい方は、録音からAI要約・議事録自動化まで対応する最新AIレコーダー「PLAUD NOTE」や、業務の加速に最適なAI仕事術本「生成AI 最速仕事術」をぜひご活用ください。