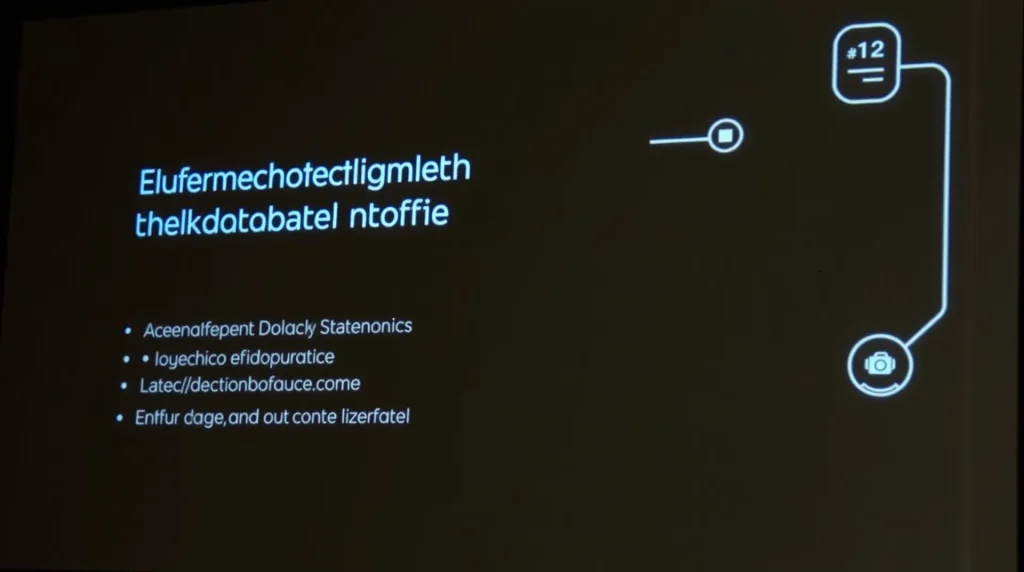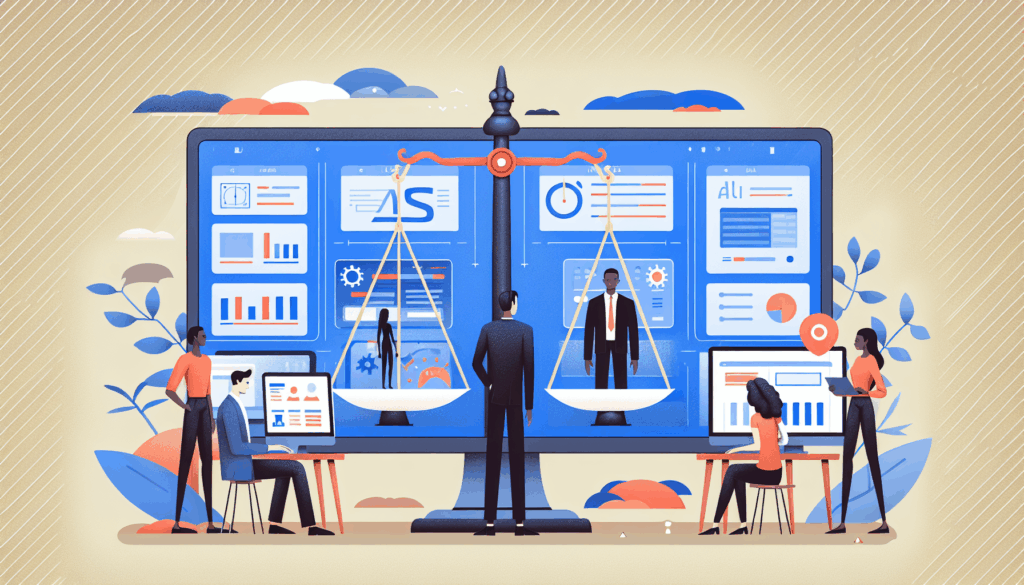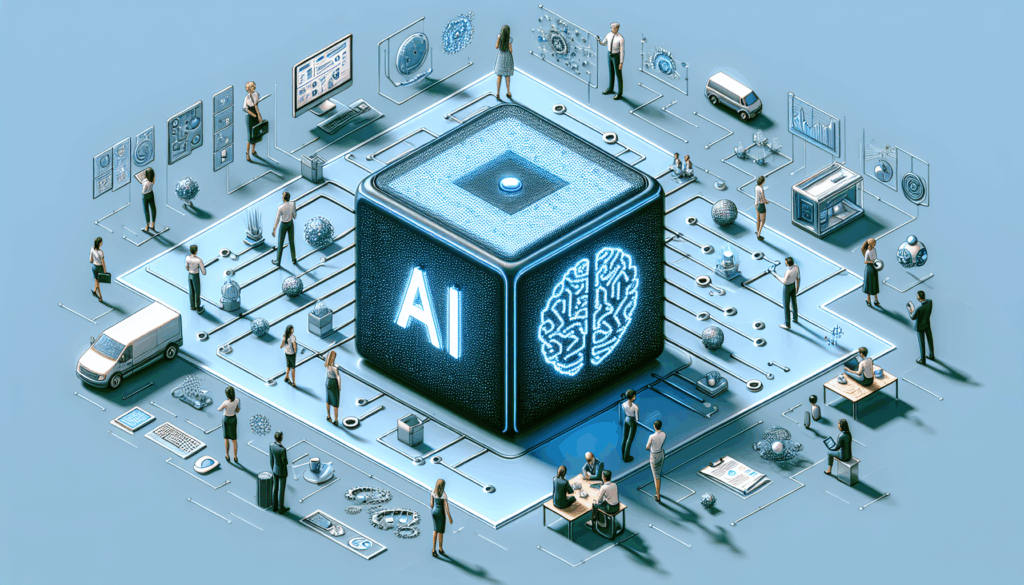(最終更新日: 2025年07月11日)
「資料作りにいつも時間を取られてしまう」「AIに興味はあるけれど、難しそうで手を出せない…」そんなお悩みはありませんか?
本記事では、注目のAIプレゼン資料作成ツール「Tome」を初心者目線で徹底解説。基本的な使い方はもちろん、他の人気ツールとの違いや料金プランまで、知りたいポイントを分かりやすくまとめました。
一度コツをつかめば、作業時間を大幅に短縮し、あなたの伝えたい内容をより魅力的に届けることができます。
最新情報を踏まえたガイドで、忙しいビジネスパーソンやマーケターの働き方がきっと変わります。
Tomeとは?混同しやすいブランドと本質的特徴を解説
当セクションでは、AIプレゼンテーションツール「Tome(tome.app)」とは何か、その本質的な特徴と混同しやすい他ブランドとの違いについて詳しく解説します。
なぜなら、「Tome」という名称はさまざまなサービスで使われており、公式サイトの特定や機能理解で戸惑う人が非常に多いからです。
- 「Tome」って何?どんなツールなのか一言で分かる
- なぜ「Tome」というワードはややこしい?ブランド混同の背景を整理
「Tome」って何?どんなツールなのか一言で分かる
Tome(tome.app)は「AIを活用した次世代型ストーリーテリングプレゼンテーション作成ツール」です。
その最大の特徴は、PowerPointなど従来のスライドツールが「静的な資料」を作るのに対し、TomeはAI(GPT-3やDALL-E 2)によって、物語性のある動的な“インタラクティブ資料”をわずか数クリックで自動生成できる点です。
たとえばユーザーが「新サービスのビジョンを伝える資料を作りたい」と一文入力するだけで、AIが物語構成・説明文・最適な画像までまとめて提案します。その後も、ページごとに動画ナレーションや外部Webの埋め込みができるため、ただ読むだけでなく“体験してもらう”資料が作成可能です。
こうした生成型ストーリーテリング形式は、ビジネスのプレゼンや教育分野、クリエイターのポートフォリオなど、既存のスライド形式に限界を感じている方にとって大きな変革となります。ただし、「Tome」と検索した際には似た名前の他サービス(tome.com等)が上位に並ぶため、本記事では改めて「tome.app=AIストーリーテリング・プレゼンである」と強調します。
なぜ「Tome」というワードはややこしい?ブランド混同の背景を整理
「Tome」というワードは、実は世界中で複数の異なるサービス・企業に使われており、検索や利用時に混同しやすいことが最大の落とし穴です。
例えば、“tome.com”はAIによる契約書分析ツール、さらに“tomeapp.com”は宗教体験用アプリケーション、“tomedes.com”は翻訳サービス会社など、まったく分野の違うサービスも多数存在しています。
実際に「Tomeの使い方が知りたい」と調べた読者が、公式サポートへ問い合わせようとメールしたところ、書類AIではなく宗教アプリ側のサポート窓口(care@tomeapp.com)に送信してしまった…という事例も珍しくありません。
本記事では、AIプレゼン・ストーリーテリングツールとしての「tome.app」だけにフォーカスします。公式サイト(https://tome.app/)以外で同名サービスを見かけても混乱しないよう、必ずURLや機能を確認するようにしましょう。詳細なサービス比較や注意点は、こちらのAIプレゼン作成ツール徹底比較も参考にしてください。

Tomeの主な機能とできること:スライド作成を超えた進化系AIツール
当セクションでは、Tomeが提供する主な機能と、その革新的な使い方について詳しく解説します。
なぜなら、Tomeは「AIでプレゼン資料を作る」だけでなく、従来の常識を覆すインタラクティブなストーリーテリング体験まで実現できる、全く新しいAIツールだからです。
- AI自動生成でできること:文章・構成・画像すべて丸投げOK
- インタラクティブ&マルチメディア:従来スライドではできない表現力
- デザイン・編集のしやすさ:誰でも迷わずプロ級レイアウト
AI自動生成でできること:文章・構成・画像すべて丸投げOK
Tome最大の特徴は、「タイトル・構成・文章・画像生成」まで、1行のプロンプトだけでAIがすべて自動生成してくれる点です。
なぜなら、GPT-3とDALL-E 2など、最新の生成AIが連携し、ユーザーの短い指示文からページ全体の骨組みや内容まで一括で用意してくれるからです。
たとえば「新製品の紹介プレゼンを作成」と入力するだけで、8ページ分程度の構成案・物語風の説明文・プレゼン用のオーダーメイド画像が数秒で完成します。
さらに、Tomeでは「もっと短く・カジュアルに」ボタン1つで文章を自動言い換えしたり、テーマカラーやフォント、一括で全ページまとめて変更することが可能です。
従来のスライドツールが「図や表、文章を自分で入力して整形する手間」に終始していたのに対し、Tomeなら発想と要望を伝えるだけで、物語のような説得力ある資料を誰でも作成できます。
インタラクティブ&マルチメディア:従来スライドではできない表現力
Tomeはスライドの枠を超え、ライブWeb埋め込みや動画、3Dコンテンツなどインタラクティブな表現を簡単に追加できます。
理由は、FigmaやYouTube、外部Webページをそのままタイムリーに埋め込めるため、静止画像やスクリーンショットでは伝わりにくい動きをリアルタイムで披露できるからです。
私が実際にTomeで社内向け資料を作った際、各ページに自分のビデオナレーションを数分ずつ挿入しました。
すると「ただ資料を配るだけ」では反応が薄かった同僚も、自由なタイミングで視聴できる解説動画と動きのあるグラフやWebダッシュボードに夢中になってくれました。
表・GIFアニメ・3Dビジュアルまでもワンクリックでタイル追加できるため、製品デモや教育現場でも、「体感的に伝わる」資料表現が可能となります。
デザイン・編集のしやすさ:誰でも迷わずプロ級レイアウト
Tomeは「タイル型レイアウト」と直感編集により、デザイン初心者でも自信をもって資料を作れます。
なぜなら、要素の追加・並び替え・サイズ調整がドラッグ&ドロップだけで完結し、スマホやタブレットでも崩れにくいレスポンシブ設計が自動適用されるからです。
たとえば、タイルを入れ替えるだけで複雑なデザイン変更も一発。
外出先ではiOSアプリで手直し、帰宅後はPCですぐ続きを編集というデバイス間同期も地味に便利です。
また、チームメンバーと同時編集や、閲覧・編集権限をきめ細かく設定して安全に共同作業できるため、現代のリモートワークにも最適です。
【実践で分かる】Tomeの使い方ステップガイド:登録から資料完成まで
このセクションでは、Tome(tome.app)を実際に使いこなすためのステップを、登録からプレゼン資料の完成・共有まで体系的に解説します。
なぜなら、Tomeは一見シンプルな操作性の反面、AI自動生成機能や独自の編集インターフェース、発表・共有方法に独特な特徴があるため、「どこから手を付ければいいか不安」という初学者が多いからです。
- アカウント作成と初期設定:最初のハードルを徹底解説
- AI自動生成 or 手動カスタム ― 選べる2つの作成アプローチ
- 編集・カスタマイズ・機能追加のイロハ
- 発表・共有・エクスポート―知っておきたい実務での使い方
アカウント作成と初期設定:最初のハードルを徹底解説
Tomeの導入は「tome.app」でのアカウント作成から始まるため、まずこの最初の壁をクリアするのが大切です。
Tomeはプレゼン作成ツールの中でも、アカウント登録後すぐに500AIクレジットがもらえて主要AI機能を体験できるお得な設計になっています。
公式サイト(tome.app)へアクセスし、メールアドレス登録→認証メール内のリンククリック→ワークスペース立ち上げと、手順自体はシンプルですが、最初にダッシュボード画面の構成や、AIクレジットの残高表示、サイドメニューの場所を知っておくと後の操作が格段に楽です。
ビギナー時代、私はこのダッシュボードのアイコンや「Create」ボタンの意味が分からず、最初の一歩を踏み出すまでに思いの外時間がかかりました。
一度「ここだけ見ておけば大丈夫!」と把握できれば、次からは迷うことなく本格的な資料作成に移行できます。

AI自動生成 or 手動カスタム ― 選べる2つの作成アプローチ
Tomeの資料作成は、「AI自動生成」か「テンプレートを使った手動編集」の2つの方式から好みに合わせて始められるのが最大の魅力です。
AI自動生成を使えば、「子ども向けの地球温暖化を説明する資料を作成」のようにテーマ・対象読者・用途を文章で指定するだけで、アウトライン→全ページ生成まで一気に自動化。
一方、手動カスタムの場合は、真っ白なキャンバスまたはテンプレートを選び、「タイル」と呼ばれるパーツ(テキスト、画像、グラフ、埋め込み動画など)を自由に積み重ねていく感覚で自分だけのストーリー構成がつくれます。
私自身、「AI出力が想像とズレたとき」には、一度途中保存してから手作業で微調整したり、不要なページだけ削除→必要な情報を追加することで、柔軟にイメージ通りのアウトプットに仕上げることができました。AIと手作業、それぞれの“いいとこ取り”がしやすいのがTomeの長所と言えます。

編集・カスタマイズ・機能追加のイロハ
作成した資料は、テキスト・画像の差し替えに加え、グラフ、動画、埋め込みコンテンツ追加など多彩な編集が「後から」自在に可能です。
Tomeのエディタは、ページ上の要素をクリックすればその場で編集が始まり、AIによる文章のトーン変更も右クリック一発。
さらに「タイル」を追加するだけで、Figmaのデザイン・表・GIF・YouTube動画・インタラクティブな数値グラフまでもドラッグ&ドロップ感覚で実装できます。
営業用ピッチ資料の制作現場で活用した時は、AI生成された見出しと文章をさくっと差し替え、提案先ごとにロゴや色をアレンジしつつ、必要に応じ動画やグラフを追加――この“時短感”はPPTでは到底真似できない体験でした。

発表・共有・エクスポート―知っておきたい実務での使い方
Tomeは「Webでそのまま発表&共有」が最適解ですが、PPTXエクスポート不可・PDFエクスポートは有料限定という制約を事前に把握しておくことが肝心です。
ライブプレゼン機能を使えば、PowerPointのようにスライド送りしつつオンラインで発表が可能で、さらに共有リンクで「閲覧のみ/編集可」の権限を細かく割り振れます。
私が過去にやらかした失敗例として、「リンク生成時に“編集可”のまま共有してしまい、取引先がうっかり内容を書き換えてしまった…」というケースも。共有時はアクセス権限を必ず再チェックしましょう。
エクスポートに関しては、無料ユーザーのままではWeb共有のみ、PDF出力や閲覧データ分析などはProプラン以降が必要です。要件次第で事前にプランを検討すると、後で慌てずに済みます。

Tomeの料金プランとAIクレジット制のリアル:どこまで無料でできる?
当セクションでは、Tomeの料金プランやAIクレジット制の仕組み、無料でどこまで使えるのか、そのリアルな体験と注意点まで詳しく解説します。
なぜなら、「AIツールだから無料でもバリバリ使える」と考える方が少なくなく、実際の使用感やコスト構造を知らずに使い始めてしまい、思わぬ制限に直面する人が多いからです。
- Tomeの料金体系と使えるAI機能範囲を総チェック
- 「無料でどこまでできる?」Tomeの試用体験と注意点
- 最新の価格情報の調べ方・注意点
Tomeの料金体系と使えるAI機能範囲を総チェック
Tomeの無料プランは一見大盤振る舞いに見えるものの、AI機能の本格的な継続利用には有料プラン(Pro)への加入が必須です。
なぜなら、無料プランで付与されるAIクレジット(初回500)は、実際にAIによるプレゼン資料を1~2件作成しただけでほぼ消費しきってしまうからです。
例えば、「AIにおまかせ」でプレゼンを12ページ作成すると、体感的に400クレジット以上が一気に減り、テキストの再生成や画像変更を行うごとに追加でクレジットを消費します。
PDFへのエクスポートやブランドロゴ追加、閲覧者分析といった高度な機能もPro($8〜20/月)以上の契約でしか利用できず、無料枠はあくまで「TomeのAI体験版」という位置付けだと理解しておくことが大切です。
| 項目 | Free / Basic | Pro / Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 無料 | $8~$20程度 | 要問い合わせ |
| AIクレジット | 500(初回のみ) | 無制限 | 無制限 |
| PDFエクスポート | 不可 | 可能 | 可能 |
| ブランドカスタム | 不可 | 可能 | 可能 |
| 閲覧者分析 | 不可 | 可能 | 可能 |
無料の範囲でTomeを最大限に活用したい場合は、手動編集やテンプレートだけを使うなど工夫が求められます。なお、AIクレジットとプラン仕様の最新状況はTome公式サイトで必ずご確認ください。

「無料でどこまでできる?」Tomeの試用体験と注意点
無料プランは、基本的に「体験版」と捉えておくのが現実的です。
なぜなら、AIによる自動プレゼン資料生成を一度実行しただけで、数百ものクレジットが消費されてしまうため、想像以上に「あともう1件・・・」が通用しない設計だからです。
私自身、ワクワクしながら「次は社内用」「今度はクライアント向け」と2件目の生成に挑戦したものの、途中で「クレジット残量不足」と警告され、編集や生成が止まってしまった経験があります。
クレジット切れ後はAI機能へのアクセスが完全に制限され、画面上には「Proへアップグレード」の案内が出る仕組みだったので、本気で運用するなら早めに有料化を検討する方がストレスなく効率的です。
最新の価格情報の調べ方・注意点
Tomeは料金体系のテストや地域ごとの価格差が頻繁にあるため、正確な最新情報は必ず公式サイトで直接確認することをおすすめします。
ネット記事やSNSでは過去の金額がそのまま流通しがちで、「聞いていた価格と違う」といった混乱もしばしば起きています。
チーム利用・商用利用を検討している場合は、公式サイトの「Enterprise見積もり依頼」フォームを使い、具体的な要望とともに問い合わせることで、企業規模や用途にあった提案をもらえます。
Tomeの公式サイトはこちらからアクセスできるので、気になる方はまず覗いてみると安心です。
Tomeと他AIプレゼンツール比較:GammaやSlidesgoとの違いは?
当セクションでは、Tomeと主要なAIプレゼンテーションツール(特にGammaやSlidesgo)との違いを分かりやすく比較し、選び方の指針を解説します。
AIプレゼン作成ツールは急速に増えていますが、選択ミスをすると「想定したファイル形式で渡せない」「インタラクティブ要素が実現できない」といったトラブルにつながりやすいからです。
- Tomeの強み・弱みを他ツールと分かりやすく対比
- Tomeが向いている人・向いていない人を明確化
Tomeの強み・弱みを他ツールと分かりやすく対比
結論から言うと、Tomeは「Webネイティブな物語型プレゼン」に特化した唯一無二のツールであり、従来型の「PPTXファイル化による業務効率化」とは一線を画しています。
なぜなら、TomeはAIによるストーリーテリングの自動生成、動画ナレーション、Web埋め込みなど“インタラクティブ性”に極振りしており、PowerPoint形式へのエクスポートは「意図的に」できない設計だからです。
たとえば、GammaやSlidesgoは「AIで瞬時にスライドを起こし、それをそのままPPTとして渡す」といった“従来フローの高速化”が可能ですが、TomeはWebリンクで見せるインタラクティブな表現・ストーリー進行・非同期コミュニケーション(動画など)で圧倒的な現代型体験を実現します。その代償として、無料枠でのAI利用回数制限や、「会社の上司にPPTで渡したい人」は不便を感じるでしょう。
まとめると、「新世代プレゼン(Web公開・動画解説・動的コンテンツ)」を武器にしたい人ならTomeは他の追随を許さない独自性があります。一方、「アウトプットはPPT一択」「無料で何度も作りたい」「日本語対応が必須」というニーズならGammaやPresentations.ai、Slidesgoも含めて冷静に比較すべきです。
- 主要AIプレゼンツール機能比較表
以下は2025年7月時点での代表的な違いです(公式サイト・関連記事も参考):
| 機能 | Tome | Gamma | Slidesgo |
|---|---|---|---|
| AIテキスト/画像生成 | ○ | ○ | ○ |
| PPT(X)エクスポート | ☓ | ○ | ○ |
| PDFエクスポート | Pro限定 | ○ | ○ |
| Web埋め込み | ◎(Figma, Webなど) | ○ | △ |
| 動画ナレーション | ◎(各ページごと) | △ | ☓ |
| 無料枠(主要AI機能) | 500回分(初回のみ) | クレジット制 | 月3回まで |
| 言語対応 | 英語中心 | 複数言語 | 日本語◎ |
このように、表現力や共有性重視ならTomeはピッタリですが、オフライン必須やファイル管理中心のビジネス用途にはGammaやSlidesgoの汎用性が目立ちます。さらに詳細は「Gammaの使い方ガイド」もご覧ください。

Tomeが向いている人・向いていない人を明確化
もしあなたが「新しいWeb体験の提案」や「短時間でクリエイティブなストーリーを形にしたい」と考えるなら、Tomeこそ最適です。
なぜなら、Tomeはシナリオ型生成、ビジュアル一貫性、リアルタイム埋め込み・動画解説など“物語性”と創造性を短時間で両立できるからです。
例えば、スタートアップのピッチやデザイン提案、社外への先進的企画プレゼンではTomeの「ダイナミックで動的」「URL共有ですぐ見せられる」といった特性が活きます。逆に、「営業資料はPPTで提出しなければならない」「会社規定で日本語対応とファイル保存が必須」という環境ではGammaやSlidesgoのようなエクスポート&多言語対応型が無難です。
要するに、Web時代らしい提案型や教育・クリエイティブ用途にはTome、業務の伝統的ワークフローや保守性重視なら他ツール、明快な棲み分けが生まれます。目的に応じ、自分の業務環境・プレゼン相手を想像しながら使い分けましょう。
- 【Tomeが向いている例】
・デザイン提案・ポートフォリオ
・教育用のインタラクティブ教材
・社外への新規事業プレゼン
・非同期型の動画付き進行 - 【Tomeが不向きな例】
・営業でPPT配布必須な大手企業
・完全な日本語運用とオフライン渡し前提
・AI生成無制限/無料枠を重視
よくある疑問・トラブル対策Q&A:Tome使いこなしのポイント解説
当セクションでは、Tome活用時によく寄せられる「実際の制約」や「つまずきやすいトラブル」、そしてそれらの解消法や使い分けのコツをQ&A形式で詳しく解説します。
なぜなら、Tomeは従来のプレゼン作成ソフトとは思想も仕組みも大きく異なるため、初めての方ほど「PPT出力は?」「無料・有料の違いは?」「日本語で大丈夫?」と悩みや迷いが生まれやすいからです。
- パワーポイントでTomeを使うには?
- Tomeで画像を生成するには?
- Tomeは無料でどこまで使える?
- Tomeの日本語対応状況は?
パワーポイントでTomeを使うには?
結論から言えば、TomeではPowerPoint(PPT/PPTX)ファイルへの直接エクスポートはできません。
理由はTome自体が「PowerPointの便利版」ではなく、自社開発のインタラクティブなストーリーテリングWebフォーマットを推進するため、という明確な戦略に基づくものです。
例えば「会議でPPT必須」「社内規定でPPT形式指定」という企業環境の方は、Tomeで作った内容をそのままPowerPointファイルで出力できると思い込み、あとから「あれ?エクスポート項目がない」と戸惑うケースが多いです。
この点は公式ヘルプでも繰り返し告知されています(公式Tomeヘルプ)。どうしてもPowerPoint運用が必須の場合は、TomeでPDFを出力(Pro限定)→他ツールでPPTへ変換、もしくは「Gamma」などPPT対応AIプレゼン作成ツールを選びましょう。
Tomeで画像を生成するには?
Tomeではページ編集画面の「AI画像生成」を使えば、指示するだけでDALL-E 2技術による独自のイメージを即時作成・挿入できます。
その方法は簡単で「バナー用のポップな未来感あるイラスト」「女性の笑顔・明るい背景」など、希望イメージをテキストで指示するだけです。
例えば、自作資料の表紙を一新したい時にAI生成ボタンから数ワードで指示すれば、既存ストックフォトに頼らずオリジナルアートがページに自動配置されます。
ビジュアル面での独自性やアイキャッチ強化を狙うなら、この「画像生成AI」は必須機能です。(DALL-E 2技術の詳細や他AI画像比較はこちらの解説記事もどうぞ)

Tomeは無料でどこまで使える?
Tomeの無料プランでは、500AIクレジット分だけ、AIによる自動生成・書き換え・画像生成の全機能を体験可能です。
ただしこのクレジットは新規登録時に一度きりで付与され、AIで数回本格的なプレゼン(例:12Pで400クレジット以上消費)を試作すれば、短期間で使い切るケースがほとんどです。
その後は手動の編集やテンプレートの閲覧だけ続けられますが、「生成AI活用による本格運用」にはProプラン(有料)への移行が推奨されています。
「まずは無料でAI自動化の威力を体感→気に入ったら本格採用」という流れになっている点を念頭に置きましょう。
Tomeの日本語対応状況は?
2025年7月現在、Tomeの画面インターフェースは英語のみ対応ですが、日本語プロンプト(AIへの指示文)もある程度は通用します。
たとえば「SEOについて詳細な資料を作って」と日本語で入力しても、AIが内容を認識し日本語スライドを生成しますが、ページによっては英語が混ざったり、レイアウトが崩れる場合も見受けられます。
公式として完全日本語UIや文章制御はまだ実装されていません。日本語で高精度なAI資料を作りたい場合は、同じくAIプレゼン系の比較解説記事や画像生成ノウハウ集も参考にしてください。
要点は「日本語も一定対応は可能だが、公式は英語メインなので、実用には注意」―これが現実的な立ち位置です。
まとめ
Tomeの本質は、AIを活用した新しいストーリーテリング体験にあります。
従来のスライド作成にとどまらず、直感的な編集やインタラクティブな要素、強力なコラボ機能によって、あなたのアイデアを短時間で魅力的に表現できます。
変化の速いデジタル時代――ここで学んだ知識を活かし、どんな場面でもストーリーで人を魅了する第一歩を踏み出しましょう。
さらに仕事効率化やAI活用を極めたい方は、「生成AI 最速仕事術」がおすすめです。AI活用術やツール選びで迷う方も、まずはこの一冊を手にして次のアクションを起こしましょう。