(最終更新日: 2025年11月11日)
AIツール導入で「社内データは漏れない?」「法務や監査に耐えられる?」と不安になっていませんか。
とくにDifyは便利な一方で、クラウドか自社運用かで守り方が大きく変わります。
本記事は、2025年最新の仕組みと公開情報を整理し、リスクの見える化と実務での対策をやさしく解説します。
データの保管場所、利用ログ、外部AIへの送信や学習への使われ方まで、チェックすべき要点を具体化します。
クラウド版の安心ポイントと注意点、自社サーバーで動かす場合の設計のコツ、大企業向けの管理機能まで比較します。
さらに、共通の落とし穴やオープンソースならではのセキュリティの弱点への向き合い方もカバー。
導入可否の判断から社内説明の材料づくりまで、この一記事で最適解に近づけるよう、専門家の視点でご案内します。
Difyのセキュリティ全体像|なぜ導入形態で変わるのか
当セクションでは、Difyのセキュリティ全体像と、導入形態によってプロファイルがどう変化するかを説明します。
なぜなら、Cloud、Self-Hosted、Enterpriseで「誰がどこまで責任を持つか」が異なり、ガバナンスや監査対応、リスク許容度に直結するからです。
- Difyの3つの提供形態とそれぞれの特徴
- クラウドVSセルフホスト:最大の違いは『責任の主体』
Difyの3つの提供形態とそれぞれの特徴
DifyのセキュリティはCloud、Self-Hosted、Enterpriseの三層で設計が分かれ、鍵は「誰がセキュリティ責任を負うか」に尽きます。
この違いが、データ主権、コンプライアンスの入手可能性、運用負荷の配分を決めるからです。
例えばCloudはベンダーがSOC 2やISO 27001に基づく統制を維持し、ユーザーは迅速な導入と監査資料の入手を見込めます(参考: Dify Docs: Get Compliance Report)。
一方セルフホストは自社で暗号化やパッチ適用、ネットワーク分離を担い、EnterpriseはSSOや包括的監査ログなど大企業向け統制が追加されます(参考: Dify Docs: Introduction、Dify Blog: Azure Marketplace)。
したがって、要件定義では機能比較より先に「責任分界点」を図で可視化して合意することが意思決定を速めます。
| 項目 | Cloud | Self-Hosted | Enterprise |
|---|---|---|---|
| デプロイ主体 | ベンダー管理SaaS | 自社インフラ | 自社VPC/オンプレ or マネージド |
| セキュリティ責任の主語 | ベンダー中心 | 自社中心 | 自社中心+製品強化 |
| コンプライアンス | SOC 2/ISO 27001(プランにより資料提供) | 自社の枠組みで対応 | エンタープライズ契約で対応 |
| ID連携/SSO | 標準プランは限定的 | 標準はなし | SAML/OIDC対応 |
| 監査ログ | 運用ログ中心 | 自社で実装/統合 | 包括的監査ログ |
| データ主権 | 委託 | 完全保持 | 完全保持(私設環境時) |
| 運用難易度 | 低 | 高 | 中〜高(機能支援あり) |
主な参考情報:
関連情報の整理には、料金やプラン差の要点も合わせて確認すると効率的です(参考: Difyの料金プランを徹底比較)。
クラウドVSセルフホスト:最大の違いは『責任の主体』
クラウドとセルフホストの最大の違いは、インフラとデータ保護の責任主体がベンダーか自社かという一点です。
責任の所在が異なると、インシデント対応フローや監査証跡、予算配分まで設計が変わるからです。
私がSaaSのPMとしてSOC 2 Type II対応やペネトレーションテスト受審をリードした際、権限境界が曖昧な領域ほど監査指摘とリスク受容の調整に時間を要しました。
DifyでもCloudはSOC 2やISOの枠組みを活用できる一方、Self-HostedはHTTPS強制やログ保護、パッチ適用などのベストプラクティスを自社で整備する必要があります(参考: Dify Docs: Introduction、Dify Docs: Get Compliance Report)。
またCloudはデータレジデンシーや基盤クラウドの情報が公開されていない点があり、契約前の確認事項になります(参考: Dify Trust Center)。
組織のルールが厳格ならEnterprise、迅速な検証はCloud、データ主権最優先ならSelf-Hostedから検討を始めるのが現実的です。
生成AI導入時の横断的なリスク対策は、併せてこちらも参照すると設計が洗練されます(参考: 生成AIのセキュリティ完全解説)。
Dify Cloud(SaaS型)のセキュリティ実態と注意点
当セクションでは、Dify Cloud(SaaS型)のセキュリティ実態と導入時の注意点を説明します。
なぜなら、公開情報だけでは判断しづらい領域があり、責任分界点や取得可能なエビデンスの違いが導入可否を左右するからです。
- SOC2・ISO27001取得で担保される範囲
- 重大な不透明点:データ保存先・暗号化ポリシーの実態
- 機能拡張のサードパーティプラグイン利用リスク
- プラン別セキュリティ機能差と30日ログ制限の落とし穴
SOC2・ISO27001取得で担保される範囲
第三者認証は「安心材料」だが、担保範囲とレポート入手性の差を理解して選ぶことが重要です。
DifyはSOC 2 Type I/IIとISO 27001:2022に対応し、組織的な管理策の設計と運用有効性が第三者に評価されています(参考: Dify Trust Center、参考: Get Compliance Report – Dify Docs)。
ただし、レポートの提供範囲はプランで分かれ、Sandboxは非提供、ProfessionalはSOC 2 Type I、EnterpriseでSOC 2 Type IIとISO 27001にアクセス可能という整理です(参考: Get Compliance Report – Dify Docs)。
監査対応では「レポート入手のしやすさ」も実務上の要点で、契約前に最新レポートの日付・監査期間・スコープ記載の有無を確認し、必要に応じてDPAや補足エビデンスの提示を依頼すると評価がスムーズです。
費用・機能の全体像は別途プラン比較で押さえ、「どのプランでどの証跡にアクセスできるか」を意思決定テーブルに落とし込みましょう(参考: Plans & Pricing – Dify、関連記事: 【2025年最新】Difyの料金プランを徹底比較)。
| プラン | エビデンス入手範囲 | 補足 |
|---|---|---|
| Sandbox | なし | PoC限定を推奨 |
| Professional | SOC 2 Type I | 基本的なベンダー監査に対応 |
| Team | 公開情報に明記なし | 要問い合わせ |
| Enterprise | SOC 2 Type II / ISO 27001 | 厳格な内部統制向け |
重大な不透明点:データ保存先・暗号化ポリシーの実態
データレジデンシーや暗号化仕様の未開示は、GDPRなど厳格な規制下では重大な検討課題です。
Difyの公開情報では、保存リージョン、基盤クラウド、転送中・保存時の暗号化仕様が明確でなく、データ主権要件や越境移転の適法性評価が難しくなります(参考: Dify Trust Center)。
企業法務の観点では、契約前にDPA、SCCの適用可否、サブプロセッサ一覧、暗号化アルゴリズムと鍵管理方式、監査証跡の保持期間を文書で取り寄せることが必須です(参考: Get Compliance Report – Dify Docs)。
プロジェクトマネージャー視点では、要件定義段階で「許容リージョン」「求める暗号化強度」「ログ保持期間」を非機能要件に明文化し、ベンダー回答を適合・条件付き適合・非適合で判定するのが有効です。
もし回答が不十分なら、機密度の高いワークロードはセルフホストやEnterpriseのVPC/オンプレ配備へセグメントする選択肢を検討します(関連記事: 生成AIのセキュリティ完全解説)。
この不透明性を残したままの本番投入は避け、必ず書面回答と契約条項で補完してから進めるのが安全です。
機能拡張のサードパーティプラグイン利用リスク
マーケットプレイスのプラグインは便利ですが、データフローが増える分だけ漏えいリスクも増加します。
Difyはプラグイン公開時にプライバシーポリシーの提示や収集データの明示を求めていますが、各プラグインの実運用をDify本体が常時保証するわけではありません(参考: Plugin Privacy Protection Guidelines)。
導入側は「何が誰に送られるか」のデータマッピング、第三者提供の有無、保持期間と削除ポリシー、脆弱性対応SLAをプラグインごとに精査する責任があります。
実務では、本番ワークスペースに入れる前に検証環境でネットワークトレースを行い、外部送信先・送信内容・失敗時リトライの挙動まで確認すると安全度が上がります。
社内規程がある場合は「許可プラグインリスト」を運用し、年次で更新・棚卸しするルールをセットしましょう。
プラン別セキュリティ機能差と30日ログ制限の落とし穴
Sandboxの「ログ30日」は本番用途では致命的で、少なくともProfessional以上が必須です。
セキュリティ事故の発見は数週間〜数ヶ月遅延することが多く、30日でログが消えると原因追跡や是正措置の根拠が残りません(参考: Logs and Annotation – Dify Docs)。
Professional以上ならログ無制限のため、監査・再現性・モデル応答のトラブルシュートに必要な証跡を維持できます(参考: Plans & Pricing – Dify)。
筆者は過去にSaaS本番で「調査開始が発生日+45日」だった案件に遭遇し、無料枠の短期保持が災いして決定的証跡が欠落し、是正報告の確度が落ちた経験があります。
部門スケールの利用でも、Slack連携やAPI利用が増えるほど監査要件は上がるため、Team/EnterpriseでSSOや包括的監査ログの有無も検討しましょう(関連記事: AIによるログ解析の最新動向)。
総じて、PoCはSandbox、本番はProfessional以上、厳格統制はEnterpriseという線引きが現実解です。
セルフホスト(Community/Enterprise)版のセキュリティ設計ポイント
当セクションでは、Difyのセルフホスト(Community/Enterprise)版を安全に導入・運用するためのセキュリティ設計ポイントを体系的に解説します。
理由は、セルフホストはデータ主権を最大化できる一方で、インフラからアプリまでのセキュリティ責任がすべて利用者側に移転し、公式ドキュメントの示す情報だけでは本番要件を満たしにくいからです。
- 「全データ主権」と運用責任のすべて
- 公式ドキュメントの限界と“落とし穴”
- エンタープライズ版のみ提供の高度ガバナンス機能
- ライセンス条件と商用利用時の注意点
「全データ主権」と運用責任のすべて
結論は、全データ主権を選ぶことは同時に「セキュリティ運用の全委任」を受け入れることだという点です。
理由は、セルフホストではネットワーク境界、防御、OSやDockerの更新、TLS構成、データ暗号化、バックアップ、鍵管理、監視までを利用者が包括的に担う設計となるためです(参考: Dify Docs: Introduction)。
具体例として、私がPMとしてオンプレ環境に導入した際は「RAG用ベクトルDBの暗号化」と「アプリログのPIIマスキング欠如」による監査リスクが顕在化し、早期にログアクセス制御と保存ポリシーの明確化が必須でした。
再結論として、セルフホストで本番運用するなら、以下の最低限チェックリストを土台に、社内のSecOpsと共同で設計・運用プロセスを確立してください。

- VPC/オンプレのレイヤード防御(パブリック公開を最小化)
- TLS1.2+の終端とHSTS、強制HTTPSリダイレクト
- OS・Docker・Difyアプリの定期パッチ適用SLA
- DBとベクトル索引の暗号化(at-rest)と鍵管理方針
- フル/増分バックアップ、復旧テストの定期実施
- Secretsの分離保管(例: 環境変数とVaultの使い分け)
- 外部LLM/APIへの送信制御とデータハンドリング方針
あわせて生成AI全般の防御観点は、こちらの実務ガイドも参照してください(生成AIのセキュリティ完全解説)。
公式ドキュメントの限界と“落とし穴”
結論として、公式ドキュメントだけを鵜呑みに本番展開すると、HTTPSやネットワーク分離、初期設定の堅牢化が抜け落ち、高リスクのまま稼働しがちです。
理由は、セルフホスト手順は充実しているものの、本番セキュリティの推奨設定(TLSの強制、外部公開範囲の最小化、初期シークレットの更新など)の深度が足りないためです(参考: Dify Docs: Introduction)。
私の失敗談として、リバースプロキシのX-Forwarded-*ヘッダー設定を見落としCookie属性が想定外となり、SSO前提の社内プロキシ下でログインが循環して3時間停止したことがありました。
再結論は、「最小ToDo」を先に固め、構成ずれをコード化して再現可能にすることです。
- 外部公開は管理UIを閉域、アプリAPIのみ必要最小を公開
- 強制HTTPSとHSTS、セキュアCookie/SameSiteの明示
- 初期管理者の強制パスワード変更とサインアップ無効化
- DB接続のネットワーク分離とアプリレベルの最小権限
- バックアップ/復旧手順の演習を四半期で実施
参考:
HTTPSとリダイレクトの最低構成例です。
# Nginx (例): 80番は常にHTTPSへ
server { listen 80; server_name app.example.com; return 301 https://$host$request_uri; }
server {
listen 443 ssl http2;
server_name app.example.com;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
location / { proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Proto https; proxy_pass http://dify:3000; }
}
初期ハードニングの環境変数例です。
# docker-compose.override.yml の一例
services:
dify:
environment:
- SECRET_KEY=<十分に長い乱数>
- DISABLE_SIGNUP=true
- EXTERNAL_URL=https://app.example.com
導入計画と合わせて、社内ルール化や教育は次の記事も参考になります(MCPセキュリティ完全ガイド)。
エンタープライズ版のみ提供の高度ガバナンス機能
結論は、SSOや包括的監査ログが必須ならEnterprise一択であり、CommunityやCloud標準プランは選択肢から外すべきです。
理由は、Difyの高度な統制機能(SAML/OIDC連携、改ざん耐性ある監査ログ、強化RBACなど)がEnterprise専用として明確に位置づけられているためです(出典: Dify Blog: Azure Marketplace、GitHub Issue: Audit log)。
具体例として、マルチ拠点・複数部門の共通基盤では、IdP統合と証跡の長期保全が監査要件の肝であり、標準の「Logs」は開発・運用向けの断片ログに留まるため監査証跡として不足します。
再結論として、統制の土台から逆算し、EnterpriseのSSO/監査ログ/データ主権に収斂する計画を検討してください。

| 項目 | Community / Cloud標準 | Enterprise |
|---|---|---|
| SSO (SAML/OIDC) | なし | あり |
| 包括的監査ログ | 不足(断片的) | あり(長期保全/統合) |
| RBAC | 限定的 | 拡張ロール/きめ細かい権限 |
| データ主権 | Cloudは委託/Communityは自前 | オンプレ/VPCで完全 |
プラン全体像は価格面も含め、こちらの比較も参考になります(Difyの料金プランを徹底比較)。
参考:
ライセンス条件と商用利用時の注意点
結論は、セルフホストCommunityは「Apache 2.0ベース+追加条件」であり、社内利用と外部SaaS提供では義務が異なるため、導入前に法務レビューが必須です。
理由は、再販・統合・SaaS提供などの商用利用シナリオでは、追加条項により別途ライセンスや契約が必要になる可能性があるからです(出典: Dify Docs: License)。
具体例として、社内のナレッジBotで使うだけなら通常は問題になりにくい一方、Difyを基盤に自社SaaSを販売する場合は、商用ライセンスの相談が必要になります(問い合わせ先例: business@dify.ai)。
再結論として、商用展開の可能性が1ミリでもあるなら「用途別の法的整理」と「公式への事前照会」を標準プロセスに組み込むべきです。
- 用途の切り分け(社内限定/顧客提供/再販・統合)
- ブランド・名称の利用可否と表記ルールの確認
- OSSコンポーネントの告知・帰属表示要件
- 契約前に法務・セキュリティ・事業の三者合議を実施
あわせて実務面の整理には、こちらの詳解も参考にしてください(Difyの商用利用完全ガイド)。
Dify共通のセキュリティ注意点と“オープンソース脆弱性”傾向
当セクションでは、Difyの導入形態にかかわらず共通して押さえるべきセキュリティの要点と、公開CVE/GHSAの履歴から読み解くリスク傾向を解説します。
理由は、CloudとSelf-Hostedで責任分界は異なるものの、APIキー管理やアクセス制御、ログ運用の設計不備がインシデントの主要因として繰り返し観測されているからです。
- APIキー管理とクライアント露出のリスク
- コンテンツモデレーションは導入企業の責任
- 過去のCVE分析から見える“特有リスク”
- 機密情報マスキング機能の非搭載リスク
APIキー管理とクライアント露出のリスク
APIキーは必ずサーバー側で保管し、クライアント露出は絶対に避けるべきです。
なぜなら、DifyのAPIキーはBearer方式で高権限を持つため、一度漏えいすると不正呼び出しやログ・ワークスペース設定への連鎖的な被害に直結するからです(参考: Dify Docs)。
私は社内のAI API基盤でフロントには一切キーを渡さず、署名付きのバックエンド・プロキシを経由させる運用に統一し、DevToolsや拡張機能経由の窃取リスクを実質ゼロに抑えました。
DifyのAuthorizationヘッダーはHTTPS下のバックエンドでのみ付与し、クライアントとは短命トークンやセッションを用いて中継するのが定石です(参考: Logs and Annotation – Dify Docs)。
実装は以下のようなエッジ関数やAPIゲートウェイの中継が現実解です。
教育・運用面では発行・ローテーション・監視を型化し、レビューを定常化することで事故を未然に防げます。
import express from 'express'
import fetch from 'node-fetch'
const app = express()
app.use(express.json())
app.post('/api/chat', async (req, res) => {
const r = await fetch('https://api.dify.ai/v1/your-endpoint', {
method: 'POST',
headers: { 'Authorization': `Bearer ${process.env.DIFY_API_KEY}`, 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify(req.body)
})
const data = await r.json()
res.status(r.status).json(data)
})
app.listen(3000)- 発行権限の限定(本番キーはプラットフォーム管理者のみ)。
- 保管はKMS/シークレットマネージャと環境変数のみ。
- フロント送信・埋め込み・ビルド時注入を禁止。
- ローテーションは30〜90日目安、破棄は即時。
- 最小権限・用途別キーを分離。
- API監査ログとアラートを併用。
社内の横断教育には、実務でのAPIセキュリティを体系学習できるDMM 生成AI CAMPのようなプログラム活用も効果的です。
コンテンツモデレーションは導入企業の責任
Difyはモデレーション機能を“組み込める”だけで、デフォルトでは何もしません。
そのため、業界規制や社内ポリシーに合わせた有害表現・個人情報・著作権侵害のフィルタリングは導入企業側で必ず実装する必要があります(参考: dify-official-plugins、参考: Plugin Privacy Protection Guidelines)。
例えば「ユーザー入力→テキスト/画像セーフティ→許可/遮断→Dify推論→ログ」の直列フローにすると、危険トラフィックの手前で遮断できます。
下図は、Azure AI Content SafetyやPalo Alto Networksプラグインを前段に挟む基本形です(参考: Dify Blog)。
顧客サポートボットでは薬機法・差別表現・機密投稿の3系統フィルタをチューニングし、遮断時は安全な代替応答テンプレートで返す設計が有効です。
倫理・コンプライアンス設計の要点はAI倫理ガイドライン徹底解説や生成AIのセキュリティ完全解説も参考になります。
過去のCVE分析から見える“特有リスク”
公開CVE/GHSAの傾向は「Broken Access Control(アクセス制御不備)」が繰り返し見つかっている点にあります。
この傾向は、信頼関係の薄い複数チームや外部クライアントが同一インスタンスを共用するマルチテナント環境で、とりわけ深刻な影響を及ぼします(参考: NVD: CVE-2025-32795、参考: GHSA一覧 – langgenius/dify)。
以下は主要事例の整理です。
| ID | 種別 | 影響バージョン(≦) | ビジネス影響 |
|---|---|---|---|
| CVE-2025-32796 | アクセス制御不備 | v0.6.12 | 一般ユーザーがAPI経由でアプリ停止/起動しDoS誘発 |
| CVE-2025-32795 | アクセス制御不備 | v0.6.12 | アプリ名・説明の改ざん |
| CVE-2025-3466 | 任意コード実行 | 1.1.2 | サーバ乗っ取り・シークレット窃取 |
| GHSA-jg5j-c9pq-w894 | Broken Access Control | 未記載 | 他ユーザーのチャット閲覧 |
パッチは迅速に公開されるものの、アクセス境界の甘さというパターンを踏まえ、ネットワーク分離・WAF・ゼロトラストで多層防御を敷くべきです(参考: CVE.org検索)。
マルチテナントでの共用は避け、チームごとにインスタンス分離するか、SSO/RBAC/監査ログが揃うEnterprise版の検討が現実的です(参考: Dify Enterprise – Azure Marketplace)。
機密情報マスキング機能の非搭載リスク
Difyは入力ログを標準で保持する一方、PIIの自動マスキングは非搭載のため、生データが記録されるリスクがあります。
この設計は、PCI-DSSやGDPRなどの規制順守観点で重大であり、誤入力がそのままLogsに保存・閲覧可能になる点を前提に運用設計が必要です(参考: Logs and Annotation – Dify Docs、参考: Dify Docs)。
まずはUIでの注意喚起、誤入力時の即時削除手順、ログ・バックアップの保持期間短縮などの“運用ガード”を用意します。
次に、アプリ前段にPII検出・墨消しゲートウェイを置き、正規表現と機械学習検出器でトークン化/伏字化してからDifyへ転送するのが実務的です。
下図は「チャットUI→PII検出→伏字化→Dify API→ログ」の流れで、カード番号や個人番号を自動的にxxxx化する例です。
外部のセキュリティレイヤーやゼロトラスト構成はMCPセキュリティ完全ガイドや生成AIのセキュリティ完全解説も参考になります。
- “禁止PII”の定義とユーザー合意の明文化。
- 前段ゲートウェイでのPII検出・伏字化・マーカー付与。
- 誤入力時の即時削除・訂正フローとデータ主体要求対応。
- ログの閲覧権限最小化と保持期間の短期化。
- 監査証跡の改ざん検知とエクスポートポリシー整備。
// PII簡易伏字化イメージ(実運用は専用DLP/ML検出を推奨)
function redactPII(text){
return text
.replace(/\b(\d{4}[- ]?){3}\d{4}\b/g, '****-****-****-****') // クレカ
.replace(/(\d{6}-\d{7})/g, '******-*******') // 個人番号(例)
}
まとめと次のアクション
要点は3つ。DifyのセキュリティはCloudかSelf-Hostedかで性質が二極化すること、実務ガバナンス(SSO・監査ログ)はEnterpriseに集約されること、そしてセルフホストは主権と引き換えに高度な運用責任を負う点です。
Cloudは導入容易な反面、データレジデンシー等の不明瞭さが残ることも確認しました。ここまでの学びを土台に、迷いなく前へ進みましょう。
次の一歩は「自社要件を3軸(データ主権・監査・スピード)で優先順位づけ→PoC→本番化ロードマップ策定」です。今日から動けます。
実践と戦略の解像度を上げたい方は、良書で一気に補強を。生成AI活用の最前線。
ステップ設計の道標には、生成DXも併せてどうぞ。今が最速の一手です。
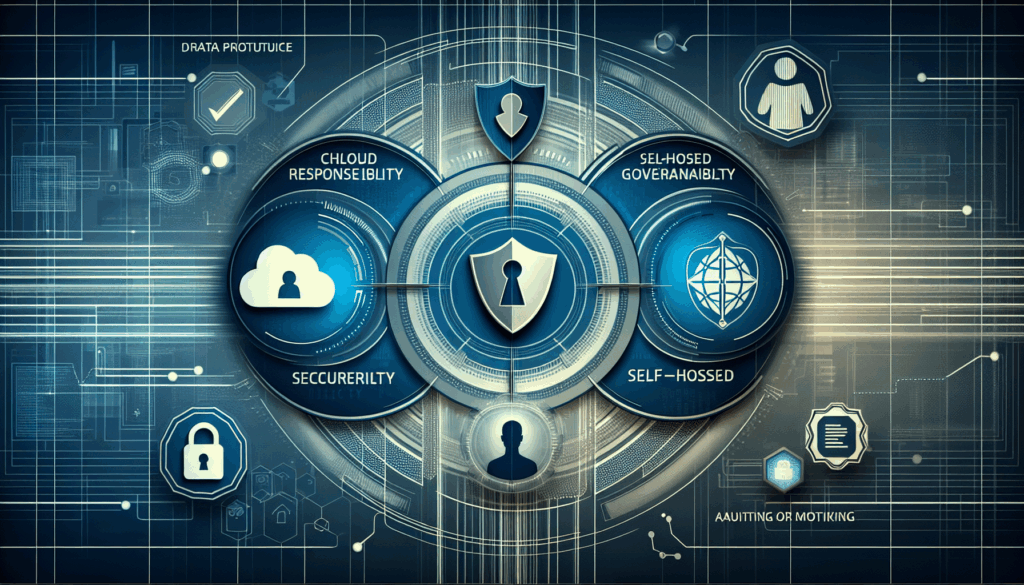






![チャットUI→PII検出(正規表現/ML)→墨消し・トークナイズ→Dify API→ログ保管のフローチャート。例: 4111-****-****-1111, 山田太郎→[PERSON]。](https://itc-tokyo.cdn.app-connect.cloud/saiteki-ai/pii_masking_flow_dify.svg)