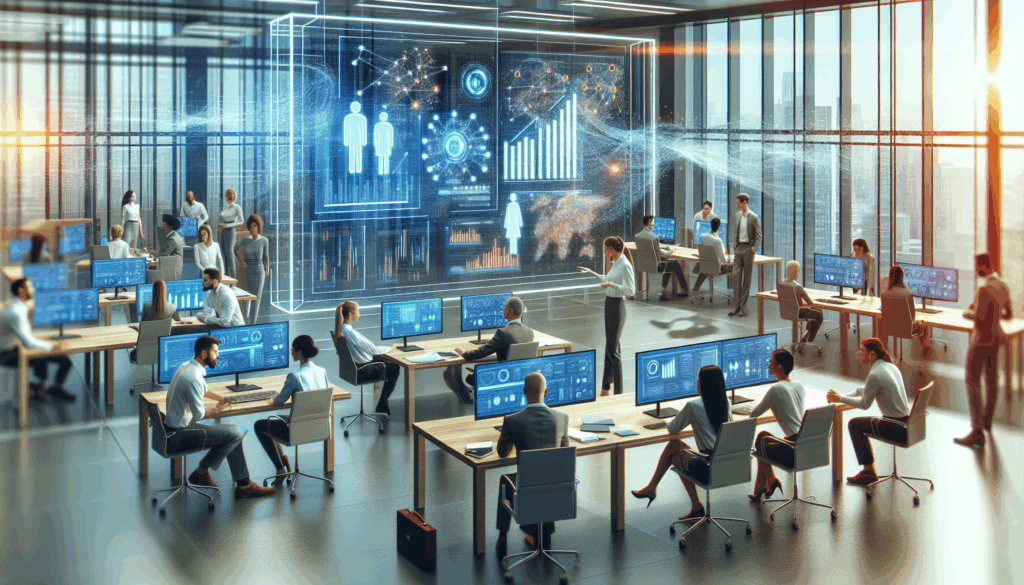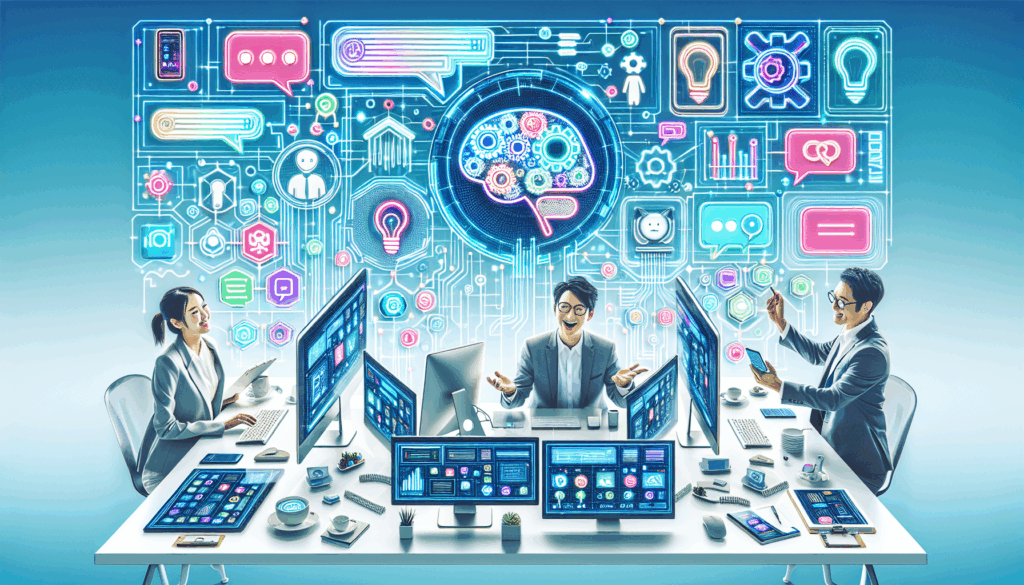(最終更新日: 2025年08月25日)
「AI導入で業務をもっと効率化したいけれど、どのツールが自社に本当に合うのか分からない」「HubSpotのAIってよく聞くけど、実際どんなことができて、費用感も気になる…」と悩んでいませんか?
本記事では、そんな迷いを抱える方に向けて、2025年注目のAI機能「HubSpot Breeze」について、その全貌から活用事例、費用まで“今、知っておきたいポイント”を徹底解説します。
単なる機能紹介や宣伝文ではなく、リアルな導入メリットや他社サービスとの違い、ROI(投資対効果)が分かる事例まで、実用的な情報を厳選。
読者が「これだ!」と思えるAIツール選びの決め手を見つけられるよう、専門家の視点で分かりやすくまとめています。
「どれを選ぶべきか」に迷うビジネスパーソンや経営者の方も、この記事でHubSpot AI導入のヒントと行動指針をきっと見つけていただけるはずです。
HubSpot AI「Breeze」とは何か?——全体像と導入メリットを解説
当セクションでは、HubSpotが2025年に発表したAIブランド「Breeze」の全体像、および導入企業にもたらす主要なメリットについて体系的に解説します。
なぜ本セクションを設けるかというと、Breezeは単なるAI機能の寄せ集めではなく、“SMB・成長企業に特化したAI活用の業務OS”として市場にも現場にも新しい価値観の転換をもたらしているからです。競合が増える中、HubSpotのAI戦略がどんな課題意識から生まれ、なぜ今多くの現場に選ばれているのか、深掘りする意義は大きいと考えます。
- HubSpotが「AIファースト」宣言した戦略的背景
- 「Breeze」3大AI機能群の全体像
- 筆者の現場実体験:AIは目的と現場課題に紐づいて初めてROIを発揮する
HubSpotが「AIファースト」宣言した戦略的背景
HubSpotは2025年に、全サービスを「AIファースト」へ大転換しました。
これは単なるトレンド追従ではなく、中小・成長企業(SMB)の「人手不足」「IT予算の限界」「複雑なAIツールは使いこなせない」という切実な声への本気の回答です。
たとえば、私の支援先の中堅企業では「AIツールを導入したいが、都度説明書を読み直し、各部署でバラバラに管理され、現場は疲弊したまま」という嘆きが度々上がっていました。この課題に対しHubSpotは「AI機能を追加する」のではなく、「あらゆる業務ツールを一体化し、しかも直感的に使えるAI業務OS」に作り変える戦略を公式に打ち出しました(HubSpot公式ページ参照)。
SMBの現場では、「AIに乗り遅れたくない」という焦りと、「操作もコストもついていけない」というリアルな不安が常につきまといます。HubSpotは、それらの本音をふまえ「シンプルで、すぐ使え、全業務にまたがるAIパッケージ」を目指したのです。
この「AIファースト」の本質は、AIの“点”導入から“面”の業務変革へのシフトです。
「Breeze」3大AI機能群の全体像
Breezeは「Copilot」「Agents」「Intelligence」、3つの役割分担されたAI機能の柱からなる明確な構造です。
Copilotは“誰でも扱えるAIアシスタント”として、文章生成やデータ要約・レポートなど日常的な作業をサポートします。Agentsはそれをさらに進化させ、営業・マーケ・カスタマーサービスにおける「デジタルワーカー」として高度な自動実行を担い、部分的な定型業務ではなく「業務フロー全体」を丸ごと自動化します。Intelligenceは、全てのAIの基盤となる「データの質と連携」を徹底強化し、“精度×運用効率”の総合力を支えます。
この三本柱は、社内に“IT専門職をほとんど持たない”中小現場でも、「とっつきやすいAI活用→一部の業務自動化→会社全体のワークフロー最適化」へと段階的にスケールアップできる設計です。
言い換えると、Breezeは「どこからでも始められ、成長ステージとともにAI活用範囲が自然に広がるオールインワン構造」という点が最大の特徴です。
下図は、Breezeの3層モデルとその相互循環をビジュアル化したものです。
このような全体設計が、ユーザーに「これだけで十分」という安心感と、DX推進の“持続可能な好循環”をもたらします(参照:HubSpot AIツールBreezeでハードルの高い成長目標を簡単に達成)。
筆者の現場実体験:AIは目的と現場課題に紐づいて初めてROIを発揮する
AIツールは「入れるだけ」では本来の威力は発揮されません。
私が実際に中堅製造業の業務プロセス設計〜自動化運用に伴走した際も、最初は「AIでメール自動返信」「AIで帳票作成」など機能単位で点在した使い方に留まっていました。しかしボトルネック分析を通じ「どこに最も時間・コスト・心理的負担が集中しているか」を細かく可視化したうえで、「ここはAgentで全自動化、ここはCopilotが日常補助、根本の顧客データ精度はIntelligenceで補強」という“設計連動”に変えたことで、現場の生産性もストレスも劇的に改善した実感があります。
特にHubSpotは「UI設計の統一」と「効果測定ツールの一体化」に優れ、導入現場でも“IT操作が苦手なスタッフ”が迷わず使え、数値的インパクト(例:問合せ半減、レポート作成年300時間削減)をすぐ実感できました。
この経験からも、「業務全体を一気通貫でカバーするBreeze構造」を選ぶことが、中小・成長企業の“本物のAI ROI”獲得への最短ルートだと確信しています。
主要なAI機能を徹底解説:Breeze Copilot/Agents/Intelligenceで何ができる?
当セクションでは、HubSpotが「Breeze」ブランドのもとで展開する、主要AI機能――Copilot、Agents、Intelligence――について解説します。
その理由は、これらの機能がHubSpotを「単なるCRM」から、業務全体を自動化し成長を加速させる『AI搭載カスタマープラットフォーム』へと進化させている中核だからです。
実際にこれらの違いと連携を正しく理解すれば、自社課題のどこにどのAIを投入するべきか迷うことなく、具体的な業務改善や成果向上を実現できます。
- Breeze Copilot:全社員のAIアシスタントとして使う
- Breeze Agents:業務ごとに“専門AIワーカー”を自動配置
- Breeze Intelligence:データの質こそAIのパワーの源泉
Breeze Copilot:全社員のAIアシスタントとして使う
Breeze Copilotは、現場の“誰でも”AIによる業務サポートを実現できる、HubSpotのユニバーサルAIアシスタントです。
なぜなら、CopilotはChatGPTのような対話型インターフェースをHubSpot画面上に直接搭載しており、Eメールやブログ執筆、営業資料の作成、CRMデータ検索・要約まで、自然言語でアクションできるからです。
例えば「この1か月で一番反応が良かったメルマガ案を出して」と入力すれば、CRMデータを解析して即座に提案。営業担当が「30日間で最も接触回数が多い顧客リストを見せて」と尋ねれば、面倒な条件設定なしにリストを自動生成します。知識ゼロの新入社員でも、AIアシスタントに「先週の顧客問い合わせを要約して」と打つだけで、要点が整理されて返ってきます。
セットアップも管理者による有効化だけで、全従業員がワンアクションで使えます。Copilot公式プロンプト集は現場で迷わずAI指示が出せる強力な武器です。
| 業務カテゴリー | プロンプト例 |
|---|---|
| Eメール作成 | 「”新製品のトライアル案内メールを作って”」 |
| 営業リサーチ | 「”今期売上が前年比20%以上伸びた顧客を一覧で”」 |
| CRM要約 | 「”田中商事の過去1年の対応を300字で要約”」 |
| 問い合わせ対応 | 「””よくある質問””集からQ&Aを自動生成」 |
公式ガイド(HubSpot Knowledge Base)もプロンプト設計の参考になります。
Breeze Agents:業務ごとに“専門AIワーカー”を自動配置
Breeze Agentsは、特定業務を“自律的に完結”させるAIスペシャリストを、必要なだけ自動で配置できる仕組みです。
なぜなら各Agentは「コンテンツ制作」「営業リサーチ」「顧客サポート」など役割ごとに事前学習されたAIで、社内データや外部情報も駆使し、従来は人員増員でしか賄えなかった運用パワーをデジタルで拡張するからです。
たとえば「Content Agent」はブランドボイスを守りつつランディングページや記事、事例など複数タイプのコンテンツを大量生成。「Prospecting Agent」なら、ターゲット企業の自動リストアップやアプローチ文作成まで「本当に欲しいリード」だけを24時間営業してくれます。「Customer/Knowledge Base Agent」は問い合わせ窓口で24時間休みなく回答しながら、メンテが追いつかないFAQや記事も自動生成。SNS Agentなら投稿案をパフォーマンス解析とあわせて高速で続々と提案。しかも各エージェントはβ版と正式版が混在し進化中、導入検討の際は下表で機能カバー範囲を確認できます。

Breeze Intelligence:データの質こそAIのパワーの源泉
Breeze Intelligenceは、CRMデータの「質と量」を強みに据えたHubSpot AI戦略の“根幹”です。
というのも2億件超の企業・個人プロファイルで自動エンリッチメントし、フォーム短縮や訪問企業特定など、情報精度を競合と一線を画しているからです。
たとえばフォームでは「既知情報は自動入力&省略」で御社の顧客体験を一歩先へ。エンリッチメント済みコンタクトは即CRMに反映され、CopilotやAgentsによる提案も的確度が向上します。また「どの企業がWebを見て、何に興味を持ったか」を匿名でも即特定、無駄打ち無しで営業パイプラインを高速化できます。データ→Copilot活用→Agent自動化→再データ強化…というフィードバックの循環が、AIの成長にも直結します。
実際、HubSpot AI公式特設ページでも、この「統合データ→AI活用」の戦略が“成果創出”の要と強調されています。データの質なくしてAI活用は語れません。
料金・クレジット体系を徹底理解:HubSpot AIの費用構造とコスパを正しく試算
当セクションでは、HubSpot AIの料金・クレジット体系について徹底解説し、実際のコストシミュレーションまでわかりやすくご紹介します。
なぜなら、AIプラットフォーム選定の多くの失敗は「価格体系の誤解」から生まれるため、事前に透明な全体像と自社に最適な試算方法を知ることが不可欠だからです。
- サブスクリプション×従量課金の“ハイブリッド”料金モデル
- 具体的なコスト試算例:エンリッチメントとAIエージェントの現実的な費用感
サブスクリプション×従量課金の“ハイブリッド”料金モデル
HubSpot AIの特徴は、毎月定額+使った分だけの「ハイブリッド料金モデル」で、予算管理と柔軟な運用を両立できる点です。
この仕組みでは、各Hubとプラン(Starter、Professional、Enterprise)ごとに月額料金が決まり、それぞれに「AIクレジット(HubSpot Credits)」が一定量付与されます。
たとえば、Starterは月500、Professionalは3,000、Enterpriseは5,000と、上位プランほど多くのAI処理枠が含まれる設計です。
「月間の範囲内での利用」だけなら追加費用なしで済みますが、クレジットをオーバーした場合も自動で1,000単位(約10ドル)のパックが都度購入でき、プロジェクト急増時や将来の成長にもスムーズに対応できます。
| Hub/プラン | 月額料金 | 主なAI機能 | 付与クレジット |
|---|---|---|---|
| Marketing Hub Starter/Pro/Ent |
$15〜 $890 $3,600 |
AIアシスタント・Customer Agentなど | 500/3,000/5,000 |
| Sales/Service Hub | $15〜/シート $100〜/シート $150〜/シート |
AI Eメール生成、AIサポートエージェント等 | 500/3,000/5,000 |
| Content Hub | $15〜 $500 $1,500 |
AIブログ/コンテンツエージェント | 500/3,000/5,000 |
| 追加1,000クレジット | 価格 | クレジット消費例 |
|---|---|---|
| 1パックごと | 約$10 | データエンリッチ:10/件、その他:AIアクション別 |
この“使った分だけ払う仕組み”は、Salesforceなどの従来型CRMの複雑さや予期せぬ超過請求リスクと比べて非常に明瞭です。
実際の運用では、標準分のクレジット=業務のベース運転費用、追加分=一時的な施策強化や成長分とみなすことで、経営層にも“読めるAI投資計画”を提示しやすくなります。
具体的なコスト試算例:エンリッチメントとAIエージェントの現実的な費用感
HubSpot AI導入の費用対効果を正しく把握するには、「自社の使い方」で現実的なシミュレーションを行うことが非常に重要です。
たとえば、「毎月10,000件の顧客データをAIで名寄せ・情報補完したい」というケースを考えてみましょう。
データエンリッチは1件あたり10クレジット。月間計算では10,000 × 10 = 100,000クレジットです。
Enterpriseプラン(5,000クレジット付与)なら、差分の95,000クレジットを追加購入(1,000単位・各約10ドル)する形になり、追加コスト目安はおよそ950ドル。これに基本月額(例:Marketing Hub Enterprise 3,600ドル)が上乗せされ、合計約4,550ドルで「10,000件分の高度AI化」が実現できます。
| エンリッチ件数 | 必要クレジット | 追加購入クレジット | 追加コスト(目安) | サブスクリプション | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000件 | 50,000 | 45,000 | $450 | $3,600 | 約$4,050 |
| 10,000件 | 100,000 | 95,000 | $950 | $3,600 | 約$4,550 |
| 3,000件 | 30,000 | 25,000 | $250 | $1,500(Content Hub Entの場合) | 約$1,750 |
この試算からも、「AI機能で何を・どれだけ行うか」がコストに直結する明快な構造であること、逆にエンリッチメントを控えれば追加費用ゼロで運用できる柔軟性が実感できます。
また、AIエージェント(Prospecting AgentやCustomer Agent)もクレジット消費型ですが、例えばサポートの自動化率を50%に高めた場合、人員増員とのコスト比較で「AIの追加利用の方が安価でROIが高い」となるケースが多数報告されています。
このように、HubSpot AIの料金体系は「自社のAI活用モデル」と密接に連携しています。表や実際の計算例をもとに現場で試算することで、最適なコスト配分を見極め、ムダのないAI活用を目指すことが肝心です。
導入の具体的イメージや比較軸についてもっと知りたい方は、AI営業ツール完全比較|おすすめ・選び方・事例まで徹底解説!や公式説明ページ(HubSpot AI製品)もご参照ください。
ROIで比較:実証済み導入事例&メリットを分かりやすく紹介
当セクションでは、HubSpotのAI機能を導入した企業が実際にどのようなROI(投資対効果)を得たのか、具体的な事例とともに各部門でのメリットをわかりやすく解説します。
なぜなら、AI導入は「なんとなく便利そう」だけでなく、明確な成果や実利がなければビジネス上の意思決定につながりにくいからです。
- ビジネス部門別の主要効果—マーケ・営業・サポート各現場でAIはどう役立つ?
- HubSpotのAI活用で実現したリアルなDXシナリオ
ビジネス部門別の主要効果—マーケ・営業・サポート各現場でAIはどう役立つ?
HubSpotのAI機能は、マーケティング・営業・カスタマーサポートいずれの現場でも、数字で証明できる成果をもたらします。
その理由は、各エージェントやAI機能が単なる「作業効率化」に収まらず、「売上UP」や「コスト削減」といった明確なビジネスKPIの変化に結びついているからです。
例えば、「Content Agent」を使った画像生成では、従来3週間かかっていたバナーや提案用画像が5分で完成。これによりマーケティング施策の実行回数が飛躍的に増え、ROIが大きく向上しています。
また、「Blog Writer」機能で週1〜2本が限界だったブログ制作も、250%増のペースへ急拡大。FBA社ではオーガニックリードが200%以上増加し、「リード獲得単価を大幅に下げる」ことに成功しました。
さらに、「Customer Agent」は50%以上の問い合わせを自動応答し、サポート工数を実質半分に削減。人的コストをかけずにCSAT(カスタマー満足度)が向上し、「人手を増やさず会社全体のサービスレベルを底上げ」しているのです。
このような成果は公式レポートでもグラフ・指標として公開されており、「どの部門が最も効果を得やすいか」「投資対効果が期待できる導入ポイントはどこか」といった自社課題ごとの判断の道しるべになります。
HubSpotのAI活用で実現したリアルなDXシナリオ
AI導入成功の鍵は、「ツールの派手さ」よりも現場課題に直結した機能選択・使い方を設計できるかにあります。
VELUX(製造業)では、顧客提案用のカスタム画像作成がボトルネックで、新規案件の営業チャンスをことごとく逃していました。しかし「Breeze Copilot」の画像生成AI導入で、作業時間が2〜3週間から5分に激減。営業実働日数が短縮され、失注リスクを可視化できるレベルで下げられたことで、売上サイクル全体が再設計されました。
一方、Franchise Brokers Association(FBA/専門サービス業)は、少人数のマーケチームで週1記事がやっと。AI Blog Writerで記事量と多チャンネル展開を一気に拡大し、リード単価は広告と比べて何分の一にも圧縮。結果として「広告支出を抑えた成長モデル」へピボットできました。
筆者自身が伴走した中堅企業のDX推進プロジェクトでも、型どおりAI導入を進めてしまった失敗例があります。例えば「チャットボットを置くだけ」では現場社員が使わず、サポート部門の問い合わせ流入も減りませんでした。その後、実際の業務ヒアリングの中から「特に問い合わせが集中するFAQ」に特化したCustomer Agentを設計し直したことで、一週間で解決率と現場満足度が急改善したのです。
このように、AI活用で本当のROI(費用対効果)を出すためには、まず自社ならどこに「最大のボトルネック」や「成長課題」があるかを見極め、HubSpot上の機能をピンポイントにマッピングすることが決め手です。
どの分野でも“課題解決ドリブン”の活用が、DX(業務変革)の成果最大化を導きます。
競合比較で見えてくるHubSpot AIの立ち位置と向いている組織
当セクションでは、HubSpot AI(Breeze)が主要な競合サービスと比べてどのような独自ポジションを持ち、どんな組織にベストマッチかを説明します。
なぜこの内容を深掘りするかというと、AIプラットフォーム導入の成否は「どんなチームに、どう運用させるか」に大きく左右されるからです。
- Salesforce Einstein等 大手競合との違い—中小・成長企業にとっての本当の利点
- 今後のAIロードマップと、最新開発動向
Salesforce Einstein等 大手競合との違い—中小・成長企業にとっての本当の利点
HubSpot AI最大の強みは、専門部署や開発リソースがなくても“ノーコードで統合AI運用”が即日始められる点です。
なぜならHubSpotは、CRM・マーケ・営業・カスタマーサポートまでワンストップでAI実装済みツールを揃えており、「今日から誰でも」全社横断で成果を出せる思想設計になっているからです。
たとえばSalesforce EinsteinやMicrosoft Copilotのような大手AI競合は「膨大なカスタマイズ性」が売りで、大企業のIT部門・外部パートナーによる独自開発前提のつくりです。
現実として、マーケや営業部が主導で予算管理しながらAI活用を推進したい中小・成長企業にとっては、「連携構築や社内ヘルプデスク対応で休日返上…」といったIT負担や、人手不足・コスト増大が想像以上の障壁となります。
HubSpotなら、社内の“現場主導”で即AIのメリットを体験でき、クレジット課金も明瞭なので「まず始めてみて、効果を見て予算を増やす」柔軟な導入も実現できます。
両者の違い、どんな企業がどちら向きかを以下にまとめます。
要するに中小~成長企業で「すぐ成果を上げたい」「複雑なカスタマイズより導入・運用のしやすさ重視」ならHubSpotのAI統合型アプローチが最適解です。逆に「自社独自プロセス」「高度なAI自動化」に膨大な投資余力があるならSalesforceなどの大手エンタープライズ向けも選択肢となります。
HubSpotとSalesforceの比較詳細(Zapier公式)
今後のAIロードマップと、最新開発動向
HubSpotのAI機能は、2025年以降さらに“現場実装型AI”へ進化することが明示されています。
なぜなら、同社公式ロードマップによれば、AI Voicebot(電話対応の自動化)、動画生成、会話インテリジェンス(Frame AI買収)など「人の手が必要だった領域」まで自動化範囲を拡張中だからです。
例として、Breeze Copilotのようなアシスタントは既に現場で活躍していますが、これにAIエージェント(例えばSocial Agent、Content Agent)、Voicebotを組み合わせることで“営業初期アタック~案件化、コンテンツ制作、サポート”の業務がほぼ自動化されるイメージが具体化しています。
今後正式リリース予定の機能や、ターゲットとなるユーザー像をわかりやすく図表でまとめることが大切です。
この進化を背景に、今や「デジタルチーム=AIが主軸」な時代が目前に迫っています。「AI化は遠い未来」ではなく、「今ここにある選択肢」となりつつあります。
よくある質問・疑問にプロの目線で回答【HubSpot AI FAQ】
当セクションでは、HubSpot AI導入に関して多く寄せられる“疑問”や“不安”を、現場経験豊富なプロ視点でひとつずつ解消します。
理由は、AI選定・連携・運用の判断ポイントを明確に理解しなければ、ただAIを導入するだけで現場の生産性や収益は思うように伸びないからです。
- 今使える“ベストなAIツール”は?HubSpotはどう選ぶ?
- HubSpotとChatGPTを連携したい場合は?
- AIの種類にはどんなものがある?HubSpot Breezeのタイプは?
- HubSpotによるMotion AI買収はいつ?何に活きる?
今使える“ベストなAIツール”は?HubSpotはどう選ぶ?
現時点で「AIツールNo.1」は一概に断言できませんが、中堅から成長企業の「使いやすさ・全社展開・ROIの明確さ」を重視するならHubSpot Breezeは“まず検討すべき本命候補”です。
その理由は、直感的で学習コストが低いインターフェース、分野別に最適化されたAIエージェント、導入・増員・運用のコストが見通しやすい統一プラットフォームにあります。
例えば、あるITベンチャー企業では「AI活用の現場定着」を単機能ツールで繰り返し失敗した後、Breezeで“営業・マーケ・CS”を一貫運用し、数ヶ月でリード獲得や受注率の定量成果が出始めたという事例もあります。
「現場で“指示待ちAI”にならず、真に全社スケールさせたい」なら、まずは“UI・コスト透明性・統合性”の3軸で他サービスと比較する目を持つことをおすすめします。
HubSpotとChatGPTを連携したい場合は?
HubSpotをChatGPTと連携したいなら、「API連携によるカスタムChatbot構築」「FAQの自動生成」「営業・サポートプロンプトの個別最適化」など複数の方法が選べます。
理由は、HubSpotが公式にAPIドキュメントを公開し、外部AI連携やGAS(Google Apps Script)などエンジニア不要で日本語化も進めやすい設計となっているためです(公式ヘルプ/国内事例記事参照)。
例えば、公式のガイドに沿って「サイトの問い合わせボット」にChatGPTを組み込み、FAQを自動生成させ“現場のナレッジづくり”を時短した日系SaaS企業のケースがあります。
「Breeze Copilotそのまま」か「ChatGPT APIラッピング」か現場要件で選び、APIやGASの独自活用ならセキュリティと運用負荷に十分配慮しましょう。
AIの種類にはどんなものがある?HubSpot Breezeのタイプは?
AIには「Narrow AI(特化型・実用型AI)」と「汎用AI(AGI)」の2種類があり、Breezeは前者=業務特化型のAIです。
こうした分類の理由は、AI技術が実務現場の課題(問い合わせ対応・データ入力・コンテンツ生成など)を短期で解決するには、万能型ではなく「業務フォーカス型AI」が最もROIを出しやすいからです。
実際、Breezeはマーケ・営業・カスタマーサクセスの現場課題“専用”に設計されており、すでに80以上のAI機能で自動化・効率化を実現しています。
今後は「マルチモーダル化(画像・動画・音声も自動化)」も公式に開発中であり、Breezeは“現実解”としてのNarrow AIから更なる領域拡張が期待されています。
HubSpotによるMotion AI買収はいつ?何に活きる?
2025年1月、HubSpotは会話解析AIのFrame AIを正式に買収し、チャットや通話のVOC解析・CS自動応答へ活用すると発表しています。
この狙いは、顧客からの生声や問い合わせチャネルの会話データを、“人の目・耳”を介さずAIで自動分類・分析することで、次世代カスタマーサクセス(CX向上)を大規模化するためです(HubSpot公式IR参照)。
たとえば、Frame AI技術が入ることで「チャット履歴や通話録音=VOC情報」を分析&インサイト化し、問い合わせナレッジの自動強化やエージェントの対応最適化が進むでしょう。
“フロントのAIチャット”と“裏側のVOC分析AI”を統合できる今後のHubSpotは、業務効率と顧客体験(CX)の両立という現場ニーズにさらに強みを発揮します。
まとめ
本記事では、HubSpotのAI搭載カスタマープラットフォーム「Breeze」がもたらす戦略的価値、主要機能、価格体系、そして実際の導入企業が得た成果までを詳しく解説しました。
重要なのは、AIの導入は単なる流行や部分最適ではなく、実際のボトルネック解消と成果創出を目指す課題解決ファーストの発想が鍵になるという点です。
自社に合ったAI活用のヒントを得た方は、まずは実践的なノウハウやAI人材育成のための学びに一歩踏み出しましょう。気になる方は、仕事で使えるAI活用法の決定版『生成AI 最速仕事術』や、基礎から実務応用までを体系的に学べる『DMM 生成AI CAMP』をチェックして、新たな一歩を始めてみてください!