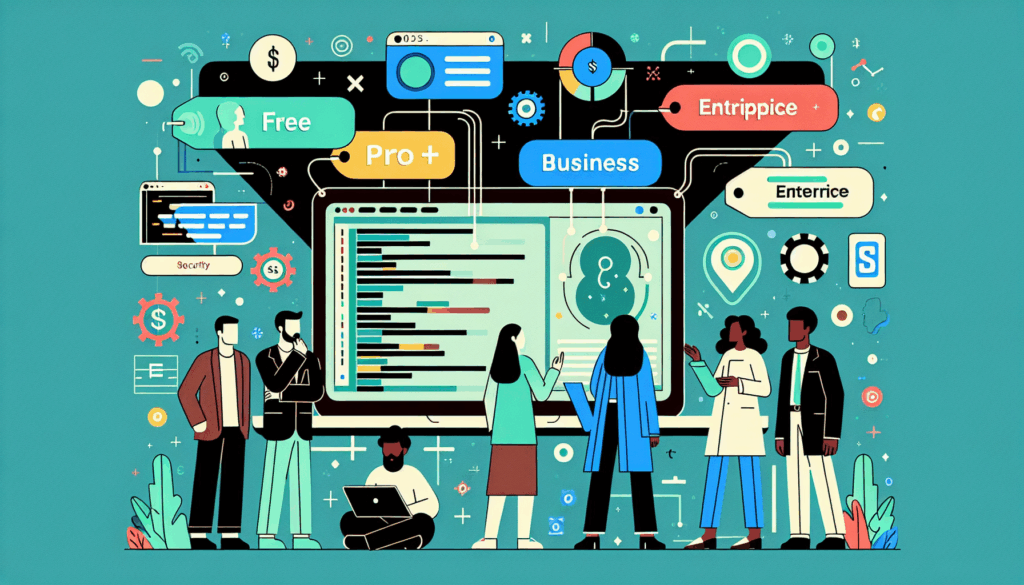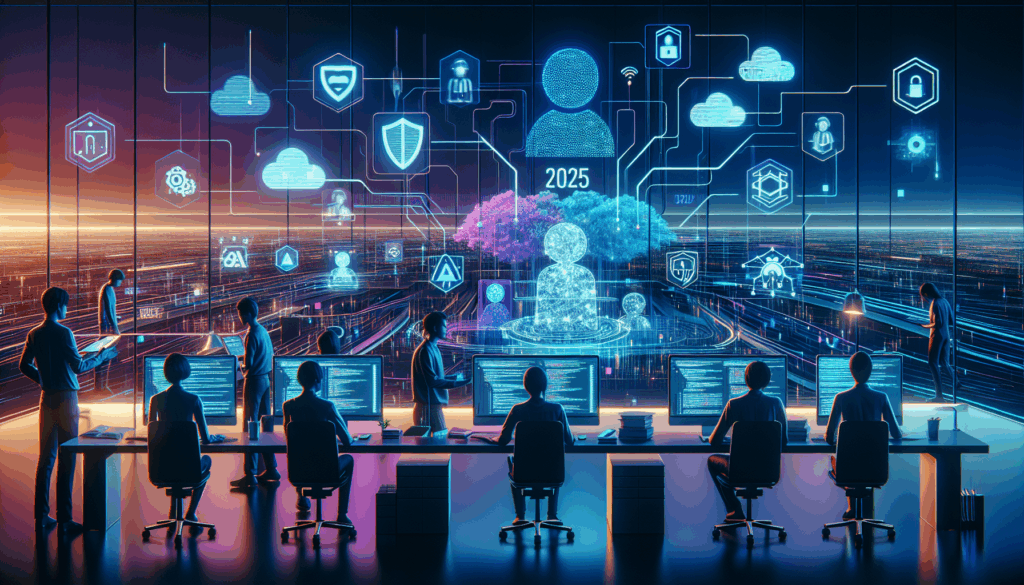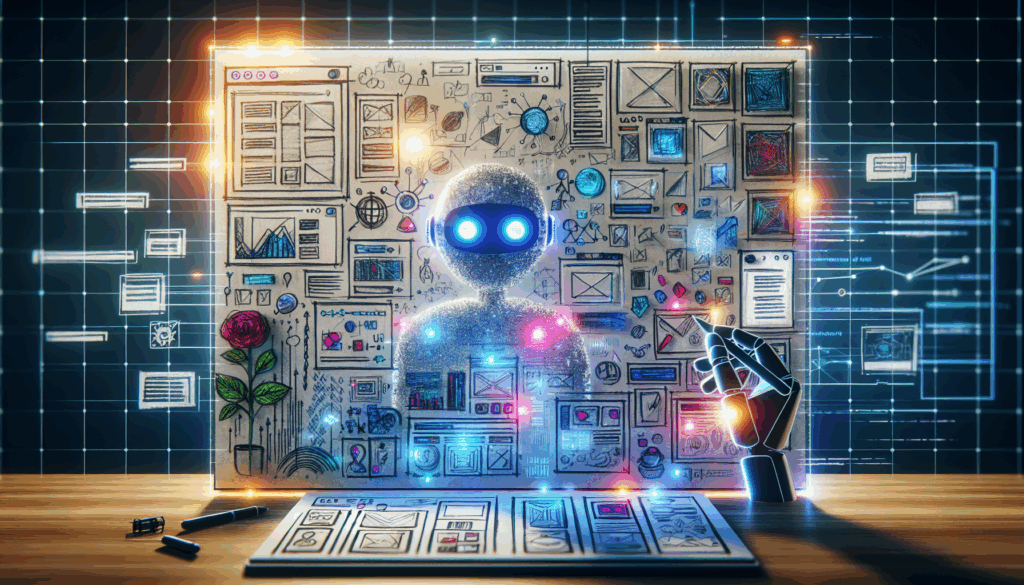(最終更新日: 2025年07月16日)
「GitHub Copilotの料金って自分に合うプランがあるの?」 「無料プランや学割、本当に活用したほうがいいのかな?」──そんな悩みを抱えていませんか?
この記事では、毎日多くのエンジニアや開発者が直面する「料金のお得な選び方」から「無料・学割で賢く使う方法」まで、最も新しい2025年最新情報をもとにやさしく解説します。
各プランのポイントをわかりやすく比較し、セキュリティや知的財産の観点からも失敗しない選び方を紹介。あなたにピッタリなCopilotプランが素早く見つかり、すぐに実践できる内容です。
公的な情報や公式ソースをしっかりリサーチし、実務者視点で整理した内容なので、初めての方も安心して読み進められます。
GitHub Copilotの料金体系|全プラン早わかりガイド(2025年最新版)
当セクションでは、2025年7月時点でのGitHub Copilotの最新料金体系を、個人・法人それぞれの全プラン比較を交えて徹底解説します。
なぜなら、Copilotは用途や規模によって必要なコストや機能・管理レベルが大きく異なり、「何となくProでよさそう…」と契約してしまうと、本当に必要だったセキュリティ保証やコスト管理の観点で後悔するケースが多発しているからです。
- 個人向け:Free/Pro/Pro+の違いと選び方
- 法人向け:Business/Enterpriseでできること・コストの落とし穴
個人向け:Free/Pro/Pro+の違いと選び方
個人ユーザーにとっては、「Copilot Free」「Pro」「Pro+」という3段階のプランの特性と使い分けが最初の大きな判断ポイントです。
なぜなら、それぞれ利用できるAI補完の回数・モデルの質・チャットの上限などが大きく異なり、「試しに始めたいだけ」なのか「毎日業務で使い倒したい」のかで費用対効果も体験も全く違ってくるためです。
例えば、Freeプラン(月0ドル)は月2,000回のコード補完&チャット50回(Claude 3.5 Sonnet/GPT-4.1可)という「本当にお試し」向き。少し使い込むとすぐに上限にぶつかり、Pro(月10ドル/年100ドル)にアップグレードすると無制限利用+最新モデルのプレミアムリクエスト(月300回)が解放されます(この時点でたいていの業務ユーザーは大満足です)。一方で「最先端のAIモデルで最大効率の作業をしたい」「カスタムナレッジベース連携も視野に入れたい」など上級者には、Pro+(月39ドル/年390ドル)という“AIパワーユーザー専用”コースが用意されています。
このように、「どれを選ぶのが正解か」は、『自分の開発頻度』『必要なAIの精度』『毎月の予算』によって分かれます。たとえば月に数回しか使わない趣味の人はFree、毎日長時間使うならPro、知識ベース連携や全モデルの最高精度が現場要件ならPro+を選択…という判断が王道です。GitHub Copilot公式料金表や、詳細なプラン比較は公式ドキュメントも必ず確認しましょう。

法人向け:Business/Enterpriseでできること・コストの落とし穴
法人ユースでは、「Business」「Enterprise」プランが“作業効率化ツール”を超えた経営資産化・リスク管理の要になります。
理由はシンプルで、個人Proプランなどと違い「IP補償(万一の著作権係争リスク補填)」「ライセンス一元管理」「コンテンツ利用ポリシー」など組織的な責任とコンプライアンス対応をガッツリ強化しているからです。中でもEnterpriseはGitHub Enterprise Cloud連携が必須で、実質1人あたり月60ドル(Enterprise 39ドル+GHEC 21ドル)という構造になっており、価格情報だけを見て見積もると“半額以下”で計上する失敗例が多発しています。
たとえば10人チームでBusinessなら「19ドル×10人」、Enterpriseに移行した場合は「(39+21)×10人」=月600ドルがベースコストに。しかもいずれも最新モデル利用分(プレミアムリクエスト枠超過)は都度0.04ドル/回の従量課金が発生するため、*利用実態を見ない予算立案は危険*です。IP補償が効くのは「重複検出フィルターONかつAI提案コードの未編集部分のみ」など適用範囲も押さえましょう。
このように、法人プランは「コスト+法的リスク+管理負荷」の三点見積りが必須で、単純な機能比較だけでは危険です。実務ではプラン公式ドキュメントや、契約前のTCOシミュレーション例(下表)を活用して、予期せぬ経営リスクを未然に防ぎましょう。

料金に関するよくある疑問を一挙解決
当セクションでは、GitHub Copilotの料金体系について、よくある疑問を実際の利用シーンや申請方法も交えて詳しく解説します。
なぜなら、多様なプラン・特典・制限があるため、「結局どの料金プランが自分や自社に最適か?」と悩む方が非常に多いからです。
- GitHub Copilotの料金はいくらですか?
- 個人でもCopilotを無料で使える?学割や無償提供の条件は?
- 無料版にはどこまで制限がある?
- 有料版(Pro/Business/Enterprise)ならではの特典は?
- プレミアムリクエストや従量課金の仕組みは?(TCOの注意点)
GitHub Copilotの料金はいくらですか?
GitHub Copilotは、個人・法人向けに複数の料金プランが用意されており、機能とコストの見極めが重要です。
理由は、同じ「Copilot」という名称でも、利用者の規模や目的によって月額・年額、利用可能機能が大きく異なるからです。
たとえば、個人向けには月$0(Free)、月$10/年$100(Pro)、そしてパワーユーザー向けの月$39/年$390(Pro+)プランの3つがあります。法人ではBusiness(月$19/人)、Enterprise(月$39/人)ですが、Enterpriseには別途GitHub Enterprise Cloud(月$21/人)が必須のため、実質月$60/人となります。
それぞれの違いや料金の早見表は公式サイトで常に更新されているので、公式のCopilot料金プラン一覧から最新版をご確認ください。
個人でもCopilotを無料で使える?学割や無償提供の条件は?
個人であればCopilot Free(月$0)プランを誰でも利用できますが、学生・教員や著名OSSメンテナーはProプランを無償で利用できる特典があります。
理由として、GitHubは次世代開発者やオープンソース推進の観点から、認証された学校関係者や主要OSSメンテナーに最上位のAIコーディング体験を提供しているからです。
筆者自身も大学生として申請し、Global Campus経由の申込画面で学生証や学校メール認証を行うことで、わずか数日でProの全機能を解放できました。対象者にはサブスクリプション画面やメールで明確に案内が届くので、GitHub Education公式サイトも要確認です。
オープンソースの無料枠は手動申請不要で、スター数・依存性数などによる審査もあるので、自分が該当するかはCopilot設定画面をチェックしましょう。
無料版にはどこまで制限がある?
Copilot Freeプランでは、月間2,000回のコード補完と50回までのチャット利用に厳しい制限が設けられています。
というのも、フリーミアムモデルの戦略で「お試しは十分、でも少し本気で使うと物足りない」絶妙な上限を設けているためです。
実際に私がFreeプランで日常的に開発していたとき、月末近くなると「ある日突然、提案が一切出なくなった」ことがありました。チャットや補完が停止したタイミングで、はじめて利用上限を意識するものです。
Proと比べて「チャットも補完も途切れないストレスフリー感」が得られない点は、用途が本格化したらすぐ感じる違いといえるでしょう。
有料版(Pro/Business/Enterprise)ならではの特典は?
有料プランでは無制限の補完・チャット、最新AIモデルやコードレビュー、法人向けはIP補償や厳格なセキュリティ管理が大きな価値です。
なぜなら、個人利用では多少の制限でも済みますが、継続的な開発や組織・企業での利用では「回数無制限」や「ガバナンス」「法的リスク軽減」は不可欠だからです。
具体的には、Pro/Pro+プラン利用者は月300~1,500回分のプレミアムリクエスト、Business/Enterpriseは一元管理とIP補償(万が一の著作権訴訟時もGitHubがサポート)。このIP補償制度や監査ログ対応、SAML認証については、公式セキュリティFAQにも明記されています。
「“自分で責任を負い切れない”場合は法人プラン必須」というのが、ガバナンス重視の企業現場での結論です。
プレミアムリクエストや従量課金の仕組みは?(TCOの注意点)
有料プランでも、最新AIモデル利用には「プレミアムリクエスト」の月次上限があり、超過分は1回あたり$0.04の従量課金となるため、TCO(総所有コスト)での把握が大切です。
なぜなら、一見「無制限」と書かれたプランでも、最先端AIの多用やエージェント・GitHub Actions連携では想定より出費が膨らみやすいからです。
たとえば、Proなら月300回、Pro+なら1,500回までが基本枠。上限を超えて推論要求すると、その度に課金通知が来ます。大規模プロジェクトや自動化シナリオでよくある「気づけば毎月数千回分の追加分」が意外なコスト増となります。
シミュレーション例:「10人チームでPro+(各自1,500回→合計15,000回)、実際に月18,000回利用=3,000回超過×$0.04=$120の追加費用」など。使い方次第で固定費+変動費を見積もる習慣が、取り返しのつかない請求トラブル防止につながります。
プラン選びで失敗しないための判断基準
当セクションでは、GitHub CopilotをはじめとするAI開発支援ツールの最適なプラン選びについて、ユーザータイプごとの視点や企業導入ならではの要件、そして料金以上の価値を引き出すコツを解説します。
なぜなら、「機能が多そうだから」「安いから」といった曖昧な理由でプランを選ぶと、後悔や追加コスト、法的トラブルなど思わぬ落とし穴にはまることが多いためです。
- あなたはどのユーザータイプ?
- 企業導入時:IP補償/セキュリティ/一元管理が本当に必要か?
- 実務者の声:料金以上の価値を得る活用ワークフロー
あなたはどのユーザータイプ?
自分にぴったりのプランは「ユーザータイプ」で選ぶのが最も合理的です。
なぜならCopilotの料金体系は、個人ビギナー・副業プロ・AIパワーユーザー・企業運用者といったペルソナごとに、最適化されて設計されているためです。
たとえばビギナーや単発の趣味開発なら「Free」、日常的な開発や副業案件を回すなら「Pro」、最先端AI活用や研究開発には「Pro+」、チーム運用や法的リスク対策が不可欠な場合は「Business/Enterprise」を選ぶのがセオリーです。
下記のチャートを自分に当てはめて考えることで、「必要以上に高い・逆に足りない機能を選ぶ失敗」を避けられます。

企業導入時:IP補償/セキュリティ/一元管理が本当に必要か?
法人向けプラン(Business/Enterprise)への切り替えを判断する最大のポイントは「IP補償」と「一元管理&セキュリティ」が会社に本当に必要かどうかです。
なぜなら、個人ProからBusinessプランへの切り替えは、月額コスト以上に自社の法的リスク許容度とアカウント統制の体制に大きな影響を与えるからです。
たとえば「IP補償」(著作権侵害時の補填)は、Business/Enterpriseで有効な公開コードフィルターを事前にONにし、未変更コードについてのみ公式に適用される仕組みです(Microsoft公式: Copilot Copyright Commitment参照)。
日常的に自社のコアコードや商用サービスの一部に生成AIの提案を組み込む場合、「もしもの訴訟時に自社で全責任を背負う覚悟がなければ、Businessプランの保険的価値は実質“必須投資”となります。
規模がある、または複数人が常用するケースでは管理負担や情報漏洩対策、権限設定を一元化する意味でもBusiness移行の合理性が高まります。
実務者の声:料金以上の価値を得る活用ワークフロー
料金の元を取るには、単なる「補完機能」の範囲を超えてCopilotを“業務自動化の起点”として活用することがコツです。
なぜなら、Pro/Businessユーザーになると無制限補完やエージェント機能・GitHub Actions連携が使い放題になり、これを生かして「定型作業のスクリプト自動生成」や「レビュー・テスト・ドキュメント生成の自動化」など業務設計ごと変えられるからです。
筆者自身は、CopilotとCI/CD、ChatOpsを組み合わせて毎月数十時間単位の手動作業を段階的に削減できました。
このように、「投入コスト=単純な開発効率の向上」だけでなく、中長期的にはTCO(総所有コスト)やリスク低減、アウトプット品質の大幅な底上げという“見えにくい付加価値”を得られるのがCopilotプラン選びの真の醍醐味です。
さらに現場実践の導入工夫や自動化成功例については、関連記事「AIコーディング支援ツール徹底比較」でも詳しく紹介しています。
GitHub Copilot導入に関するセキュリティ・著作権・管理のリアル
当セクションでは、GitHub Copilot導入時に必ず押さえておきたい「セキュリティ」「著作権(IP補償)」「管理機能」の実態と、その違いを徹底的に解説します。
これは、Copilot活用が社員一人から組織全体へ広がる過程で、“気軽なAI補完ツール”から“企業資産の安全管理ツール”へと評価軸がシフトするため、どのプラン選択が自社リスクに見合うのか、具体的に見抜く必要があるからです。
- 個人/法人で異なるデータ利用と補償のレイヤー
- IP補償──どこまで守ってくれる?“盲点”を解説
個人/法人で異なるデータ利用と補償のレイヤー
GitHub Copilotのセキュリティや補償は、「個人」と「法人」で根本的に異なります。
その理由は、個人向け(Free/Pro/Pro+)ではユーザーデータやコードの一部がAIモデルや製品改善のために利用されうるのに対し、法人向け(Business/Enterprise)は「IDEプロンプト・チャット内容・コードの保持・学習利用は無し」と明確に制御されるためです。
たとえば、個人でProプランを使っているうちは「自分のコードがAIの改善やトレーニングに使われる可能性がある」点に注意が必要です。これがチームや企業で機密性の高いコードを扱う場合、社外流出リスクや第三者利用の懸念が現実問題となります(実際、個人利用のProアカウントに社内メンバーがバラバラ加入してしまい、後から一括管理やデータ制約が効かず困るケースは後を絶ちません)。
これに対し、Business/Enterpriseプランでは厳格な「非保持・非学習」設定となるうえ、ライセンスやポリシーが一元管理できること、SOC2/ISO 27001認証、監査ログ、SAML SSOによる認証統制など、セキュリティチェックシートの要求項目にしっかり応えます。
つまり、「管理リスク」「データ流出」「法的コンプライアンス」を意識する法人は、個人向けプランとは別物と認識し、プラン選び時は下記の比較マトリックスで要件を精査しましょう。

このように、Copilotを「たまたまAIがあるから使う」から「会社資産を守るIT投資」へ進化させるなら、法人プラン導入へのアップデートを検討しましょう。
IP補償──どこまで守ってくれる?“盲点”を解説
CopilotのBusiness/Enterpriseプランでは、著作権侵害などIPリスクから顧客を守る「IP補償(知的財産の防御)」がつきますが、その中身は意外と条件付きです。
ポイントは、「公開コード一致フィルターを有効&“未変更補完”のみが対象」という2点です。要するに「AIが出したままの提案を、ほぼそのまま受け入れたコードだけ」を補償、さらに公開コードと一致しそうな部分は自動で除外する設定が“必須”。
たとえば、開発現場で推奨コードをもとにちょっと加工(コメントを追記、変数名を変更)した場合、実は補償の範囲外となる可能性すらあります。これは公式ガイドライン(Microsoft Copilot Copyright Commitmentや文化庁・著作権ガイドライン)にも明記されています。
「IP補償さえあれば訴訟も安心」と思いがちですが、実際は開発プロセス全体で“Copilotコードのトレースを識別・証明できる体制”と“社内コードレビュー・IPスキャン”も必要です。保険適用範囲の盲点を理解したうえで、法務や情報システム担当が共同でリスク管理体制を構築し、「補償」+「現場運用」でバランスをとることが大切です。
結論として、IP補償はあくまで最後の安心材料であり、運用設計を怠るとその効果は限定的です。Copilot導入時は、公式FAQや契約約款、文化庁サイトなども事前にチェックし、必要な社内ポリシーとあわせて活用してください。
まとめ
本記事では、2025年夏時点におけるGitHub Copilot料金体系の全容と、個人・法人それぞれの選択ポイント、リスクと導入の決め手となるガバナンス・セキュリティ要件まで網羅的に解説しました。
最も大切なのは、単なる価格比較にとどまらず、将来の生産性、リスクマネジメント、そしてAI活用による自己成長・組織革新までを視野に入れてプランを選ぶことです。
AI時代の新しい“働き方”“学び方”を、まずは自分自身のスキルとマインドセットからアップデートしていく一歩を、今ここから踏み出しましょう。
今のあなたの仕事やキャリアの課題に、AI活用のノウハウとDXの視点を加えたいなら、『生成AI 最速仕事術』が強力な指針となるはずです。
あるいは本格的にAIスキルを身につけたい方は、「Aidemy」のオンラインコーチングも要チェック。新たな技術とプラットフォームの活用で、あなたの可能性を大きく広げていきましょう!