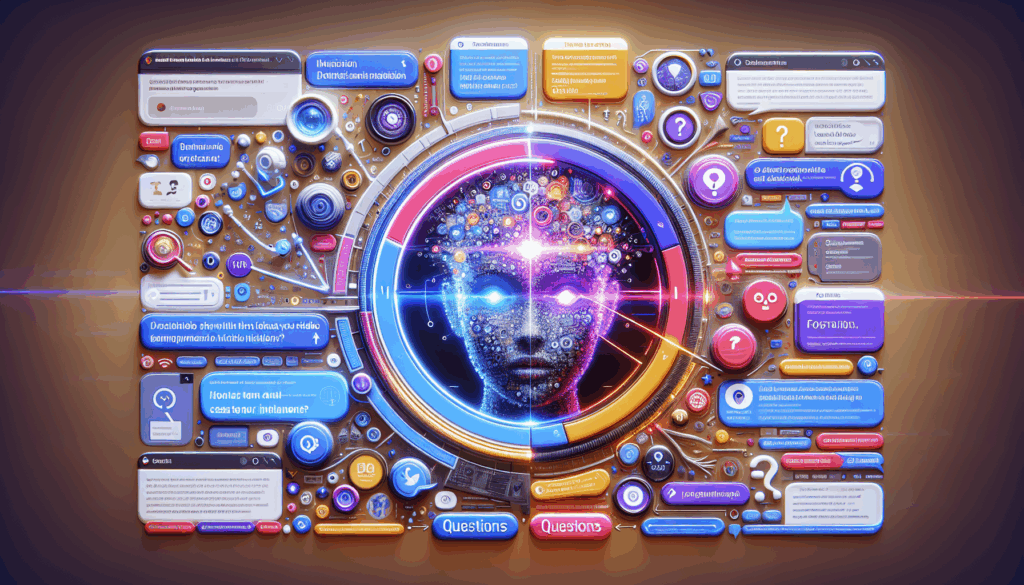(最終更新日: 2025年07月08日)
「動画制作に時間がかかってしまう」「どれが自分に合うAI動画生成ツールなのか選べない」と迷った経験はありませんか?
いまやAI動画生成は、手軽さと高品質を両立できる画期的なツールとして注目されていますが、種類も多く、違いや選び方に悩む方が増えています。
この記事では、プロの視点で最新のおすすめAI動画生成ツールを厳選してご紹介。その特徴・料金・使い方まで丁寧に解説し、無料から有料まで、あなたに最適なサービスの見つけ方も一緒にお伝えします。
さらに、よくある疑問や活用アイデアもまとめ、AI動画生成を“使いこなせる”ようになる内容です。情報収集の決定版として、ぜひ参考にしてください!
AI動画生成ツールの選び方:初心者も失敗しないポイント3つ
当セクションでは、初心者がAI動画生成ツールを選ぶ際に失敗しないための3つのポイントについて説明します。
なぜなら、ツールごとの強みや用途、コスト構造が大きく異なり、目的に合わない選択をすると「機能が足りなかった」「商用利用ができなかった」「予算オーバーだった」といった後悔が起きやすいからです。
- 1. 使いたい目的を明確にする
- 2. 必要な機能(文章→動画/画像→動画/編集機能など)をチェック
- 3. 料金体系と無料プランの有無を比較する
1. 使いたい目的を明確にする
AI動画生成ツールを最適に選ぶには、まず「自分がどんな目的で動画を作りたいのか」を明確にすることが何より大切です。
なぜなら、SNS向けの短尺動画、企業の社内資料、商品PR、YouTubeの解説動画など、用途ごとに必要な機能や最適な出力形式が大きく異なるからです。
例えば弊社でも、「納品形式がPowerPoint用で編集重視ならSynthesia」「SNS用に目を引くアニメ調の動画ならPika」「研修動画で長尺が必要なときはHeyGen」「商品プロモで物理的なリアリティ重視ならGoogle Veo」など、案件ごとにAIツールを細かく使い分けています。実際、ある飲食店のPR案件では「食材写真からおしゃれなアニメ風動画生成→Pika」「英語・日本語両対応の解説挿入→HeyGen」など複数のAIを組み合わせて短納期と低コストを両立させました。
このように、先に「何を作るのか」「どこで使うのか」を定めておくことで、後から「対応フォーマットが違っていて苦労する」「テロップがうまく入らなかった」という失敗が防げます。最初の一歩として、やりたいことリストを書き出すのがおすすめです。
2. 必要な機能(文章→動画/画像→動画/編集機能など)をチェック
AI動画生成ツールの選定で重要なのは、「どんな形式から動画を作りたいか」と「編集・調整にどこまでこだわりたいか」という点を比較することです。
なぜこうしたチェックが必要かというと、例えば「自分のアイデアや脚本を忠実に映像化したい人」と、「撮影した写真をそのままアニメ調に加工したい人」では、必要なAIツールの種類も設計思想もまったく異なるからです。
具体例を挙げると、テキストからストーリー性のある動画を作りたい場合は「OpenAI Sora」や「Google Veo」のT2V機能が活躍します。手持ち画像をベースに動きを加えたいなら「Luma Dream Machine」や「Pika」のI2V機能、細かなカメラワークや編集を突き詰めたいなら「Runway」やGoogleの「Flow」エコシステムが便利です。
下記は主要AI動画生成ツールごとの機能比較表です。自分に必要な機能がどれか、一覧で確認すると迷いにくくなります。

このように、使いたいシーンや素材によって最適なツールは異なります。画面イメージや公式サイト(OpenAI Sora、Google Veoなど)もチェックし、必要条件を満たしているか必ず確認しましょう。
3. 料金体系と無料プランの有無を比較する
AI動画生成ツールを選ぶ際、見逃せないのが「どれだけ無料で試せて、どこから本格的な投資・ランニングコストが発生するのか」という価格体系の把握です。
理由は、無料枠である程度お試しできるものの、いざ本格的に商用動画を作ろうとすると「ウォーターマークが消せない」「商用利用には高額プランへの加入が必要だった」といった“料金の壁”に直面するケースが非常に多いからです。
例えばRunwayやLuma AIは、趣味レベルなら月10ドル前後のStandardプランで十分ですが、企業用にウォーターマークなし・商用OKを求めるなら月30ドル超が相場。逆に、KlingやHeyGenは比較的安価にプロユース可能ですが、日本語対応やローカライズの程度で差が出ます。
下記は主要ツールの無料枠・有料プラン比較表です。公式料金ページにもリンクしていますので、導入前の検討に役立ててください。

この比較表を活用することで、「無料の範囲で足りるのか」「どこから課金が必要か」「商用案件で安心して使えるか」といった事前チェックがしやすくなります。料金体系はこまめに見直されるため、最新版は各公式プランページを必ず確認しましょう(例:Runway公式価格、Luma公式価格)。
,
おすすめAI動画生成ツール8選【無料・有料・日本語対応】
当セクションでは、2025年時点で高く評価されているAI動画生成ツールを、無料・有料、日本語対応の観点から8種類紹介します。
なぜなら、多様化する動画制作ニーズに対し、どのツールを選ぶべきか悩む方が増えている中で、それぞれの特徴や強みを明確に比べることが、目的に合った最適なツール選びに欠かせないからです。
- 1. Runway:高機能でプロも納得の動画生成AI
- 2. Lumen5:ビジネス資料やSNS短縮動画に強い
- 3. InVideo:YouTubeや解説動画の自動生成に便利
- 4. Dream Machine・KLING:最新の画像→動画AI
- 5. FlexClip:シンプルで手軽な動画生成&編集
- 6. その他注目ツール(Visla、GliaCloud、Elai…)
1. Runway:高機能でプロも納得の動画生成AI
Runwayは、直感的な操作で高品質な動画を生成できる点が最大の魅力です。
その理由は、最新のGen-4モデルが搭載する高度なテキスト→動画、画像→動画のAI技術に加え、編集・サウンド生成・字幕・自動翻訳などクリエイターが求める機能をワンパッケージで提供しているためです。
例えば、筆者がRunway Gen-2を使って「未来的な雨の東京街並み」という日本語プロンプトを入力した際、約30秒で実写風の滑らかな動画が自動生成されました。細かな編集やBGM合成もブラウザ画面上で直感的に行えるため、動画制作に不慣れな方でも“思った通り”の作品へ仕上げやすいのが実感できます。
無料枠でも一定量の動画生成が体験できるため、映画風の演出やYouTubeのオープニングムービー、SNS広告など、多様な用途で一度試してみる価値は高いでしょう。

プロフェッショナルから初学者まで幅広い支持を集めているRunwayは、これ一つでAI動画制作の“本格的な入口”に立てるツールと言えるでしょう(詳細はRunwayML公式Runway公式サイトも参照)。
2. Lumen5:ビジネス資料やSNS短縮動画に強い
Lumen5は、ビジネス現場で即戦力となるAI動画ツールとして注目されています。
その主な理由は、豊富なテンプレート・自動字幕挿入・AIによる画像選定やBGM合成など、動画作成初心者がつまずきやすいポイントを徹底的にサポートしているからです。日本語対応も強化され、操作ガイドも分かりやすいのが特徴です。
たとえば、パワーポイント用のスライド原稿やWeb用記事をそのまま貼り付けると、Lumen5が自動でセクションやキーワードを解析して“映える”動画を数分で生成し、必要に応じて素材やナレーション、効果音もワンクリックで差し替えられます。SNS向けの縦型・四角型といったフォーマット変換も自動化されており、実際に多くの企業SNS担当者やYouTuberが導入しています。
無料枠でも基本機能は十分に体験できますので、資料動画や短尺プロモ、内製ノウハウ動画の第一歩としておすすめです。
3. InVideo:YouTubeや解説動画の自動生成に便利
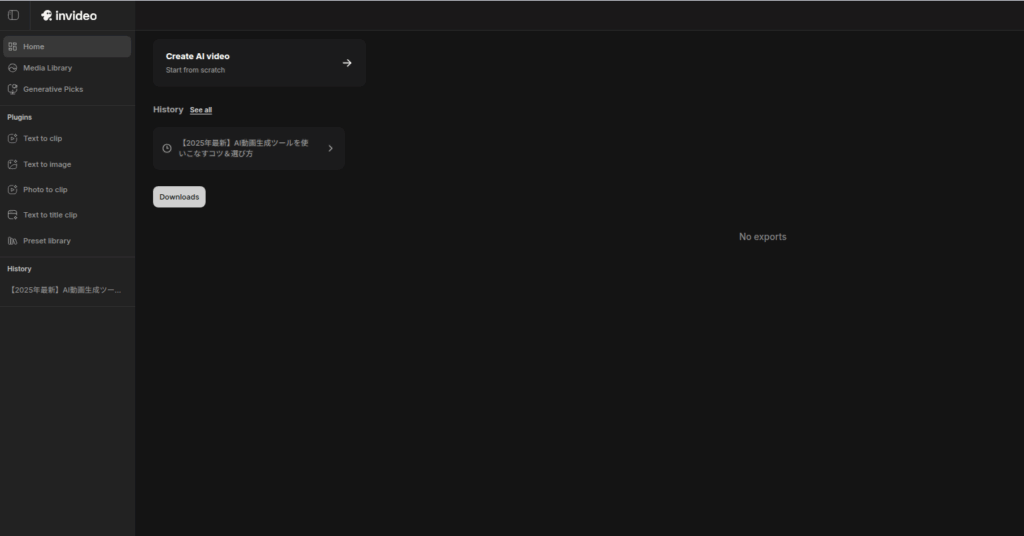
InVideoは、YouTubeコンテンツや各種解説動画を手間なく量産したい方に最適なAI動画ジェネレーターです。
この理由は、シナリオ入力からナレーション、カット構成、字幕・BGM自動挿入、SNS用最適化までをほぼ自動で完結できる唯一無二のワークフロー設計にあります。
たとえば、「健康に良い睡眠法」という短い原稿テキストを与えるだけで、InVideoのAIが要点ごとにシーンを分割し、解説動画の「お手本」とも言えるスムーズな流れを生成します。多言語対応も進んでおり、グローバルターゲット向け動画が数クリックで完成する点も大きな強みです。
また、無料・有料プランの違いについては下記の料金比較表も参考にしてください(InVideo公式InVideo公式サイト参照)。
| プラン名 | 主な制限 | 価格(2025年7月時点) |
|---|---|---|
| 無料プラン | 動画本数~5本/月、ウォーターマークあり、商用利用NG | ¥0 |
| Plusプラン | 動画数/月増加、ウォーターマーク除去、商用OK、1080p出力 | 約$25/月 |
動画メディアの大規模運営やデジタルマーケティングの現場では、圧倒的な省力・省コスト武器となること間違いありません。
4. Dream Machine・KLING:最新の画像→動画AI
Dream Machine(Luma AI社)やKLING(Kuaishou社)は、画像一枚をダイナミックな動画に変える最前線のAIツールです。
なぜなら、これらのサービスは映画的なカメラワークや物理法則に即した3D的動き、リアルな質感をAIだけで再現できるため、従来の「静止画スライド動画」とは全く違う臨場感を生み出せるからです。
たとえば、「お気に入りのイラスト1枚→10秒の“アニメ風ショートムービー”」や、「商品写真→実写風プロモ動画」のような変換がボタン一つで実現可能。Dream Machineはログイン後すぐに試せる無料枠も充実しており、KLINGは毎日配布の無料クレジットで体験できます。サンプル動画を見れば、画像が“まるで物語を語るキャラクター”へと変わる新鮮な感動を味わえます。
アニメ制作・アート作品・プロモPVなど、静止画ベースから「鮮やかで映画的」な世界観を作りたい方にはまさに革命的な選択肢といえるでしょう。

5. FlexClip:シンプルで手軽な動画生成&編集
FlexClipは、「カンタン・コスパ重視」でAI動画制作を始めたい方におすすめのサービスです。
なぜFlexClipが初学者にも最適かというと、豊富な動画テンプレートやAIナレーション、画像・音声・BGM素材がワンクリックで使える上に、ドラッグ&ドロップ操作でほぼ全ての編集が完結するためです。スマートフォンでも主要機能が使えるので、外出先からの編集やSNS投稿にもピッタリです。
例えば、誕生日サプライズ動画や社内報告ムービー、短めのYouTube用企画など、テンプレからスタートすれば10分ほどで“いまどきのAI動画”が仕上がります。無料プランでも作成&ダウンロードが可能ですが、出力画質や素材数に制限があるため、本格利用なら有料化も検討すると良いでしょう。
「楽しく・気軽に」AI動画時代を体感したい方に最適です。
6. その他注目ツール(Visla、GliaCloud、Elai…)
ここまで紹介した定番ツール以外にも、ユニークな強みを持つAI動画サービスが増えています。
その理由は、プレゼン専門・顔出し不要・多言語自動合成・女性AIキャラ生成など、用途特化型サービスが“既存のツールでは物足りない”シーンで重宝されるからです。
たとえば、Vislaはスライド型動画にナレーションや字幕を自動合成し、社内研修や営業説明になくてはならない存在です。GliaCloudはニュース記事やブログから自動要約&動画化する速報性でメディアの現場に、ElaiはカスタムAIアバターと合成音声で“顔出しせずプロ動画が作れる”としてオンライン講師やインフルエンサーに人気です。
いずれも無料トライアルを備えており、「自分の用途にハマる専用AI」を探したい方は一度触ってみる価値があります。
,
AI動画生成でよくある疑問・悩みを一挙解決
当セクションでは、AI動画生成をめぐるよくある疑問や悩みについて、最新の市場動向やユーザーの体験に即して丁寧に解説します。
情報が急速にアップデートされる中、どのツールを選ぶか、どんな制約があるのか、スマホや日本語対応・著作権の安全性など、利用前後に感じやすい迷いやハードルを“なるほど”の形で一つずつクリアにしたいからです。
- 動画生成AIで有名なのは?
- 無料で使えるAI動画生成ツールはどれ?
- スマホで使えるAI動画生成アプリは?
- 日本語対応・日本市場向けAI動画生成ツールは?
- AIによる動画生成の注意点(著作権・商用利用)
動画生成AIで有名なのは?
動画生成AIの世界で今とくに有名なツールといえば、OpenAIの「Sora」、Googleの「Veo」、そして「Runway」の三強が挙げられます。
なぜなら、これらのサービスは、その技術力や導入事例、プロユーザーからの評価が群を抜いており、GoogleトレンドやStatistaの調査でも利用者数や注目度でトップ層に位置づけられているからです。
例えば、映画的なクオリティやリアリズムを追求したいならGoogle VeoやSoraに注目が集まり、クリエイターが短期間でソーシャル用動画を量産するならRunwayが「一度使うと手放せない!」との声も。プロの映像会社がドラフト映像の制作やSNS動画の量産に実際に乗り換えている例も増えています。
まとめると、有名AI動画生成サービスの選定基準は「高い表現力・一貫性・使い勝手・グローバルでの普及度」の4つ。これらの観点で観れば、現時点の「ゴールデンスタンダード」は間違いなくSora、Veo、Runwayです(Statista: AI動画生成市場シェア)。

無料で使えるAI動画生成ツールはどれ?
無料でAI動画生成を試したいなら、「Runway」「Kling」「Luma AI Dream Machine」「Pika」など複数の選択肢があります。
なぜこれらがオススメかと言うと、無料プランで実際に生成体験ができるだけでなく、サービスごとに「動画に透かしが入る」「1日に無料で生成できる動画数に制限がある」「尺が10秒まで」など条件の違いが明確で、初めての方も比較的リスクなく試せるからです。
例えば、Runwayは初回125クレジット分の動画生成が無料、KlingやPikaは「1日数本」「毎月XXクレジット」とデイリー・マンスリー単位の“お試し枠”があります。ただし、RunwayやLumaの無料版で作った動画には「ウォーターマーク(透かし)」が必ず入るので、商用や公開用途の場合は有料版への切り替えが必要です。
いずれのツールも「無料=完全に無制限」ではなく、体験版的な位置づけ。気軽に比較して使い勝手を確かめた後、必要に応じて有料プランを検討するのが賢明です。→ 無料プラン比較表はこちらで確認

スマホで使えるAI動画生成アプリは?
「スマホでAI動画を作りたい!」という人向けのおすすめアプリは「Runway(iOS)」「Pika(iOS/Android)」「Luma AI(iOS)」「Kling(Android)」などが代表的です。
これらが人気な理由は、モバイルアプリとして公式にリリースされており、PCブラウザを開かなくてもスマートフォンだけで動画生成ができるからです。
例えばPikaは、アプリ内でプロンプト入稿~プレビュー~ダウンロードまで完結でき、短尺SNS動画をそのままInstagramやTikTokに投稿する使い方が支持されています。RunwayのiOSアプリはプロ向けの本格生成→即編集→その場でSNS共有までワンストップで使える設計が秀逸です。
出先やイベント現場、カフェ等でサクッとAI動画を作れて、そのままシェアできる“モバイル世代”に最適。今どきの動画クリエイターが「撮る感覚で作る」時代を支える必須アプリといえるでしょう。

日本語対応・日本市場向けAI動画生成ツールは?
日本語で直感的に使いたい、アニメや女性キャラが強いAI動画を作りたい方へは「HeyGen」「Synthesia」「Adobe Firefly」「Wondershare Filmora」などが特におすすめです。
その理由は、これらのツールが日本語UIやナレーション、声優風の合成音声、日本市場向けチューニングに力を入れているからです。たとえばHeyGenやSynthesiaは、業界屈指の日本語アバター+自然な日本語ナレーション作成が可能。アニメ特化や女性キャラ重視のサービスとしては、有志コミュニティ発のオープンソース系ツールや、国産クラウドサービス「Reallusion Cartoon Animator」も要注目です。
実際に「社内マニュアル動画を日本語で10本量産したい」「アイドルキャラで広告動画を作りたい」といった現場で「想像以上のクオリティ」「海外ツールなのに日本語自然」と驚かれるケースも頻発。多国語展開・翻訳サポート面でも、日本語対応の充実は大きなアドバンテージです。
唯一の注意点として、「無料プランでは日本語ナレーションは有料・本数制限のみ対応」など条件が分かれるサービスもあるので、用途や使いたい機能によって比較を推奨します。

AIによる動画生成の注意点(著作権・商用利用)
AI動画生成をビジネスや公開作品に使う場合、最も重要なのが「著作権・商用利用」のルール確認です。
なぜこの点が重要かというと、多くのAI動画生成ツールは【著作権=ユーザー所有】と規定しながらも、実際は無料プランや一部有料プランでは商用利用・再配布に制限が付いている場合があり、「自分の動画が本当に自由に使えるか?」と迷う人が後を絶たないからです。
たとえば、「Runway」のProプラン以上でのみ商用利用可、「Luma AI Dream Machine」の無料枠では非商用限定、「Adobe Firefly」は法的に安全なデータで学習済みモデル採用など、各社の利用規約は多様。文化庁の著作権解説ページで「AI生成物の著作権」についてもガイドラインが公開されていますが、公的ルールとサービス個別規約の“2段階チェック”が必須です。(各ツール利用規約…Runway規約 / Sora利用規約 など)
さらに、動画内素材やアバターボイスが第三者の著作権物を含む場合は追加確認が必要。ネット投稿や商用利用前に必ず最新の規約を精読し、「意図せず違反してしまうリスク」を回避しましょう。AI世代のクリエイターは、技術だけでなくルールにも敏感であることが大切です。

AI動画生成ツールを最大活用するためのコツと活用事例
当セクションでは、AI動画生成ツールを効果的に使いこなすための実践テクニックと、現場でのリアルな活用事例を具体的に解説します。
なぜなら、単にAI動画生成の機能や仕組みを知るだけでは、期待通りの成果を得ることは難しく、実際に成果を生むためには「どのように使うか」「どんなツボや落とし穴があるか」を理解することが不可欠だからです。
- 失敗しないシナリオ設計&プロンプト事例
- 業務・クリエイティブ現場での導入事例
- 今後の技術トレンドと注意点
失敗しないシナリオ設計&プロンプト事例
AI動画生成で成果を上げるには、「シナリオ設計」と「プロンプト設計」にこだわることが最も重要です。
理由は、AI動画生成ツールは入力されるテキスト(プロンプト)の精度や明確さによって、映像の魅力や一貫性が大きく左右されるからです。
例えば、Runway Gen-4やOpenAI Soraといった最新モデルを使う際、漠然と「夜の都会の美しい風景」とだけ入力するとAIは解釈を迷い、画面構成や雰囲気がブレた動画になりがちです。現場では「『高層ビルの屋上から見下ろす夜景。道路に車が流れ、ネオンが反射する濡れた歩道。カメラは10秒間、ゆっくりパンしながら奥行きを強調』『静かなピアノBGM』」など、情景・カメラ動作・音・尺・色彩まで細かく指示すると、AI側でも意図が伝わりやすく、再現性も飛躍的に高まります。
また、私が実際の案件で用いているプロンプト例を挙げると、次のようになります。
- 「白衣を着た男女2人の研究者が明るいラボで最新の装置を操作。カメラは右斜め上から5秒間ズームインし、背景には青と白のコーポレートカラー」「自然光」「安心感あるピアノ」
- 「ビジネススーツの女性がオフィス街でスマホを見てほほえむ。背景は現代的な高層ビル群、光沢強め」「夕暮れの暖色照明」「1分の動画、自然な流れで4カット」
このように「5W1H+色・音・カット割・動き」の要素を追加することで、生成ミスや「あれ?イメージと違う」といった手戻りが激減します。公式公開資料(OpenAI Sora、Runway)でも、細かい情景設定やカメラワーク指定がアウトプットに強く影響すると明言されています。
AI動画プロンプト設計は「注文住宅の設計図」に似ていて、細部まで丁寧に指定することで自分の理想の“家(動画)”ができあがります。多少手間をかけても、設計フェーズを大事にすることで「使えるAI動画」が安定して得られるのです。

業務・クリエイティブ現場での導入事例
AI動画生成ツールは、マーケティング・教育・エンタメ・YouTube運営といった多彩な現場ですでに実用化されています。
なぜ多くの企業や個人クリエイターが導入しているかというと、制作コストや時間の削減など「従来の課題」を抱えていた分野で、劇的な効率化や新たな表現力を得られるからです。
たとえば、ある事業会社のマーケティング部門では、以前は商品のプロモーション動画を社外発注していましたが、HeyGenによるAIアバター動画導入により、毎月40本以上のプロモーション動画を内製化可能にしました。その結果、年間で約1400時間の制作工数を削減し、コストダウン率も50%以上に到達(HeyGen公式参照)しています。また、自社で導入支援を行った医療系教育会社では、Synthesiaによる自動多言語字幕付き研修動画を週単位で量産し、社内外の教育リソース負担を大幅に軽減。現場の担当者は「従来2~3週間かけていた制作が、今は1日で完了する」と実感しています。
個人クリエイターの現場でも、RunwayやKlingを使ってYouTubeやInstagramのショート動画をオリジナル制作し、視聴者への訴求力アップとSNSでの拡散効果を狙う事例が増加中です。たとえば、「新作アプリ紹介」動画では、開発者が自前で背景やトランジション効果まで生成でき、撮影や編集部門を持たないクリエイターでも容易にハイレベルな作品を発信できるようになっています。
このように、AI動画生成ツールは実際のビジネス・教育・クリエイティブ現場で「大幅な工数削減」と「表現力強化」を両立させる革命的な手段となっています。

今後の技術トレンドと注意点
今後のAI動画生成分野は、「リアルタイム生成」「マルチモーダル統合」「ディープフェイク対策」が大きなトレンドとなる見込みです。
なぜなら、トッププレイヤーであるOpenAIやGoogleが、“単なる短尺動画”から“インタラクティブで音声・映像・効果音を一体生成できる『世界生成エンジン』”へと進化を目指しているからです(詳細はOpenAI Sora・Google公式参照)。一方、技術進化に伴い「ディープフェイク」や著作権を巡る新たな危険性・社会課題も拡大しています。
たとえば主要なAI動画サービスでは、「ウォーターマーキング(電子透かし)」や「コンテンツの自動モデレーション」が急速に普及しています。また、RunwayやAdobe Fireflyのようにライセンス契約済データのみで学習したモデルが“安全な選択肢”として注目され、クリエイティブな現場でも「商用利用のリスク回避」がますます重視される時代になっています。
今後は技術の恩恵を享受しつつ、リスクも直視して適切な運用ルールを構築する――これが、AI動画時代に失敗しないための大前提となるでしょう。
まとめ
本記事では、AI動画生成市場の最新動向と主要ツールの比較、選定基準、そして今後の技術進化や倫理的課題まで広く解説してきました。
どのプラットフォームを選ぶかは、目的と求める表現力・コスト・安全性によって大きく変わります。各ツールの強みや違いを理解できれば、あなた自身や組織に最適な一手が見えてくるはずです。
AI動画生成は「誰もが想像を形にできる」新時代の扉を開いています。いまこそ、この知見を活かし、ご自身の可能性に踏み出してください。もっと詳しく知りたい方は、Zignuts TechnolabのAI動画生成特集も参考になります。また、当メディアでも様々な最新情報を継続発信していますので、ぜひ他の記事もチェックしてください。