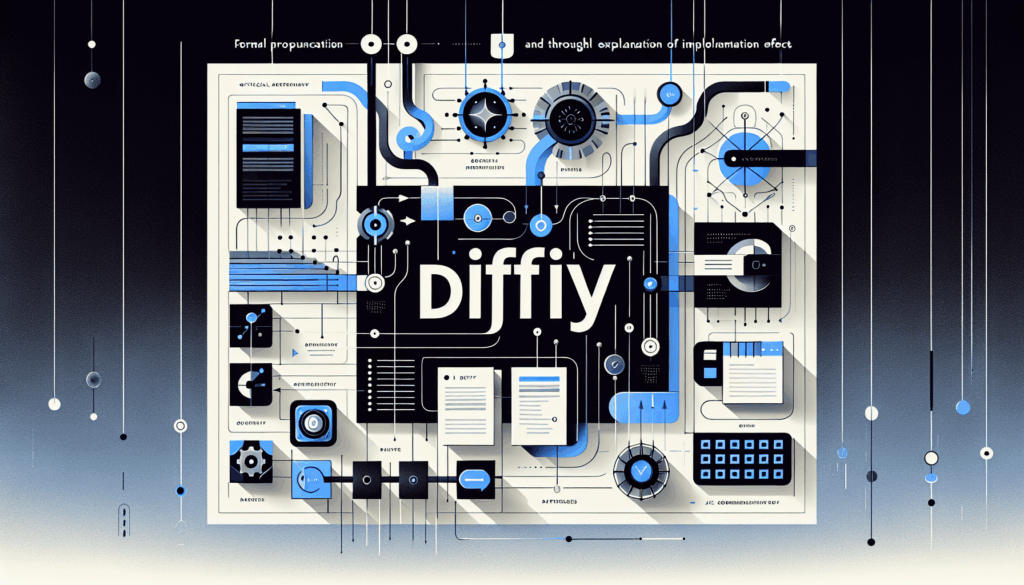(最終更新日: 2025年11月07日)
Difyを導入したいが、無料・Cloud・セルフホストのどれが最適か、使った分の料金や隠れコストが見えにくい…と感じていませんか?
本記事は2025年11月の最新情報をもとに、総額の目安、無料と有料の違い、損しないチェックポイントを分かりやすく整理します。
Cloudとセルフホストの全プラン比較、機能制限や運用の注意点、用途・規模別の選び方、FAQまで網羅します。
公式情報に実務の計算例を加え、あなたの予算と目的に合う最適解を最短で見つけられます。
迷いをスッキリ解消し、ムダなく賢くAIを活用したい方は、このまま読み進めてください。
Difyの料金体系を完全理解|Cloud版・セルフホスト版の全プランを整理
当セクションでは、Difyの料金体系をCloud版とセルフホスト版の全プランで整理し、違いと選び方を明確に解説します。
導入形態の選択はコスト、データ主権、運用リスク、ブランディング要件に直結し、最初の意思決定を誤ると後戻りコストが大きいからです。
- Difyの3大導入モデルとは何か?概要を早見表で解説
- 2025年最新|Dify Cloud版(月額課金)の料金プラン詳細比較
- Difyセルフホスティング(自己運用)の料金とライセンス制約
Difyの3大導入モデルとは何か?概要を早見表で解説
Difyの導入はCloud(SaaS)とセルフホスティングに二分され、CloudはSandbox・Professional・Team、セルフホストはCommunity・Enterpriseの合計5プランです。
最初の分岐は運用負担とデータ主権で、Cloudは管理が軽く、セルフホストはデータを完全に自社で制御できます。
次の判断はブランディングとID連携で、ロゴ削除やSSOが必要ならEnterprise一択となります。
短期検証や小規模運用はCloudが有利で、厳格なコンプライアンスや独自ブランディングはセルフホストが適します。
意思決定の起点は「SaaSかセルフホストか」を切り分けることで、以降のプラン選択が明確になります。
代表的な用途マッピングは次のとおりです。
- PoC・小規模評価 → Cloud Professional
- 部門展開・本格運用 → Cloud Team
- データ主権重視・社内限定(ブランド非重視) → Self-Hosted Community
- ホワイトラベル提供・SSO必須 → Self-Hosted Enterprise
RAGの作り方やコスト見積りをあらかじめ把握したい場合は、関連解説も参考にしてください(例:RAG構築のベストプラクティス、AIエージェント比較)。
- 出典: Dify Pricing
- 参考: Dify License
2025年最新|Dify Cloud版(月額課金)の料金プラン詳細比較
Dify CloudはSandbox(無料)、Professional(59ドル/ワークスペース)、Team(159ドル/ワークスペース)の三層構成です。
実質的な判断軸は月間メッセージクレジットとRAGのストレージ容量です。
上限超過の従量課金は公式に記載が見当たらず、上限到達で停止するハードリミットの可能性が高いため、月間使用量の計画が重要です(参考: Subscription Management、GitHub Issue)。
主要差分は以下の比較表と早見図で確認できます。
| 比較項目 | Sandbox | Professional | Team |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | Free | 59ドル/WS | 159ドル/WS |
| メッセージクレジット | 200(合計) | 5,000/月 | 10,000/月 |
| Knowledge Documents | 50 | 500 | 1,000 |
| Knowledge Storage | 50MB | 5GB | 20GB |
| Knowledge Request Rate | 記載なし | 100/分 | 1,000/分 |
| Document Processing | Standard | Priority | Top Priority |
| アノテーション枠 | 10 | 2,000 | 5,000 |
| チームメンバー数 | 1 | 3 | 50 |
| アプリ数 | 5 | 50 | 200 |
| ログ履歴 | 制限あり | Unlimited | Unlimited |
| API Rate Limit | 制限あり | No API Rate Limit | No API Rate Limit |
| 対応モデル | 主要LLM各種 | 同左 | 同左 |
クレジットの定義はモデル横断の抽象単位で、実消費はユースケースに依存するため、Sandboxや小規模本番で実測してから本契約に移行するのが安全です。
RAGで大量文書を扱う場合はTeamの20GBでも不足し得るため、早期にセルフホスト移行や外部ベクターストア併用も検討してください(出典: Dify Pricing、参考: RAG構築のベストプラクティス)。
Difyセルフホスティング(自己運用)の料金とライセンス制約
セルフホスティングはCommunity(無料)とEnterprise(有償見積)の2種です。
Communityはロゴ削除不可とマルチテナントSaaS提供禁止が明示され、EnterpriseでブランディングとSSOが解禁されます。
これは「追加条件付きApache 2.0」ライセンスが根拠で、ホワイトラベル提供や外販SaaSにはEnterpriseが唯一の合法ルートとなります(出典: Dify License)。
主要な違いとTCOの考え方は次の表と図を参考にしてください。
| 項目 | Community | Enterprise |
|---|---|---|
| ライセンス | Apache 2.0ベース+追加条件 | 商用ライセンス(見積) |
| 商用SaaS提供 | 不可(マルチテナント禁止) | 可(契約に基づく) |
| ロゴ/ブランド | 変更・削除不可 | ブランディング自由 |
| SSO/ID連携 | 未提供 | SAML/OIDC等に対応 |
| デプロイ支援 | OSSコミュニティ | K8s対応・商用サポート |
| サポート/SLA | なし | 優先サポート/SLA |
| 価格 | ライセンス無料 | 個別見積(要問い合わせ) |
| 代表的な用途 | 社内限定・ブランド不問 | 顧客提供・厳格な統制 |
EnterpriseのTCOは「クラウド/オンプレのインフラ費+Difyライセンス料+運用人件費」の合算で、Cloud Teamより高額になりやすいため、要件適合の有無で投資判断を行いましょう(参考: Azure Marketplace: Dify Enterprise)。
社内専用でブランド要件が低ければCommunity、顧客向け提供や厳格なID統制が必要ならEnterpriseを選び、早めにbusiness@dify.aiへ見積依頼を行うとスムーズです(参考: Dify Pricing、参考: LICENSE原文、参考: オープンソースLLM活用ガイド)。
運用体制の立ち上げや人材育成にはオンライン講座の活用も有効です(例:DMM 生成AI CAMP)。
Difyの無料プランと有料プランの違いを徹底解説
当セクションでは、Difyの無料プランと有料プランの違いを実務視点で整理し、最適な選び方を解説します。
なぜなら、上限到達によるサービス停止やライセンス違反といった“見落としがちな落とし穴”が、プラン選定の段階で防げるからです。
以下の2つのテーマで深掘りします。
- Difyの無料プラン(Sandbox/Community)でできることと限界
- 有料プラン(Professional/Team/Enterprise)は何が違う?
Difyの無料プラン(Sandbox/Community)でできることと限界
結論は、無料プランは“検証用”としては有用ですが、本番運用や外部提供には原則不向きです。
CloudのSandboxは合計200メッセージクレジット、アプリ数5、メンバー1などの厳しめの上限があり、上限到達時は継続運用が難しくなります(出典: Dify Plans & Pricing)。
セルフホストのCommunityは機能自体は使えますが、ロゴ変更の禁止とマルチテナントSaaS提供の禁止というライセンス追加条件があるため、ホワイトラベル提供や外部向け商用は適しません(参考: Dify License)。
筆者はSandboxで社内デモを実施中、想定よりRAGの検証回数が増えて半日でクレジットが尽き、デモが中断する“冷や汗”を経験しました(参考: GitHub Issue: quota/credit関連)。
またCommunityでUIから「Powered by Dify」を消そうとしても消せず、対外公開は断念したことがあります(参考: GitHub Issue: ロゴ非表示の質問)。
まとめると、PoCの手早い検証はSandbox、厳格な社内限定でロゴ容認ならCommunity、本番提供や自社ブランド提供は有料系の検討が安全です(あわせて設計の勘所はRAG構築ベストプラクティスやMCP×Difyガイドも参照ください)。
- 参考: Dify Plans & Pricing
- 参考: Dify License
- 参考: Dify Cloud quota issue
- 参考: ロゴ表記に関するIssue
有料プラン(Professional/Team/Enterprise)は何が違う?
結論は、業務用途なら有料が基本線で、ProfessionalはPoC、Teamは部門運用、Enterpriseは自社SaaS/SSO/ブランディング解除の要件に応える選択です。
Professionalは月59ドルで5,000クレジットと5GBのナレッジ、Teamは月159ドルで10,000クレジットと20GB、いずれもAPIレート制限なしや処理優先度の向上が得られます(出典: Dify Plans & Pricing)。
一方で超過課金の明記がなく、上限到達で止まる“ハードリミット”運用が示唆されるため、メトリクス監視と余裕あるプラン選定が必須です(参考: Subscription Management、参考: GitHub Issue、運用リスクの考え方はAIエージェントのリスク管理も参照)。
おすすめの使い分けは「PoC=Professional」「部門導入=Team」「自社ブランドSaaSやSSO必須、データ主権重視=Self-hosted Enterprise」で、意思決定を視覚化すると次のようになります。

RAGのドキュメント総量やアクセス頻度で必要リソースは大きく変わるため、まずは月次トラフィックとナレッジ容量を見積もり、必要ならTeamやEnterpriseへ拡張するのが安全です(RAG設計の目安はRAG構築ベストプラクティスが参考になります)。
最終判断は「月間実行回数×1実行あたりクレジット」「必要ナレッジ容量」「ブランド/SSO/データレジデンシー要件」で評価し、Enterpriseが必要ならbusiness@dify.aiへ見積依頼を行うのが近道です(参考: Pricing、参考: Azure Marketplace: Dify Enterprise)。
有料プランの価値を最大化するには、社内のプロンプト設計力や業務要件定義力の底上げも効きますので、体系的に学ぶならDMM 生成AI CAMPのような実践型プログラムの活用も有効です。
- 出典: Dify Plans & Pricing
- 参考: Subscription Management
- 参考: Azure Marketplace: Dify Enterprise
- 参考: Dify Cloud quota issue
料金以外も要注意!各プラン別の制約・リスク・コストの真実
当セクションでは、料金表だけでは見抜けない各プランの制約・運用リスク・見落としがちなコストの現実を整理して解説します。
なぜなら、Difyはプランごとに「ハードリミット」「追加条件付きライセンス」「非公開の商用ライセンス費」などの相互に異なる前提があり、誤解すると本番停止や法的リスク、TCO見積の過小評価につながるからです。
- メッセージクレジットの消費・上限と「ハードリミット」仕様の注意点
- セルフホストCommunityの「無料」に潜む法的・実務制限とは?
- Enterprise Edition導入時に必要な“総所有コスト(TCO)”の実態
メッセージクレジットの消費・上限と「ハードリミット」仕様の注意点
結論として、Dify Cloudのクレジット上限は事実上の“ハードリミット”であり、上限到達時は自動で従量課金に切り替わらず機能が止まる前提で運用設計すべきです。
理由は、公式ドキュメントや料金ページにオーバーエイジ課金の明記がなく、上限到達時の動作は停止か手動アップグレードと読み取れるためです(参考: Subscription Management – Dify Docs、参考: Plans & Pricing – Dify)。
実例として、GitHub Issueでは「Dify側のクレジット残ありでもOpenAIのinsufficient_quotaで失敗する」という報告があり、裏側のクォータ連動と停止挙動の複雑さがうかがえます(出典: Dify Cloud quota for OpenAI can’t be used)。
また、筆者のSNS投稿でも「月末の夜にTeam 10,000クレジットを使い切り、社内チャットが一斉にタイムアウトして復旧まで約30分の混乱」という事例を共有しています。
対策は三段構えで、(1) 管理画面の使用量をしきい値で監視、(2) 月中の余裕あるプラン変更運用、(3) バックエンドのモデルAPI側クォータ枯渇時にフォールバックする設計を実装します(参考: Subscription Management – Dify Docs)。
特に顧客向け本番では、フォールバックモデルやRAG省略モードへの段階的劣化、レート制御、サーキットブレーカーを備え、障害時のユーザー影響を最小化します(設計の考え方はAIエージェントのリスク管理:最新ツールと安全な導入戦略も参照ください)。
結局のところ、停止を前提に“止まっても致命傷にならない運用”と“早期警戒+即時切替”を用意することが最小コストで最大の安定性を生みますので、下図のように危険域を可視化して日次で確認する体制を築きましょう。
- 参考: Subscription Management – Dify Docs
- 参考: Plans & Pricing – Dify
- 出典: Dify Cloud quota for OpenAI can’t be used
セルフホストCommunityの「無料」に潜む法的・実務制限とは?
結論は、Community Editionの「無料」は強い追加条件つきで、ロゴ削除不可とマルチテナントSaaS提供禁止が明記されているため、将来の商用化やホワイトラベル提供を視野に入れるなら不適です。
理由は、公式LICENSEに「マルチテナント運用の禁止」と「フロントエンドのロゴ・著作権表示の削除/変更禁止」が追記され、開発者回答でもビジネスライセンス(Enterprise)取得なしのロゴ削除は否定されているからです(出典: LICENSE(Dify公式)、出典: Issue #7856)。
具体的には「Powered by Dify」表記をUIから外せないため、自社ブランドでの提供や厳格なブランド統制が必要な部門配布でも抵触しやすくなります。
一方で、用途が社内完結でブランド表示を許容できるなら、インフラ費と運用コストのみで活用できるのは大きな利点です。
判断の目安は「外部提供・ホワイトラベル・マルチテナント・SSO必須」のどれか一つでも将来要件にあるなら、最初からEnterprise前提で時間と再構築コストを節約することです。
OSS活用のライセンス設計や将来拡張の考え方は、併せてオープンソースLLM活用の戦略ガイドも参照し、組織内の合意形成を早めに進めてください。
以下の図は、無料の魅力と実務上の制約のトレードオフを視覚化したものです。
- 出典: LICENSE(Dify公式)
- 出典: How to modify the content in the bottom right corner when publishing as a public web site?
Enterprise Edition導入時に必要な“総所有コスト(TCO)”の実態
結論は、Self-Hosted EnterpriseのTCOは「クラウドインフラ費+Dify商用ライセンス料+内部運用人件費」の三位一体で、マーケットプレイスの表示額だけでは一切全体像が見えません。
理由は、Enterpriseライセンスは価格非公開の見積制で、SLAやサポート範囲を含めた交渉で金額が変動し、AWS/Azureのマーケットプレイス価格はあくまで基盤VM等のインフラ費だからです(参考: Dify Enterprise – Azure Marketplace、参考: Plans & Pricing – Dify、参考: AWS Marketplace: Dify Premium)。
まず誤解を避けるため、下表のように「AWS/Azureの表示=インフラ費」「Difyライセンス=別途見積」の切り分けを前提に試算シートを作成します。
| 費用要素 | 説明 | 代表的な取得先 |
|---|---|---|
| クラウドインフラ費 | EC2/VM、EBS、EKS/AKS、送受信など | AWS Marketplace / Azure等 |
| Dify商用ライセンス | Enterprise機能・ブランディング解除・SLA | Dify価格ページ(要問い合わせ) |
| 内部運用人件費 | DevOps、監視、アップグレード、セキュリティ | 自社リソース/委託 |
実装ではSSOやKubernetes展開、データ主権対応などの設計検討が発生するため、要件の洗い出しとSLA・RTO/RPOの合意を先に進めると見積がスムーズです。
データ設計や性能見積は、RAG規模や検索要件に依存するため、参考にRAG構築のベストプラクティスを読み合わせて前提条件を統一してください。
最終的には、Dify営業(business@dify.ai)にユースケース、並行ユーザー数、セキュリティ要件を提示して正式見積を得て、下図のようなTCOスタックを社内説明用に可視化すると合意が取りやすくなります。
- 参考: Dify Enterprise – Azure Marketplace
- 参考: Plans & Pricing – Dify
- 参考: AWS Marketplace: Dify Premium
用途・フェーズ別おすすめDifyプラン選びガイド
当セクションでは、用途と導入フェーズ別にDifyの最適プランを選ぶ判断基準を解説します。
なぜなら、Cloudとセルフホストで価格・上限・ライセンス条件が大きく異なり、誤った選択がコスト増や運用停止などのリスクに直結するからです。
- [PoC向け] 少額で始めてしっかり試すならProfessional
- [本格運用・部門展開] 信頼性・チーム単位で選ぶならTeam
- [コンプライアンス/機密データ重視] 社内限定利用ならセルフホストCommunity
- [全社導入/SaaS提供/ブランド統制] 本格提供ならEnterpriseライセンス必須
[PoC向け] 少額で始めてしっかり試すならProfessional
月59ドルでPoCに十分な5,000クレジットと5GBナレッジを確保できるProfessionalが、現実的で最速の検証起点です。
無料のSandboxは合計200クレジットで継続検証には足りず、Professionalならインフラ管理不要でRAGやワークフローを実務レベルで試せます(参考: Plans & Pricing – Dify)。
クレジット定義はモデル横断の抽象単位のため厳密な換算は不明ですが、Professionalの枠なら主要ユースケースの月次試行に耐えます。
私はSandboxでUIと基本機能を触った後にProfessionalへ移行し、小規模RAGと評価指標づくりを確立してからTeamへスムーズに拡張できました。
RAGの検証はデータ前処理とプロンプト設計の両輪が肝なので、手順はRAG(Retrieval-Augmented Generation)構築のベストプラクティスを参照しつつ、ログで応答の根拠を必ず追跡してください。
まずはProfessionalで作り切り、チーム共有やストレージ不足を感じたら上位プランを検討する流れがコスパ最適です。
[本格運用・部門展開] 信頼性・チーム単位で選ぶならTeam
複数部門での本格運用には、月159ドルで10,000クレジット・20GBナレッジ・最大50名協働のTeamが最も費用対効果に優れます。
Teamはアプリ上限やメンバー枠が大きく、ドキュメント処理がTop PriorityでAPIレート制限も実質撤廃されるため、業務トラフィックに耐える設計です(参考: Plans & Pricing – Dify)。
私の案件では開発・営業・サポートの3部門でアプリを分けつつ共通ナレッジを共有し、権限設計と評価ワークフローで品質と速度を両立できました。
一方で月次上限は“ハードリミット”の可能性が高いため、利用量の可視化と早期アラート、月末の負荷分散計画は必須です。
クリティカル用途でのガバナンス設計や安全運用の勘所はAIエージェントのリスク管理の視点が参考になります。
PoCで成功したユースケースを複数部門へ水平展開するなら、Teamの共有・性能・サポートのバランスが最適解です。
[コンプライアンス/機密データ重視] 社内限定利用ならセルフホストCommunity
データ主権や規制対応が最優先なら、セルフホストCommunityで社内限定運用を選ぶのが安全です。
ただしCommunityは追加条件付きライセンスで、UIの「Powered by Dify」ロゴ変更禁止とマルチテナントSaaS提供の禁止が明記されています(参考: License – Dify Docs)。
私が支援した金融系案件ではVPC内デプロイで審査を通しましたが、外部公開は不可、UIのロゴ表記も残す前提でブランド統制に配慮しました。
外部提供や厳格なブランド要件がある場合はCommunityが適さないため、Enterpriseの検討が必要です。
セキュリティ設計やネットワーク分離の勘所は生成AIのセキュリティ完全解説の原則に沿って事前に方針化すると移行が円滑です。
「社内限定・ブランド非変更・SaaS提供なし」を許容できるシーンに限定すれば、Communityはコスト最小で要件を満たせます。
[全社導入/SaaS提供/ブランド統制] 本格提供ならEnterpriseライセンス必須
自社SaaSへの組込みや全社SSO、ホワイトラベルが必須ならEnterpriseライセンス一択です。
Enterpriseはブランディング解除やSSO・マルチテナント管理など企業要件を満たし、価格はカスタム見積でTCOはインフラ費・ライセンス費・運用人件費の合算で評価します(参考: Dify Enterprise License – Microsoft Marketplace)。
私が見積依頼を行った際は、要件の粒度を揃えるほど提案が精密になり、不要な“保険的オプション”を外せると実感しました。
- ユースケース別の同時接続・RAG容量・ピークトラフィックを数値で提示する。
- SSO方式と権限モデル、監査要件(ログ保持・SLA)を事前に文書化する。
- 運用体制(オンコール/障害対応フロー)と責任分界点をRACIで明確にする。
見積後はPoC→段階リリース→部門横断展開の順で進めると、コストとリスクを抑えて全社導入を成功させやすくなります。
よくある質問(FAQ):Dify料金に関する疑問を全て解説
当セクションでは、Difyの無料・有料の範囲、価格、決定的な違い、無料でのビジネス利用可否を整理して解説します。
導入検討時に最もつまずきやすいのが、無料でどこまで試せるかと、どのプランを選べば業務要件を満たせるかという点だからです。
- Q. Difyの無料範囲はどこまでですか?
- Q. Difyの有料プランはいくらですか?
- Q. Dify無料/有料で何が決定的に違いますか?
- Q. 無料プランでビジネスユースは可能ですか?
Q. Difyの無料範囲はどこまでですか?
結論として、Cloud Sandboxは合計200クレジットと5アプリまで、Self-Hosted Communityはライセンス料無料だが制約があります。
無料は検証用途までで、商用や大量データ処理には適しません。
理由は、Sandboxのリソース上限が低く、Communityではロゴ削除とマルチテナントSaaS提供が禁止されているためです。
以下の小表に無料でできること・できないことをまとめます。
| 項目 | Cloud Sandbox | Self-Hosted Community |
|---|---|---|
| 料金 | 無料 | ライセンス料無料(インフラ費別) |
| メッセージクレジット | 合計200 | 制限なし(自前モデル/鍵前提) |
| アプリ数 | 5 | 制約なし(自社運用前提) |
| ロゴ変更 | 不可 | 不可(Powered by Dify固定) |
| マルチテナントSaaS提供 | 不可 | 不可(書面許可なしで禁止) |
| 想定用途 | PoC・軽い検証 | 社内限定利用 |
| サポート | 限定的 | コミュニティ中心 |
例えば、RAGで社内文書を検証するだけでも、取り込みとテストで200クレジットは早期に尽きがちです。
したがって、本格運用や顧客提供を想定するなら、有料プランやEnterpriseの検討が必要です。
- 出典: Subscription Management – Dify Docs
- 出典: License – Dify Docs
- 出典: Dify LICENSE(GitHub配布ファイル)
- 参考: GitHub Issue: ロゴ表記に関する公式回答
Q. Difyの有料プランはいくらですか?
結論として、Cloud Professionalは月額59ドル、Teamは月額159ドルで、いずれもワークスペース単位の課金です。
Enterpriseは個別見積もりで、Self-Hosted Enterpriseはインフラ費用とライセンス料、運用人件費を合算したTCOで判断します。
理由は、上限超過時の従量課金が公開されておらず、上限到達で停止する可能性があるため、リソースと価格の事前設計が重要だからです。
具体的には、Professionalは月5,000クレジットと5GBのナレッジ、Teamは月10,000クレジットと20GBのナレッジが提供されます。
一方、AWSやAzureのMarketplaceの時間単価は仮想マシン等のインフラ料金であり、Difyライセンス料は別です。
したがって、PoCならProfessional、本格運用ならTeam、データ主権やブランディング要件が厳しい場合はEnterprise見積もりが現実的です。
- 出典: Plans & Pricing – Dify
- 参考: Subscription Management – Dify Docs
- 参考: Dify Enterprise – Azure Marketplace
- 参考: AWS Marketplace: Dify Premium
費用対効果の考え方は、導入前にAIチャットボットの費用対効果ガイドを参考にすると整理しやすいです.
Q. Dify無料/有料で何が決定的に違いますか?
結論は、商用許諾、拡張性、サポート体制が決定的に違います。
理由は、Communityはロゴ変更不可とSaaS提供禁止で、Sandboxはクレジットとストレージが小さい一方、有料はリソースと権限が拡張されるからです。
例えば、有料CloudではAPIレート制限の撤廃や優先処理、ナレッジ容量の増強が提供されます。
さらに、EnterpriseはSSOやブランディング解除、公式サポートとSLAが用意され、厳格なガバナンスに適合します。
結果として、顧客向け提供や全社展開では、有料プランやEnterpriseが安全かつ現実的です。
一方、短期の技術検証や限定的な社内利用では、無料でも十分に価値があります。
リスク管理の観点は、あわせて生成AIのセキュリティ解説を参照すると判断が明確になります。
Q. 無料プランでビジネスユースは可能ですか?
結論として、無料プランでも小規模なビジネスユースは不可能ではありません。
ただし、クレジット上限やロゴ固定、機能制限により、継続運用や顧客提供には不向きです。
理由は、上限到達時の停止リスクやブランド統制不能、サポート体制の不備が、サービス品質と信頼性を損なうためです。
たとえば、月次の問い合わせピークでクレジットを使い切ると、翌月まで応答が止まる可能性があります。
実務で使うなら、月間利用量とRAGのデータ容量を試算し、ProfessionalやTeamでコストとパフォーマンスを事前評価してください。
最終的には、試算と小規模パイロットでリスクを把握し、有料プラン前提で計画するのが安全です。
RAG要件の見積もりはRAG構築ベストプラクティス、費用設計は費用対効果ガイドが参考になります。
まとめと次の一歩
DifyのCloudとセルフホスティングを俯瞰し、意思決定の要点を整理しました。
Cloudは上限到達で停止し得るリスク、Communityはロゴ変更不可・マルチテナント不可、EnterpriseはSSO等の強みとTCO精査が必須です。
要件と予算から逆算し、小さく検証しながら運用設計を前倒しすることが成功の近道です。
基礎と実務を最速で掴むなら、生成AI 最速仕事術で学びを強化しましょう。
現場で使える体系的スキルは、DMM 生成AI CAMPで今すぐ習得を始めてください。