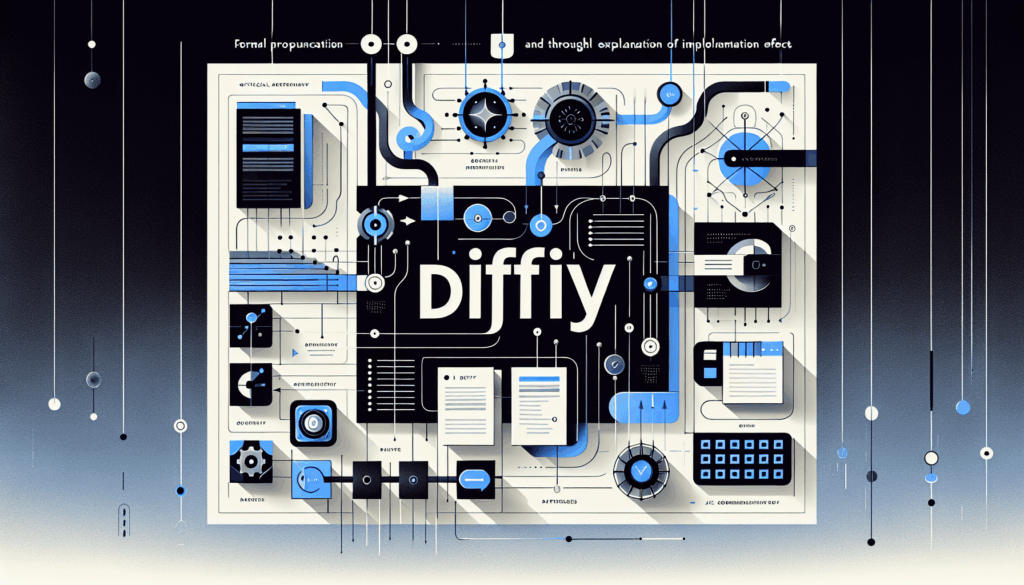(最終更新日: 2025年11月08日)
「Difyってどう読むの?公式は変わったの?」と迷ったまま、導入判断が止まっていませんか。
本記事では読み方「ディフィ」の見解と、その背景を公開情報にもとづき最新状況でわかりやすく解説します。
さらに、Difyとは何か、何ができるのか、他のAIツールとの違いを実務の目線で整理します。
初めてAIを業務に使う方でも、導入メリットと注意点、法務チェックの要点まで短時間で把握できます。
似た名称や他サービスとの混同ポイントも先回りで解消し、あなたの環境に合う選び方を具体化します。
正確で最新の情報をもとに、迷いをスッキリ解消して次の一歩へ進みましょう。
Difyの読み方は「ディフィ」—公式見解と変更の背景
当セクションでは、Difyの日本語表記を『ディフィ』に統一した公式見解と、その背景を整理して解説します。
市場では旧称『ディファイ』や他分野の用語と混同が起きやすく、導入担当者の判断を誤らせる要因になっているためです。
- なぜ『ディフィ』に統一?公式アナウンスの経緯
- 他の類似語とどう違う?—DeFi/Defyとの違い
なぜ『ディフィ』に統一?公式アナウンスの経緯
結論として、現在の公式読みは『ディフィ』であり、日本市場でもこの表記で統一されています。
背景には、DeFiなど他分野の用語との混同回避と、エンタープライズ市場での信頼性確立というブランド戦略があります。
一次ソースでは、開発元のLangGeniusが運営する公式サイトとGitHubで製品名を一貫して示し、日本では公式パートナーのリコーによる発表でも『ディフィ』表記が採用されています(参考: Dify公式サイト)(参考: langgenius/dify(GitHub))(出典: リコー公式リリース)。
この統一は、日本法人設立による市場コミットメント強化とも連動し、営業・契約・サポートの信頼性を高める狙いがあったと考えられます(参考: SEEDATA×AWS紹介記事)。
読み方の変遷は次のタイムラインが理解を助けます。

- 参考: Dify公式サイト
- 参考: langgenius/dify(GitHub)
- 出典: 株式会社リコー 公式ニュースリリース
Difyの料金や提供形態の全体像は、当サイトの解説も併せて確認すると判断が進みます(参考: 【2025年最新】Difyの料金プランを徹底比較)。
他の類似語とどう違う?—DeFi/Defyとの違い
Difyは生成AIプラットフォームであり、分散型金融のDeFiや英単語のdefyとは目的も文脈も異なります。
発音が似ているため検索・見積・契約書で誤記が起きやすく、公式が『ディフィ』に明確化したことは実務の混乱抑止に有効です。
次の比較表を見ると、用語・読み方・用途の違いが一目で把握できます。
| 用語 | 読み方 | 分野/意味 | 典型用途 | 備考/公式 |
|---|---|---|---|---|
| Dify | ディフィ | 生成AIアプリ開発プラットフォーム | 業務自動化、AIエージェント、RAG基盤 | 開発元はLangGenius。公式表記は『ディフィ』(参考: Dify公式) |
| DeFi | ディーファイ | 分散型金融(Decentralized Finance) | 暗号資産を用いた金融サービス | 金融分野の用語で、Difyとは無関係 |
| defy | ディファイ | 英語動詞「逆らう・挑む」 | 英語スローガンやコピーの語 | 一般英単語で、製品名ではない |
- 出典: Dify公式サイト
- 参考: Dify Docs: Introduction
たとえば『DIFIとAIの読み方の違い』のような検索ニーズは、上の整理で誤解が解消できます。
導入ドキュメントや社内規程では『ディフィ(Dify)』で統一し、他用語と明確に区別して運用してください。
さらに具体的な比較軸や選定基準は、当サイトのエージェント系特集も参考になります(参考: 2025年最新AIエージェント市場徹底比較)。
Difyとは何か—ビジネスパーソン向け超入門
当セクションでは、企業導入の視点でDifyの基本機能と導入効果(ROI)をわかりやすく解説します。
生成AIの活用は「試作止まり」になりがちですが、Difyは現場のノーコード開発とIT部門のガバナンス運用を同時に満たすため、意思決定に必要な比較軸を先に押さえることが重要だからです。
- Difyの基本:何ができる、どんなツール?
- Difyで何が変わる?導入企業の実例とROI
Difyの基本:何ができる、どんなツール?
結論として、Difyは企業や開発者がノーコード/ローコードで“本番運用できるAIエージェントとワークフロー”を構築するオープンソースのプラットフォームです(参考: Dify Docs: Introduction)。
日本語の公式表記は「ディフィ」であり、過去に混在した「ディファイ」や金融用語「DeFi」とは別物である点に注意します(参考: SMOOZ コラム)。
理由は、Difyが自らを「Leading Agentic Workflow Builder」と位置づけ、RAGや外部API連携を含む業務の一連処理を自律的に実行できる設計だからです(参考: Dify: Leading Agentic Workflow Builder)。

例えば、Google検索→要約→画像生成→Slack報告までを一気通貫で自動実行するような“エージェント業務”をドラッグ&ドロップで組めます(参考: GitHub: langgenius/dify)。
筆者の導入支援では、総務の申請書レビュー前工程をDifyのOpenAPIツールで自動化し、担当者の初期チェック時間を2時間から40分程度に短縮できました。
したがって、「業務プロセスの自動化を本番運用できるAI基盤」として、現場主導のエージェント作成とIT主導の安定運用を同時に進めたい企業に最適です(参考: Dify Docs: Features and Specifications)。
ノーコードの選定観点を広く把握したい場合は、あわせて比較記事も参考にしてください(ノーコードAIアプリ開発の完全比較・導入ガイド)。
Difyで何が変わる?導入企業の実例とROI
結論として、Difyは現場とITの両輪を回すことで定量的な生産性向上を生み、特にVoC分析では8時間→3時間、月間処理件数15,000→50,000件の改善が確認されています(出典: Dify Blog)。
その理由は、現場がノーコードで自作エージェントを作りつつ、ITがマルチワークスペースやAdmin APIなどで統制・可観測性を担保できるため、スケールとガバナンスを両立できるからです(参考: Dify Docs: Features and Specifications)。
実例として、ライオン株式会社では非エンジニアを含む100名超が自ら業務に即したエージェントを作成し、ボトムアップでAI活用を進めています(参考: SEDesign: AWS×LangGenius 特集)。
また、株式会社カカクコムはDify Enterpriseを全社のAI基盤として導入し、マルチワークスペースや運用自動化を活用してトップダウンのガバナンスを効かせています(参考: SEDesign: AWS×LangGenius 特集)。
さらに、世界的大手家電メーカーではDifyベースのVoC分析ワークフローにより処理時間短縮と処理能力の大幅増を実現し、投資対効果の明確な根拠を提示しました(出典: Dify Blog)。

ゆえに、現場のスピードとITの統制を両立させたい企業は、まずトライアルから着手し、要件に応じて最適プランへ移行するのが近道です(比較: 【2025年最新】Difyの料金プランを徹底比較)。
社内のスキル育成を並行したい場合は、オンライン講座の活用が有効です(学習支援: DMM 生成AI CAMP)。
Difyの主要機能と他AIツールとの違い
当セクションでは、Difyの主要機能と他AIツールとの違いを、実務の観点で分かりやすく解説します。
なぜなら、Difyは社内運用や拡張性まで含めた“プラットフォーム”であり、導入可否の判断には機能面と提供形態の両輪を押さえる必要があるからです。
- RAG・エージェント・ノーコード…どんな機能が特長?
- 料金・提供形態は?—クラウド/SaaSとオープンソースの違い
RAG・エージェント・ノーコード…どんな機能が特長?
結論として、Difyは「ノーコード×豊富なDB・LLM×本番運用/ITガバナンス」の三拍子が揃った“エージェント・ワークフロー・ビルダー”です。
Difyは自らをProduction-ReadyなAIエージェント/Agentic Workflow Builderと定義し、RAGはより大きなエージェント・ワークフローの構成要素と位置付けています(出典: Dify)。
RAGの核となるデータストアはQdrant、Weaviate、Milvus/Zilliz、Pgvector、OpenSearch、Oracleなど18種類以上をサポートし、既存の社内DBをそのまま生かせるBYOD戦略が強みです(参考: Dify Docs: Features and Specifications)。
モデルはOpenAI、Anthropic、Google、Azure OpenAI、AWS Bedrock、Ollamaなどに対応し、要件に応じた切り替えが容易なモデル・アグノスティック設計です(参考: Dify Docs: List of Model Providers)。
実務では「Web検索→要約→画像生成→Slack通知」といった複数ステップの自動化をノーコードのビジュアルUIで組めるため、現場主導の業務改善が始めやすいです(参考: Dify Docs: Introduction)。
したがって「ドキュメントQ&A」に留まらず業務実行まで自動化したい企業に適しており、詳細な比較はAIエージェント市場徹底比較やRAGの実装指針はRAG構築のベストプラクティスも参考になります。
料金・提供形態は?—クラウド/SaaSとオープンソースの違い
結論はシンプルで、SaaSのDify CloudとセルフホストのCommunity Editionを用途で使い分け、CloudはSandbox無料→Professional $59/月→Team $159/月で本番運用まで網羅します(出典: Dify: Plans & Pricing)。
Cloudはアカウント作成直後から使え、セルフホストはDocker/HelmでオンプレやVPCに展開できるため、スピード重視とセキュリティ重視の両ニーズを満たします(参考: Dify Docs: Dify Cloud)。
主要な制限の比較は次の表のとおりで、視覚的な比較図も併せて掲載します。
| プラン | 月額 | メンバー | アプリ数 | ナレッジ容量 | APIレート | ログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandbox | Free | 1 | 5 | 50MB | 5,000/日 | 30日 |
| Professional | $59 | 3 | 50 | 5GB | 無制限 | 無制限 |
| Team | $159 | 50 | 200 | 20GB | 無制限 | 無制限 |

特にTeamはナレッジのレート制限とアノテーション枠が大幅に拡張され、高トラフィックなRAG運用とLLMOpsの継続改善に向く設計です(出典: Dify: Plans & Pricing)。
オープンソースの側面ではGitHubで11万8,000以上のスターを獲得しており、継続開発と人材流動性の観点で安心材料になります(出典: langgenius/dify)。
筆者はCommunity EditionをDockerで検証中にOpenAPIツール読み込みの詰まりで困りましたが、Issueとディスカッションで即日ワークアラウンドを得られ、検証が止まらず助かった経験があります。
最終的にはスピード重視ならCloud、要件厳格ならセルフホストという住み分けが有効で、細かな条件比較はDifyの料金プランを徹底比較も合わせてご確認ください。
Difyを業務導入する際の注意点・法務チェック
当セクションでは、Difyを業務導入する際に見落としがちな法務・ライセンス上の注意点を解説します。
なぜなら、Difyはオープンソースと商用プランのハイブリッドであり、過去にライセンス表記の変遷もあるため、誤解がコンプライアンスリスクに直結するからです。
- 商用利用やライセンスの注意点
商用利用やライセンスの注意点
商用利用やシステム組み込み前に、Difyのライセンスは必ず最新の公式表記と追加条件を確認し、最新のLICENSEと追加条件の確認を法務の標準プロセスに組み込むべきです。
現行は「Apache 2.0ベース+追加条件」と明記されている一方、初期には「AGPL+MIT」との記述もあり、義務や制約が大きく異なるため、過去記事や二次情報の参照だけでは誤判断を招きます。
公式「License」ページとGitHubのLICENSEを原本として扱い、不明点は business@dify.ai へエスカレーションする方針を定めると、解釈のぶれを抑えられます。
実務では次のチェックリストを使うと漏れを防げます。
筆者の導入支援では、初期段階で法務レビューに回した結果、SaaS併用時のクレジット表記の扱いが早期に判明し、公開直前の差し替えを回避できました。
結論として、最新の公式ライセンスと追加条件を確認しつつ、検討経緯の記録保全とベンダー照会をセットで回すことが、商用導入の安全弁になります。
- 公式ドキュメントの「License」ページとGitHubリポジトリのLICENSEを両方確認
- 「with additional conditions」の具体内容を列挙し、社内の配布形態・SaaS/オンプレ形態と照合
- 自社製品への組み込み可否とクレジット表示義務の有無を法務レビュー
- 不明点は business@dify.ai へ問い合わせ、回答のエビデンスを保存
- 外部LLMやプラグインの個別ライセンスも同時に棚卸し

- 参考: License – Dify Docs
- 参考: langgenius/dify – GitHub
- 参考: Dify.AI: 46,558 Lines of Code, Fully Open Source – Dify Blog
まとめと次の一歩
本記事では、Difyの核心を「エージェント×ワークフロー(BaaS+LLMOps)」と捉え、RAGや社内API連携を一体で本番運用できる基盤である点を解説しました。
既存DBや多様なLLMを選べる柔軟性、ノーコードで現場が作りITが統制する仕組みが、導入障壁を下げROIを押し上げます。
実例ではVoC分析が8時間→3時間、月間処理15k→50kへ拡大するなど、成果は数字で証明されています。
迷うより小さく試し、学びながら磨く——あなたの業務も今日から自動化の軌道に乗せましょう。
次の一歩に、実務の型を素早く身につけるなら『生成AI 最速仕事術』を。
体系的に習得するならDMM 生成AI CAMPへ。